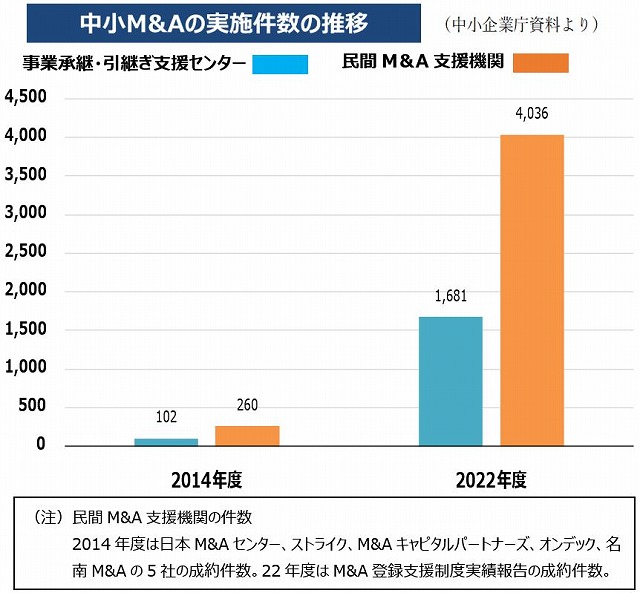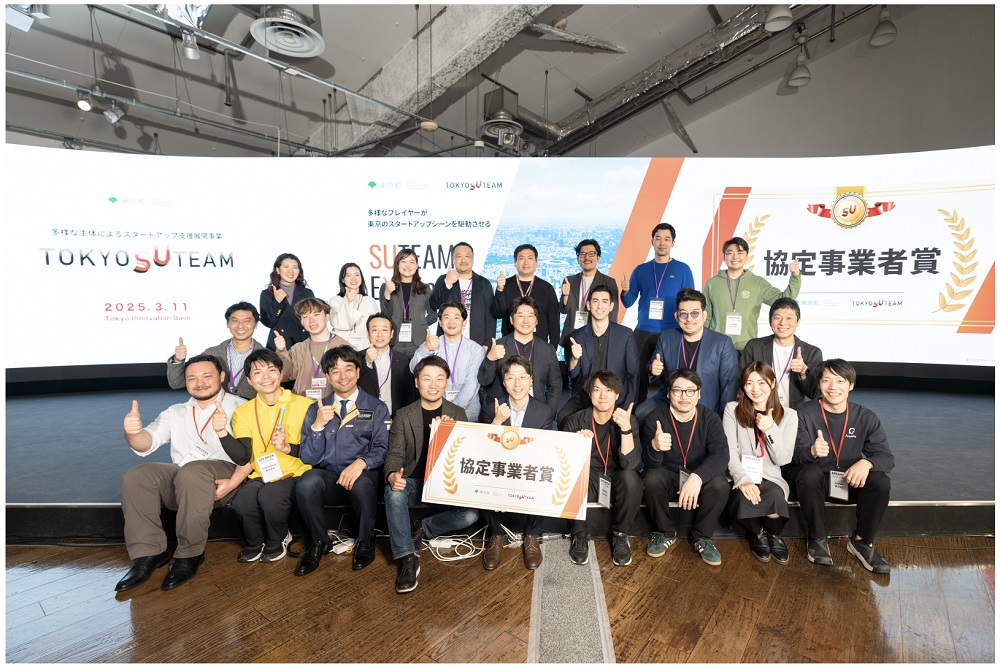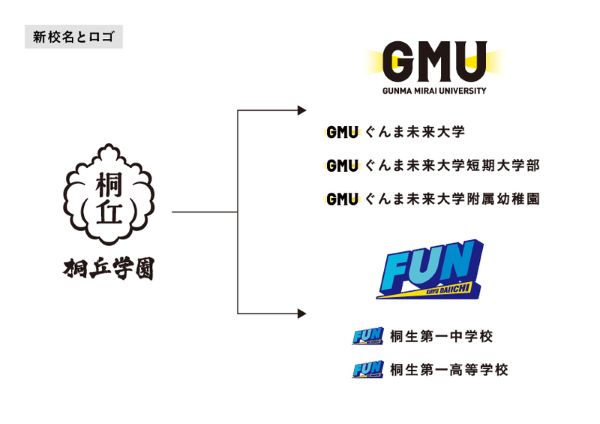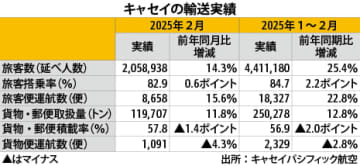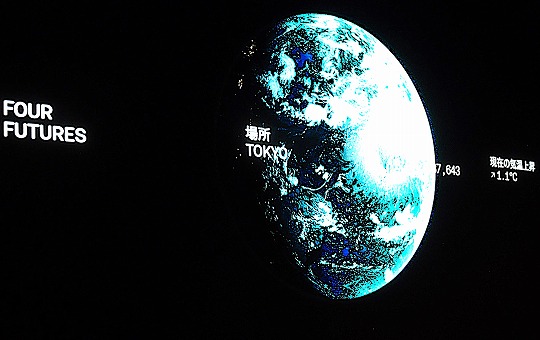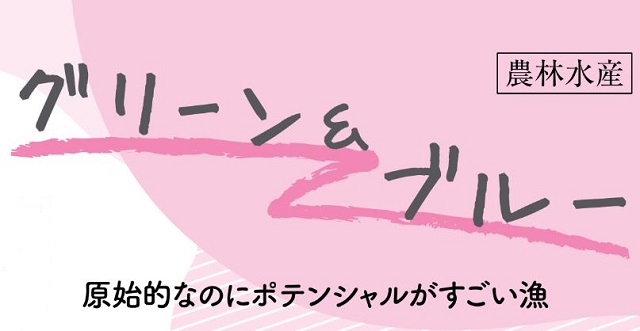かつて手話の使用が日本はじめ世界で禁止されるという歴史があったことはご存じだろうか。手話が言語としての市民権を得たのはつい最近のことで、国連総会において、手話言語が音声言語と対等であることが採択されたのは、2017年のことだった。
その決議を受け、「手話言語の国際デー(International Day of Sign Languages)」が9月23日と定められるなど、手話に関する意識が高まっている。
手話は、あらゆる情報を即座同時に伝え、受け取る技法ともいわれている。本稿ではろう者への理解を深めることはもちろん、手話が持っているポテンシャルに注目し、手話がもたらす新たなコミュニケーションの可能性に迫りたい。
▼ブレストと手話
私は神奈川県・鎌倉に居住しながら、現在、青森県五戸町にある東北メディカル学院という理学療法士や作業療法士養成の専門学校に勤務している。五戸町にも少子高齢化の波が押し寄せ、まちの活性化が喫緊の課題となっている。
そのような中、筆者が関与している鎌倉で生まれたまちづくり活動の「カマコン」を五戸町でも学生も巻き込み開催することになった。名前はカマコンにちなみ「五之魂」(ごのこん)だ。
活動内容は、まちの活性化に関するさまざまなアイデアをブレーンストーミング(ブレスト)で生み出し、それを具体的な行動に移してゆこうというものである。新型コロナウイルス禍で開催が何度も見送られる中、今まで6回開催、15のテーマについてブレストが行われてきた。
そのなかでも、昨年5月「五之魂」第2回のテーマでは、町の手話サークルの人たちが「五戸町を手話の街にしたい」とのプレゼンを行い、ブレストを行った。当日はこれ以外に2テーマあり、参加者約25人がめいめいのテーマに7~8人ずつ分かれブレストを実施。手話のテーマにはろう者の方や通訳など手話関係者が過半数を占めていた。
なお、この手話以外のテーマのブレストチームにはろう者の方は入っていない。注目すべきはそのアイデアの数である。手話以外のろう者の入らないブレストチームのアイデア数が20~30程度であったものが、手話のチームでは40を超えるアイデアが出たことだ。この数の差は一体、何を意味するのだろうか?
五戸町では昨年4月から、手話を言語として認める手話言語条例が施行された。5月にはブラジルで開催された、ろう者のためのオリンピックである第24回夏季デフリンピック競技大会陸上競技男子100メートルで、五戸町出身の佐々木琢磨氏が、日本人初の金メダルを獲得し、町では祝賀行事が開催された。
とりわけ私の手話への関心を深めたのが五戸町長の若宮佳一氏が自ら行った手話による祝辞であった。町長が「佐々木さん金メダルおめでとう」と手話で表現された際、右手を背中から振り上げる格好で金メダルに輝く佐々木選手の名前を表現されたのだった。手話で「佐々木」は「佐々木小次郎」の剣術のスタイルが語源であるとの町長の解説に、がぜん手話に興味を持つことになった。
▼手話は言語の一つ
さて、「手話言語の国際デー」や「手話言語条例」がなぜ制定されたのか?
ろう者のコミュニケーション手段として、かつて、ろう学校でコミュニケ―ションツールとして主に教えるのは「口話法」であった。それは、聞こえない人にも声を使って会話ができるようにする、またそれを手がかりに日本語を身に付けられるようにする、といったものであった。
ろう学校での手話の使用は禁止されていた。これは日本だけでなく世界的にその傾向があったという。手話の使用を認めると、ろう児は厳しい口話法の訓練よりも手話に流れてしまい、口話法による日本語の獲得ができなくなる、との考え方があったらしい。
ただ、実際のところは、手話を禁止し、そのような厳しい訓練を行ったとしても、口話法によって日本語を獲得することは困難であった。また、ろう学校が手話を禁止し続けてきたにもかかわらず、ろう者はろう者同士の中で手話を使い続け、次代に伝承してきた。
そして、近年になって手話には音声言語の音韻に相当する構成要素があることなどが発見された。日本では、手話が日本語とは異なる統語規則を持った言語であることが知られるようになったのは、1990年代中頃になってからである。
つまりかつて、手話は言語でなく、話し言葉より劣ったものとみなされていたものが、言語としての市民権を得たのはごく最近のことである。それを広く国民に認知されることを目的で制定されたのが先の「手話言語の国際デー」や「手話言語条例」であった。
▼手話の種類
手話には大きく分けて、日本語対応手話と日本手話の二つがある。日本手話は幼い頃から聞こえないろう者が中心となって使われているもので、ろうコミュニティーで自然に生まれた。手の動きに、顔や頭の動きや空間の使い方が加えられる。日本語対応手話は、主に難聴者や日本語獲得後に失聴した人に使われており、日本語と同じ語順で単語を手の動きで表現する。
▼手話vs話し言葉
ではブレストでなぜ手話チームのアイデア数が多かったのか?
まず今回のブレストチームを分析しよう。通常チームによって差が出るのは、ブレストの経験値やチームをリードするファシリテーターの手腕に依存するところが大きく、またブレストテーマにも左右される。
第2回の「五之魂」では3チームに分かれ、①チームごとにテーマが異なる②参加者のブレスト経験はほぼ初心者③訓練されたファシリテーターは参加していない④1チームだけ、ろう者が手話で参加。3チームの条件は①と④を除き同じではあるが、決定的に異なるのは手話をテーマにブレストしたチームだけ、ろう者が参加していたことで、ろう者、通訳など、ろう関係者は手話でブレストし、アイデア数が抜きんでていたことだ。
これは話し言葉と手話の違いに原因があるのではないか。話し言葉を使う参加者については、特にブレスト初心者は話し言葉で思考をめぐらし、価値のあるアイデアか?はたまたないアイデアか?を考えぬいた上で発語する。
またそれもアイデアについて解説を付した、話し言葉で発語することが多い。これに対し手話での参加者はアイデアを画像処理するように瞬時に表現している。これは話し言葉のブレスト熟練者と同様の手法である。
つまり、話し言葉は言葉が時間軸上に並ぶ線状のようなものであるのに対し、手話は、言葉の全ての要素が映像のように一度に表現されることから、表現にかかる時間が手話の方が短いという違いがある。
▼日本手話
さらに手話の中でも日本手話では、手や指の形、動きとともに、視線、顔の表情、首振りなどの非手指動作(NMM=Non-Manual Markers)が文法の核心部分を担っている。そのため、顔の表情は感情を表現するためだけではなく、文法の一部として言語に組み込まれている。
また、CL(Classifier)と呼ばれる、ジェスチャーを文法化したような技法があり、目で見たものの状況を言語化し再現することに優れているといわれている。日本で初めて日本手話を第一言語として教える明晴学園の校長を務めた斉藤道雄氏によると、「たとえば日本語で『ボールが地面をはね返った』というのを、手話ならどんな大きさのボールがどれくらいのスピード、角度でどの方向にはねていったのか、瞬時に動画のように表現します。だからこそ、ろう者は、そのような表現ができない音声語を『もの足りない』と思うようです。」と述べている。
また斉藤氏によると、ろう者の寄宿舎でのエピソードとして、仲間でお金を出しあい、じゃんけんで勝ったものが代表して映画を鑑賞し、帰って手話で映画を臨場感あふれるように仲間に再現したという。
▼手話のポテンシャル
ブレストでのアイデア出しでは、解説的になりがちな初心者の話し言葉でのブレストに対し、ブレスト初心者ではあるが、手話で瞬時にアイデアを表現できる、ろう者のブレストが優位であったのだ。
つまり、手話が言語でありながら話し言葉では限界のある情報の量や質を表現できる可能性があるのではないか。手話は、ろう者の言語としての機能を果たすことは分かっているが、どうも、手話で見えてくる新たなコミュニケ―ションがあるようだ。
ろう者は300人に1人といわれているが、手話は、ろう者だけの言語でなくいわゆる聴者側にいる話し言葉の使い手としても、ろう者とのコミュニケ―ション以外の目的で修得していく時代が来るのではないか。
現在コロナ禍でテレワークなどオンラインによるコミュニケーショが一気に広がりを見せているが、対面のような相手との空気感をはかりながらの対話が難しくなっているといわれている。
このような時こそ手話から学ぶことは、まずろう者が相手の表情をしっかり捉える技法、そして相手に自分の意志をしっかり伝える豊かな表情の技法である。
しかしそれだけではない、手話のもつあらゆる情報を即座同時に伝え、受け取る技法に注目したい。とりわけ日本手話は、デジタル化で軽視されかねない人との温もりある関係性を担保しながら、アナログでありながらも、ろう者の技量レベルにもよるが、デジタル的な高速大容量のコミュニケ―ションが可能である。そのように考えると、手話という言語にはこれからますます活用されるポテンシャルがあるのではないか。
まずは義務教育の場で、手話を英語など第2外国語と同じ位置づけで履修できるようにし、手話やろう文化への理解を深めることから始めるべきだろう。また、社会人としてのコミュニケーション力強化のため、企業研修での手話講座の導入などが今後必要ではないか。手話がこれからの人間社会に大きく貢献してゆくことは間違いなさそうだ。
【筆者略歴】
植嶋 平治 (うえしま・へいじ)
前青山学院大経済学部非常勤講師
学校法人臨研学舎東北メディカル学院専務理事、東北医療福祉事業協同組合理事。
社会福祉法人しばた会理事長、医療法人M&Bコラボレーション常務理事
1976年、大阪市立大商学部卒
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)