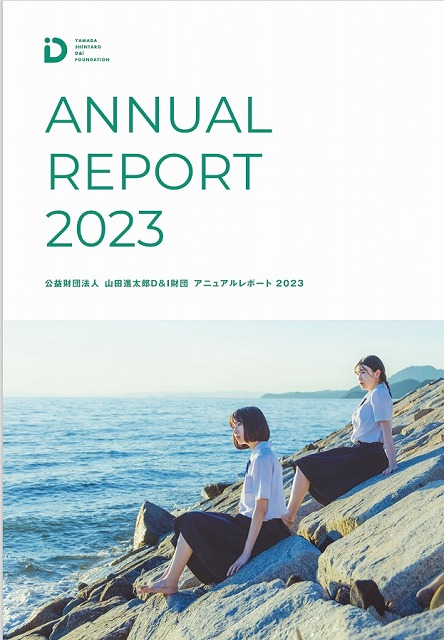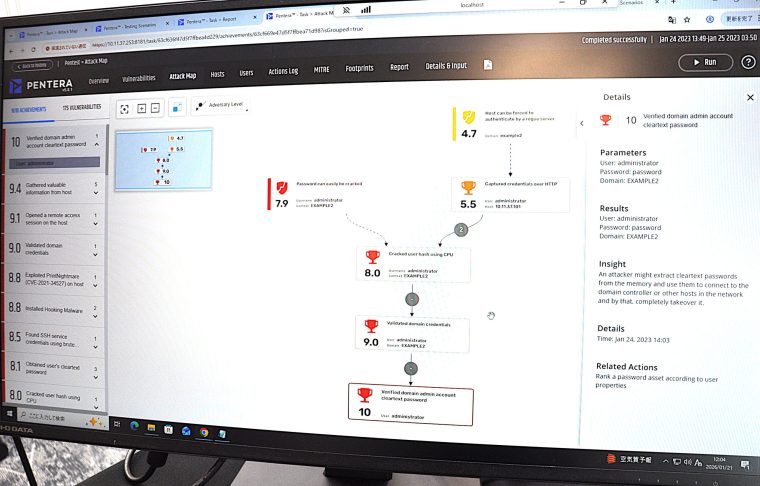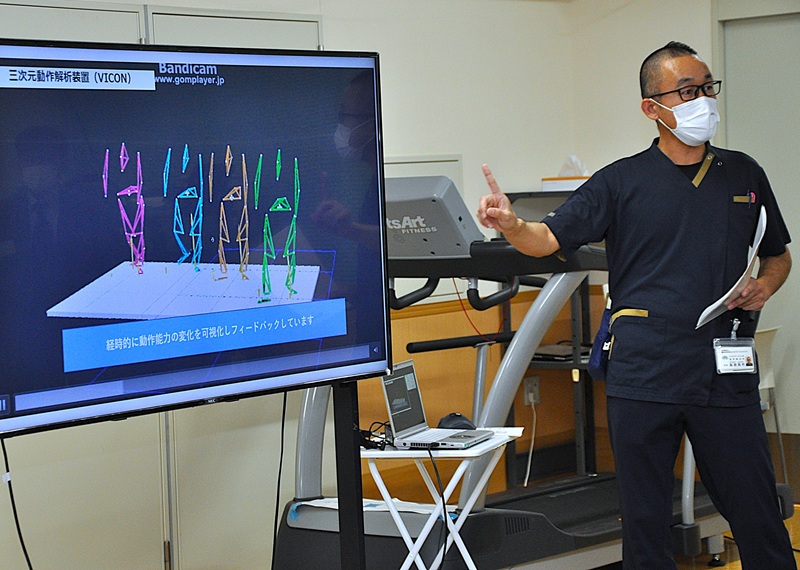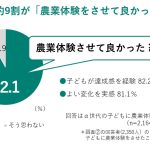ビニールハウスの屋根越しに朝の光が差し込み、朝露をまとった青葉の匂いが立ちのぼり始める。静まりかえっていたハウス内に、作業着姿の人たちがそれぞれの作業に取りかかるため、次々と集まってきた―。
ここは、エスプールプラスが運営する千葉県市原市の「わーくはぴねす農園」だ。現在、全国60カ所に農園は広がり、知的障がい者ら約5000人が、一般企業の一員として働く場を支えている。農園は企業向けの貸し農園という形を取り、障がい者の雇用を進めたい企業と、働く意欲を持つ人たちをつなぐ役割を担ってきた。
この日訪ねたのは、事業を率いる大橋王二(おおはし・おうじ)社長。現場の農園では、上谷周人(かみたに・しゅうと)さんと重田洋平(しげた・ようへい)さんが農作業にいそしんでいた。

▽就職できる選択肢を社会に増やしたい
わーくはぴねす農園は2011年、ここ市原市でスタートした。大橋社長は、創業の理念をこう語る。
「重度の知的障がいがあっても、人生の中で就職するという経験にたどり着ける社会を作りたい。そのためには、就職できる選択肢そのものを、社会の側が増やしていく必要があると考えました」
当初、「働きたい気持ちはあるのに、合う環境が見つからない人が非常に多い」という現実とぶつかった。福祉事業所や特別支援学校を回る中で、支援の在り方や仕事内容によっては、本人が仕事の手応えを感じにくいことも実感した。そこで着目したのが、野菜作りだった。
「自分がやった仕事の成果が、目に見える仕事であることが大事だと思ったんです」
育てる、収穫する、誰かに渡す。成果が目に見え、人に喜ばれる循環が、働く意味を実感しやすいと考えた。
農園を整備し、障がい者雇用を促進したい企業に貸し出す。企業は自社の雇用として農園の仕事を位置付け、障がいのある人は一般企業の社員として働く。この仕組みは、当時ほとんど前例のないモデルだったが、現在では約700社が導入し、定着率は92%を超えている。
▽畑仕事で生まれる「仕事の実感」
ブロッコリーの畝の前で、上谷さんがハサミを手に、根元を確かめ、ゆっくりと刃を入れると、ずっしりとしたブロッコリーが手に収まった。
大橋社長はその様子を見て、「立派に育てたね」と声をかける。サポート役である農場長とともに、水やりの回数や日々の工夫を一つ一つ確認しながら、「どこが良かったのか」「何が成果につながったのか」を具体的に伝え、上谷さん自身が自分の仕事を実感できるよう言葉を添えていく。
わーくはぴねす農園では、作業ができるかどうかで人を区別するのではなく、本人の特性や得意な点に合わせて役割や手順を組み立て、仕事として成り立たせている。
上谷さんは現在、水やりや収穫に加え、袋詰めの工程も担っている。袋詰めされた野菜は地域のマルシェで販売されている。
仕事は「楽しい」と即答する。
「10年続けてきましたけど、飽きたことはありません。ずっと働きたい。一生懸命頑張って、給料をもらって生活したい」
野菜が育っていく過程を見ることや、誰かに渡して喜ばれることが、働く楽しさにつながっているという。
給料で買ったサッカーボールやスパイクは、休日に楽しむフットサルで使う。自分で稼いだお金で欲しいものを買えることは、生活の自信にもつながっている。

▽父親が感じた「社会人になった」という実感
上谷さんの父親・佳弘さん(私立・光風台三育小学校長=市原市)は、農園で働き始めた頃の変化を「意識が変わった」と振り返る。
以前、隣県で通っていた作業所では、同じ作業を繰り返す日々の中で息子の表情が次第に硬くなり、家に帰っても仕事の話をほとんどしなかったという。
わーくはぴねす農園では、最初に出会った農場長から「社会人なのだから、自分で通勤しなさい」と指導された。送り迎えが当たり前だと思っていた親にとって、それは大きな転換だった。電車で通勤し、仕事に向かう姿を見て、息子が社会の一員として働いていることを実感したという。
自分で育てた野菜を家族や周囲の人に渡し、喜んでもらうことが日々の糧になっている。
「ああ、ここが息子の居場所なんだな、と感じました」
息子の笑顔を見て、そう感じ取った佳弘さん。お金以上に、社会の中で役割を果たせたことが、親としての安心にもつながっている。

▽次の10年へ――広がる選択肢
大橋社長自身も、若い頃に進路に迷った経験を持つ。大学時代、将来像を描けずに休学し、東南アジアやインドの貧困地域を旅した。路上で出会った子どもたちは、厳しい環境にありながらも夢を語っていた。その姿に触れ、「ハンディキャップがあることで未来が制限される状況を、少しでも減らしたい」と強く思うようになったという。
障がい者雇用が5000人規模に広がった今、大橋社長は数字以上の変化を感じている。一人暮らしやグループホームに挑戦する人や、趣味を広げる人など、農園での経験を通して、一人ひとりの人生の選択肢が広がっている。
「人数や農園の数で示せる成果以上に、就職をきっかけに起きた一人ひとりの変化を現場で見てきた実感があります」
それこそが、この事業が社会に与えた最大のインパクトだ、と大橋社長は語る。
農園はこれまで大都市圏を中心に展開してきたが、「この1、2年を目安に、地方での展開も進めていきたい」と大橋社長。地域の条件に応じて形を工夫しながら、新たなモデルにも挑戦し、働く場の選択肢を広げていく考えだ。
ビニールハウスの中で育つ野菜のように、ゆっくりでも確実に根を張る働き方。この取り組みは、これからも多くの障がい者の人生に、着実に変化をもたらしていく。
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)