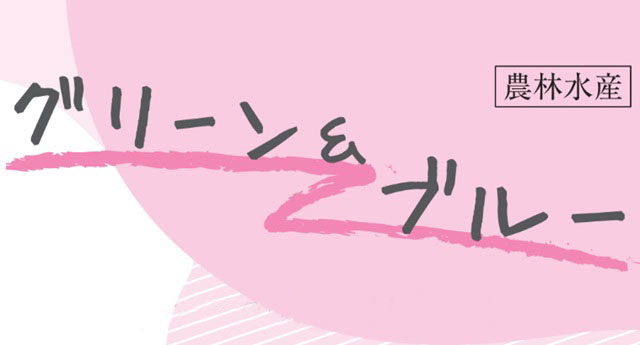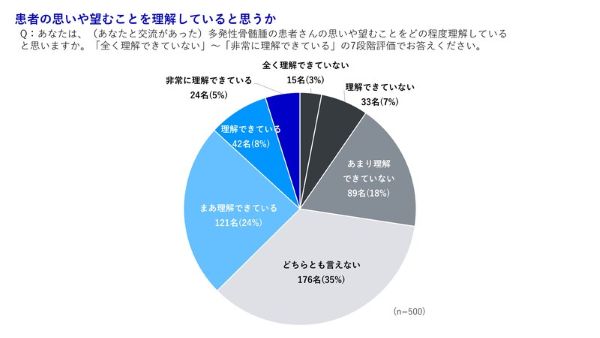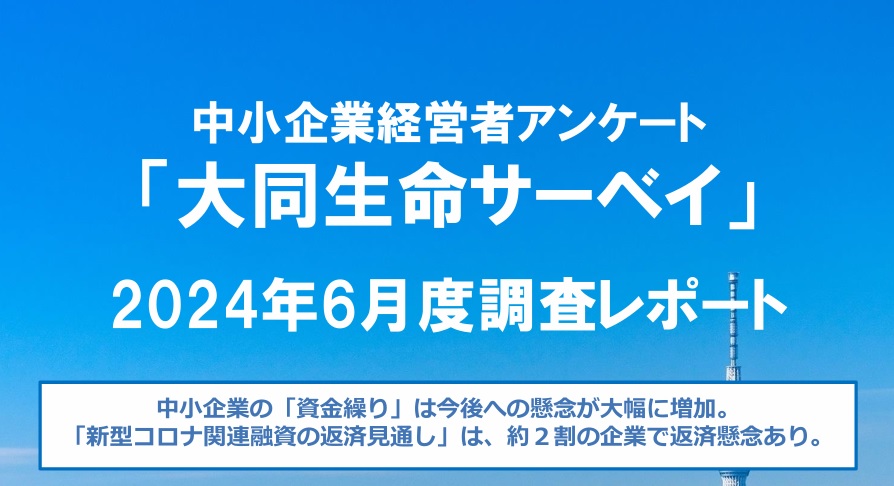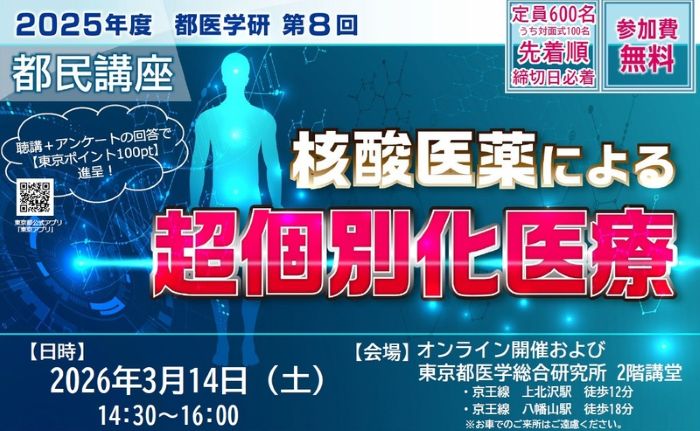木々が成長して太ると、隣の木との間隔が狭くなり、互いに圧迫し合うようになる。放っておくと成長に悪影響を及ぼし、下手をすると枯死する木も出てくる。木々が込み合うと地表に日差しが届かなくなり、背の低い草木が枯れて土がむき出しになる。そこに雨が降ると土が流れ出し、災害を引き起こすリスクが高まる。
そこで何本かの木を間引き、適切な密度を確保することで木の成長を促進し、森の環境を適切に保つことが重要になる。その作業が間伐であり、間伐によって生産された木材が間伐材である。現在、そのことは広く認知されていて、間伐材やそれを利用した製品も、間伐の推進に寄与するエコ商品として評価を得ている。
ただ、実は木材のマーケットでは「間伐材」という商品は流通していない。山で生産された丸太は市場に出荷されたり、製材工場や合板工場に直接販売されたりするわけだが、その際にその丸太が間伐によって生産されたものなのか、あるいはすべての木を伐採する皆伐(かいばつ)で生産されたものなのかは明示されていない。原材料の丸太が間伐材かどうかわからないのだから、製材品や合板もそれが間伐材でつくられたのかどうかはわからない。
間伐材というと品質に難のあるものと捉えられがちだが、必ずしもそうではない。適切に間伐を行えば残った木が粒ぞろいの品質になっていくのが道理で、その山でまた間伐を行えば、質の良い間伐材丸太が生産される。200〜300年くらいも木を育て続ける場合は、樹齢100年とか150年の間伐材も出てくる。
実際に間伐は各地で行われているのだから、間違いなく間伐材は生産されている。しかし、どれが間伐材なのかを特定するのは難しい。伐採業者と直接つながっていれば確かめる術(すべ)もあり、それを根拠に間伐材であることをアピールしている製品もある。だが、そういうケースは稀(まれ)だろう。
間伐材という言葉が持つエコ商品としての響きの良さが広く行き渡る中で、林業・木材業関係者はその言葉が歩き続けるまま放置してきた。木を伐(き)ることに抵抗感を示す人にも、間伐の意義なら理解してもらいやすく、木材利用キャンペーンのマスコットとして適役だった。だが、そろそろ卒業しなければならない。
林業への理解を深めてもらうためにも、まずこの実態を広く知ってもらうことから始めたい。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.39からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)