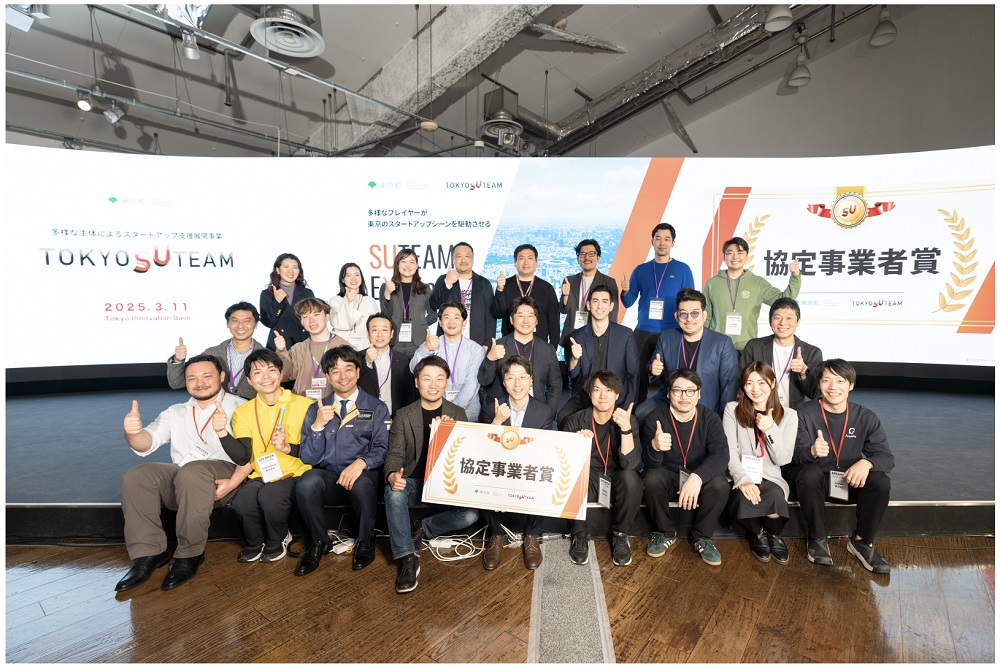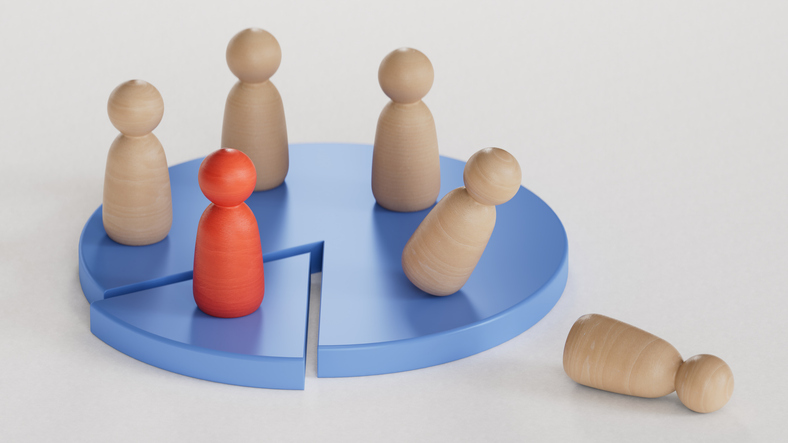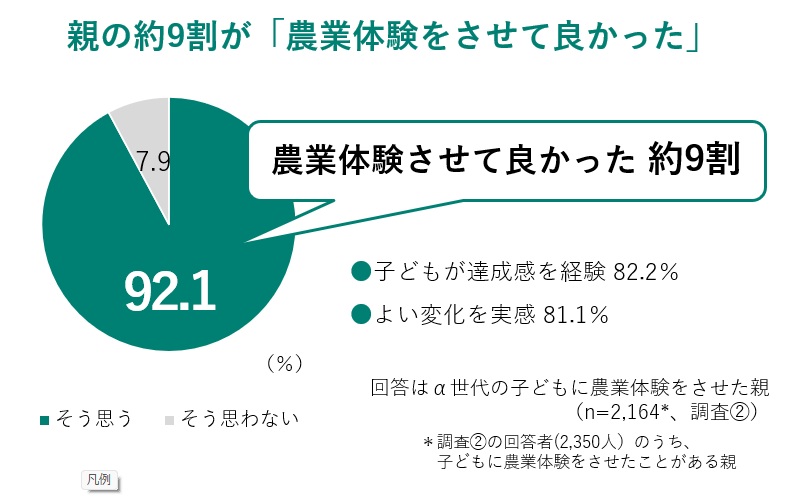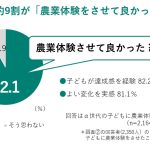埼玉県を中心に関東地方で量販店を展開している株式会社ヤオコー(川越市)が、国産の果物を使ったスイーツを開発、事業や収益の拡大だけでなく、素材の安定的な調達、食品廃棄の削減など社会的にも貢献できる事業モデルを拡充している。
ヤオコーは、経営理念として「豊かで楽しく健康的な食生活を提案する」を掲げている。店頭のデリカ(総菜)部門では主食、主菜、副菜を提供し、パンを扱うベーカリー部門もあるが、食事のシーンの最後であるスイーツを自社製品としては扱っていなかった。そこで、埼玉県・東松山に工場を新設し、一昨年からプリンと杏仁豆腐(あんにんどうふ)をつくり、販売を始めた。

スイーツの事業を拡大するため、果物との組み合わせを検討したが、素材の調達が難関となった。「酸味があるイチゴはスイーツに合う。本物を目指す上で冷凍品は扱いたくない。輸入品はカビなど品質面の管理がとても難しく、夏期を含め1年を通じて生のイチゴをどう調達するかが最大の課題だった」(デリカ事業部の関谷貴彦インストアベーカリー担当部長)という。
そんな時に、一般社団法人日本食農連携機構から「ヤオコーは加工場を持っているので、余っているイチゴを使えないか」という提案があり、苫東ファーム株式会社(北海道苫小牧市)を紹介された。同社は、情報通信技術(ICT)を活用して環境を制御する大規模な栽培施設を2014年から運営し、国産イチゴの流通量が減る夏にも安定した生産ができる。
「小粒で通常だと廃棄するかジャムに加工するイチゴなら、値頃感を維持したままたっぷりと使える。摘んでから3日以内で加工販売でき、鮮度や色合いを維持し、さらに食品ロスの削減に寄与できる」(同)と、苫東ファームからの夏イチゴ(写真)の調達を即決した。
こうして「ヤオコー ピノ いちご&ブルーベリー杏仁豆腐」(298円+税)が完成、ヤングファミリー層が多い地域や駅前など8店舗で販売を始めた。冬イチゴは九州・関東、春先は地元産と、通年で国産の調達にこだわり、ブルーベリーも千葉など首都圏で調達している。規格外品を活用して廃棄を減らす取り組みはイチゴだけではない。
昨年末のクリスマス用の西洋梨のタルトの素材は国産のラ・フランス(写真)を使った。「青果の担当者と共同し、不揃いや傷ものを加工に回すことで18センチのタルトを2380円で提供でき、冷凍洋梨を使うのと比べるとフルーツを倍以上使えた」(同)という。
ヤオコーは、1890年に埼玉県比企郡小川町で青果店「八百幸商店」として創業、ヤオコー183店舗、AVE13店舗、フーコット3店舗(23年3月末)を展開し、小売り激戦区の首都圏にあって、23年3月期決算は34期連続の増収増益を達成した。中でもデリカ部門は、売上高構成比率の14・9%(22年)に対して、純利益構成比は27.6%を占め、商品開発力の強さを示している。
同社が重視している内製化は、商品の企画から生産・販売までを垂直統合する一種のSPA(製造小売業)だ。アパレル分野で普及し、ナイキやファーストリテイリングが代表例だが、眼鏡や家具分野でも広がり、食農分野にも浸透してきた。背景には人工知能(AI)やロボットの普及もある。新商品の企画や開発など付加価値が高く、やり甲斐のある魅力的な職場を開拓しないと人材を確保できないからだ。
例えば、株式会社穴太ホールディングス(千葉県木更津市)の戸波亮代表取締役代表は、著書の「葬儀会社が農業を始めたら、サステナブルな新しいビジネスモデルができた」の中で、「自分でつくって自分で売る。だから面白い」と、内製化の徹底により、葬儀に使う花から稲作に参入し、卵や甘酒の製造まで統合した経緯を説明している。
また、コロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻を背景に、輸入に過度に依存するサプライチェーン(流通網)のリスクが強く認識され、安定的な調達先として国産が重要になっている。外国為替市場で円安が進み、価格の面でも輸入品が安いとは限らなくなった。
これまで農業分野では、生産者が加工・流通を取り込み付加価値を高める「6次産業化」が重視されてきたが、流通業など異業種が起点となって連携が進む可能性が強まっている。(石井勇人共同通信アグリラボ編集長)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)