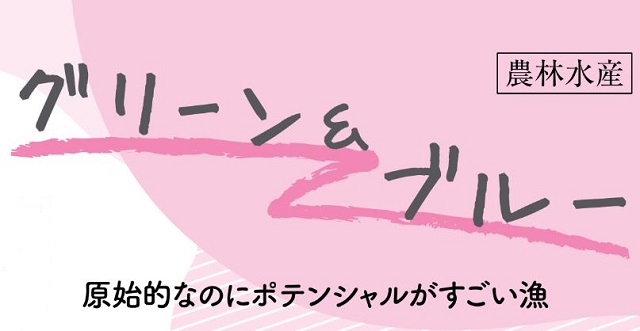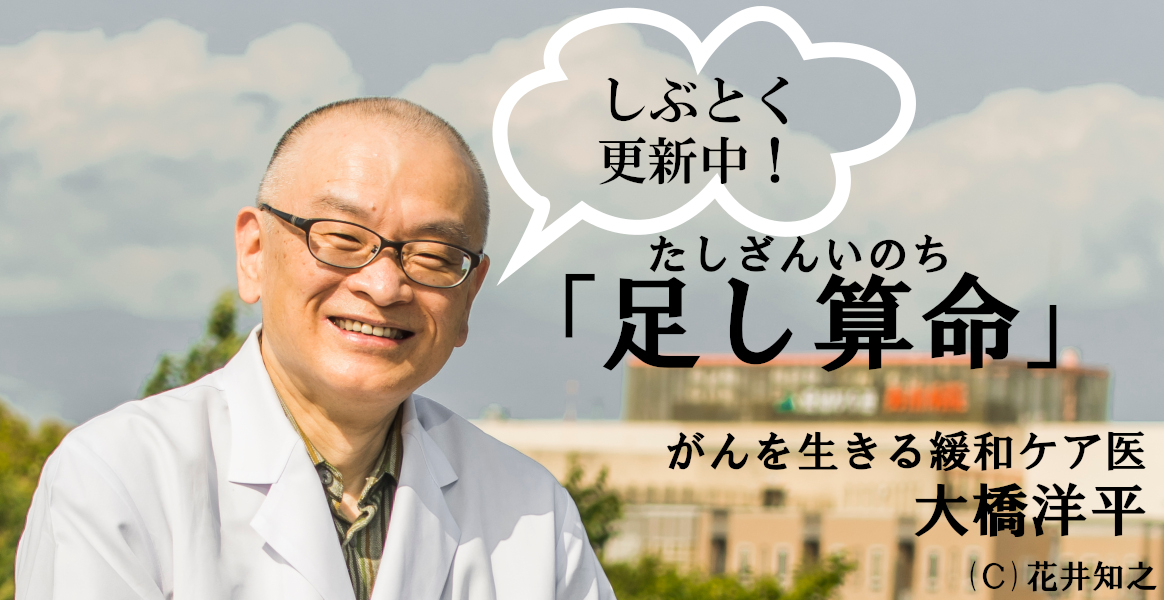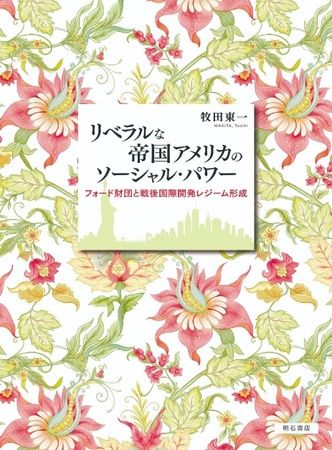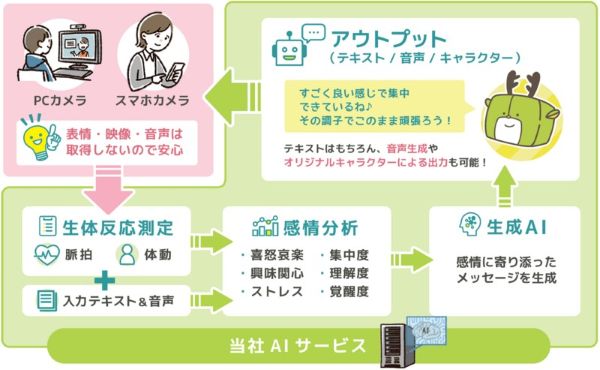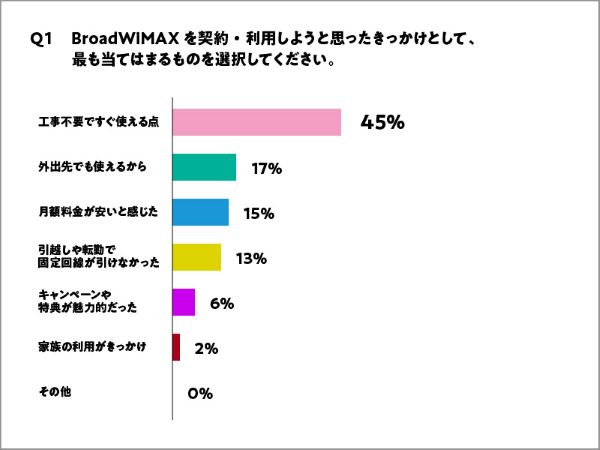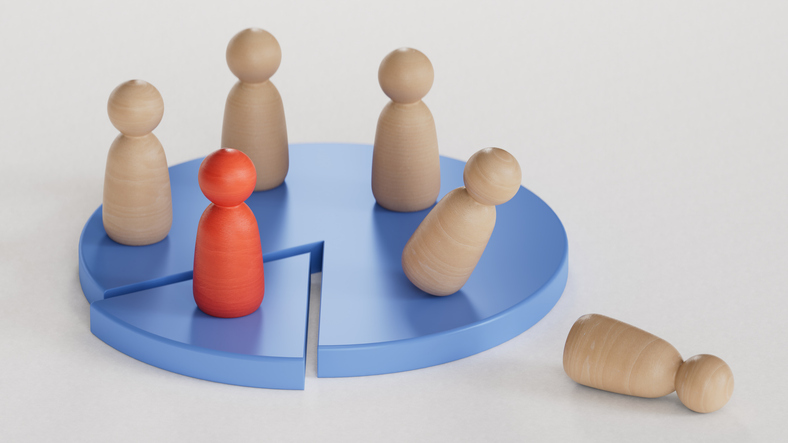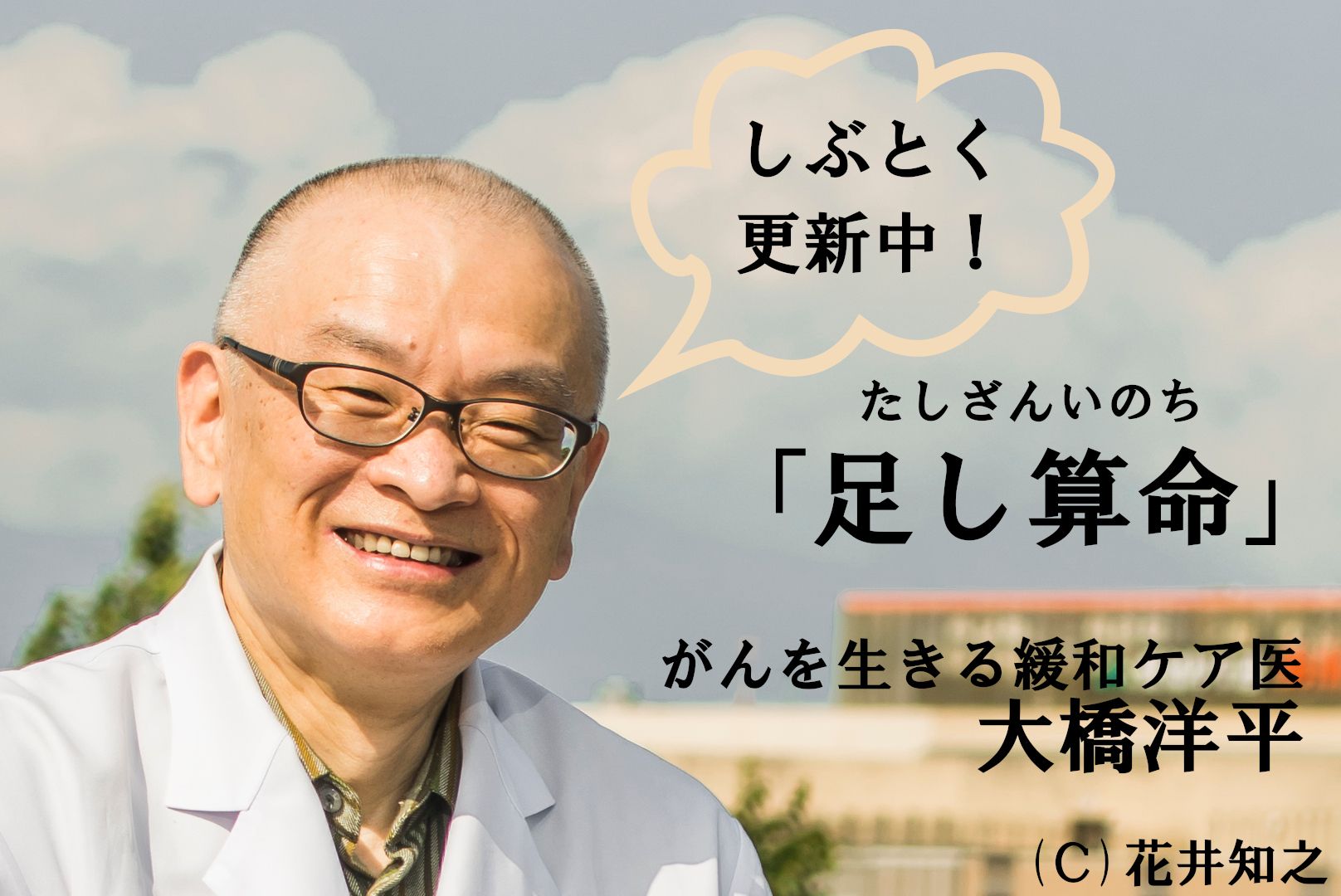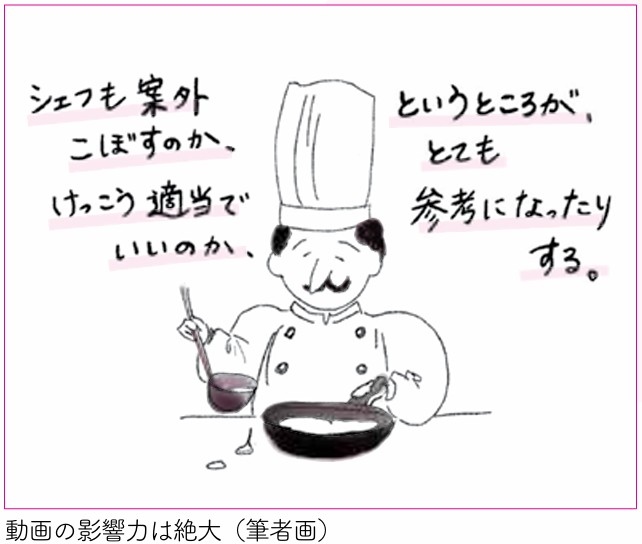「もんどり漁」という言葉を聞いたことがあるだろうか? これは円筒状や鳥かご状に編まれた網かごの中に餌を入れ、海や川に沈めて魚が入るのを待つ漁法のこと。京都の伊根町や滋賀の琵琶湖などで古くから用いられている。
筆者は伊根町で体験させていただいたのだが、何とも原始的なのに、これぞ現代人が求める“効率的・合理的・持続可能”な仕組みではないか…!と感動してしまった。
漁というと普通、一般的な生活者には縁遠いものだろう。しかし伊根のもんどり漁は、生活者の営みにも自然と入り込んでいる。驚くべきは、その物理的・精神的なハードルの低さだ。
まず網かごを仕掛ける場所が、自宅など敷地の脇や、もはや建物の中だったりする。
伊根町には「舟屋(ふなや)」という独特の建築物が200軒以上も残っているのだが、これは文字通り船を格納する場所として建てられた。海の上に足場を組んで2階建ての倉庫をつくり、1階は建物の中なのに半分ほどは床がなくて、海からそのまま船で入れる。1階の床がある部分と2階は作業場や物置として活用され、この建物に向かい合う形で自宅を建てるのが一昔前の伊根のスタンダードだった。
現在では舟屋をリノベーションして飲食店や宿、自宅として活用する方も増えているが、変わらず船置き場とする漁師さんもいらっしゃる。
この敷地の引っ掛けられる所にロープの片端を繋(つな)ぎ、もう一方に網かごをくくりつけ、中に夕飯の残飯などを入れる。あとは網かごを海中にドボンと落とせば、漁の準備は完了だ。
そのまま普通に自宅で眠り、朝起きたらロープを引いて網かごを挙げる。中に魚が入っていれば、漁は成功という流れだ(筆者が体験した時には高級魚であるキジハタとタコが入っていた)。
取れた魚は食卓に並び、あらなどの残りがエサとして網かごに入れられ、また翌日のもんどり漁に活かされる。
特別な準備も手間もいらない。日々の食事で出る、言ってしまえば本来は廃棄するのにエネルギーのかかるゴミを再活用して、新たな価値(魚)を生み出す正の循環。まさに“効率的・合理的・持続可能”のお手本ではないだろうか。
このもんどり漁、もちろん正式な「漁法」なので漁業権は必要だ。しかし仕組みはシンプルで、お子さんや女性も気軽に体験できるため、観光コンテンツとして整備する漁業者さんも増えている。
この連載でも何度か書いている通り、漁業界はさまざまな課題を抱えているが、その解決に向けては一般生活者たちの理解や協力が欠かせない。漁業界と生活者たちの接点が求められる中、気軽に楽しめて、大切な学びや気付きを与えてくれるもんどり漁は、すごいポテンシャルを秘めていると思う。日本各地のこうした漁法を見つけて体験し、多くの方に伝えていきたい。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.15からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)