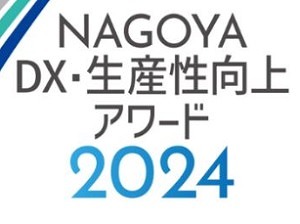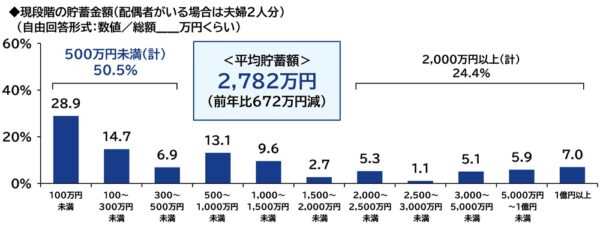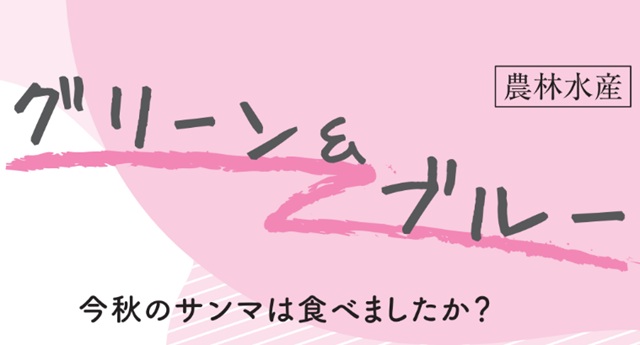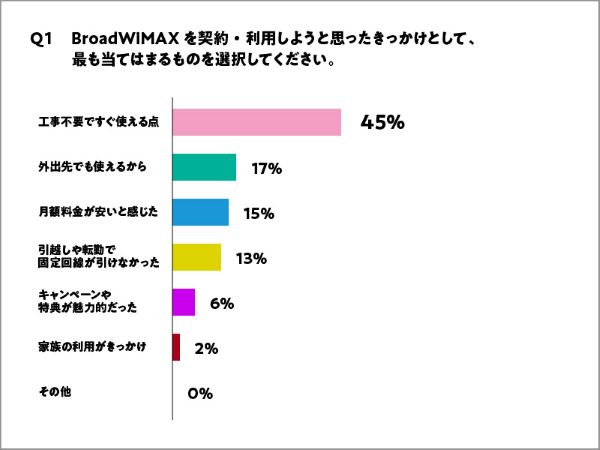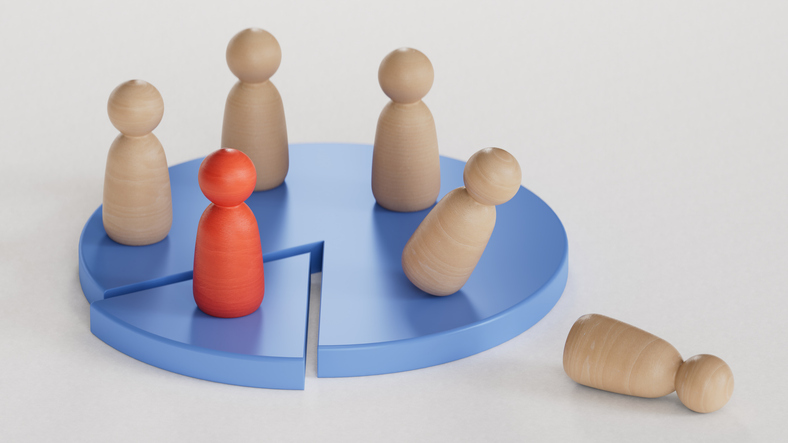10月13日に閉幕した大阪・関西万博のテーマの一つである持続可能な社会の実現について考えるパネルディスカッション「未来を変える選択を。今、私たちができること」(EY Japan主催)が10月3日、大阪市内で開かれた。オンライン視聴も含めおよそ170人が参加し、社会の持続可能性を巡るパネリスト4人の議論に耳を傾けた。
万博の関連イベント「テーマウィーク」の一つとして開催。パネルディスカッションの司会進行役を務めたEY新日本監査法人気候変動・サステナビリティ・サービス(CCaSS)事業部長の牛島慶一さんが冒頭あいさつし「世界は格差の拡大、世論の分断が顕在化している。サステナビリティの活動を急ぎすぎた結果とも考えられるが、気候変動問題などは待ってくれない。未来を変える選択は今の私たちにある」と述べ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを停滞させることなく着実に前に進める必要性を強調した。

4人のパネリストは、日本国際博覧会協会持続可能性局長の永見靖さん▽大和ハウス工業常務執行役員の能村盛隆さん▽パナソニックホールディングス(HD)執行役員の小川理子さん▽EY新日本監査法人CCaSS事業部シニアコンサルタントのテンチュリン・エルダーさん。それぞれ議論の前提となる発表も行い、万博での持続可能な社会の実現に向けた取り組みや、2030年までに達成を目指す国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成状況などを報告した。
■万博初の人権デュー・ディリジェンス

永見さんは「過去の万博などでは持続可能性というと環境が中心だったが、大阪・関西万博では人権の問題もしっかり取り組むと決め、持続可能な万博運営とともに、来場者やスタッフら多種多様な参加者が安心して万博に参加できる環境を整備する“インクルーシブ(包摂的)な万博運営”をあえて万博の基本計画で打ち出した」と述べ、人権侵害を防ぐ一連の仕組み「人権デュー・ディリジェンス」を万博として初めて導入したことを明らかにした。
その上で「協会は人権侵害に関する苦情を窓口で聞き取り改善につなげてきた。人権問題にはいろいろなものがあるが、万博で出てきた人権の問題は7月ぐらいまでに120件程度あり、改善する作業をしてきた」と話した。
■建設業界のメルカリ

万博のパビリオン「いのちの遊び場クラゲ館」の企画・管理を担った大和ハウス工業の能村さんは、廃棄物をできるだけなくし、資源を循環させながら活用していく経済システム「サーキューラーエコノミー」推進の取り組みを説明。その一つとしてパビリオンなど万博で使った建設資材・設備を再利用する仕組みとして立ち上げた、建設資材・設備の売り手である所有者と、買い手をつなげるリユースマッチングサイト「ミャク市!」の内容を紹介し、位置付けとしては「建設業界のメルカリ」を目指した、とした。
「いのちの遊び場クラゲ館」は広島県福山市が万博閉幕後の移築先として名乗りを上げており、能村さんは「(クラゲ館が)新しい場所で生き続けるとしたら、望外の喜び」と述べた。
■家電→パビリオン→家電

万博のパナソニックパビリオン「ノモの国」館長でもあるパナソニックHD執行役員の小川さんは、「ノモの国」での資源循環の取り組みを紹介。
「(ノモの国では)柱や梁(はり)の98%は家電のリサイクル鉄を使用している。幹線ケーブルには家電リサイクル銅を使っている。歩道の舗装ブロックには9200台分の洗濯機のリサイクルガラスを使った。そして万博閉幕後に解体されると、これらのリサイクル建材は、家電材料に戻っていく。家電から家電へのリサイクルはこれまでやっていたが、家電から建築資材になってまた家電に戻るこの取り組みは初めての試みだった」と語った。
■SDGs達成率はまだ35%

EY新日本シニアコンサルタントのエルダーさんは「世界で環境意識は高まり続け、SDGsは誰もが知る言葉になったが、今年7月時点で世界のSDGs達成率は35%にとどまっている。目指すべき姿と実際の行動の間にはギャップがある」と指摘した上で、政治や企業の行動を変えて「より持続可能な社会と経済」を創造するためには、生産力を重視するGDP(国内総生産)中心の考え方を脱却して「環境に悪影響を与える汚染活動や戦争などを生産量が増えるからといってプラスとしない新しい価値尺度が必要だ」と強調した。

同じ会場では10月1~3日、人類が気候変動対策に失敗した30年後の深刻な地球環境破壊に直面した人類の姿をはじめ4通りの未来を最新映像で体感する体験型イベント「FOUR FUTURES(フォーフューチャーズ)」(EY Japan主催)も開かれ、3日間で計130人が参加した。参加者は体験後、30年後の人類のために各自ができること、やるべきことをテーマに意見交換した。
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)