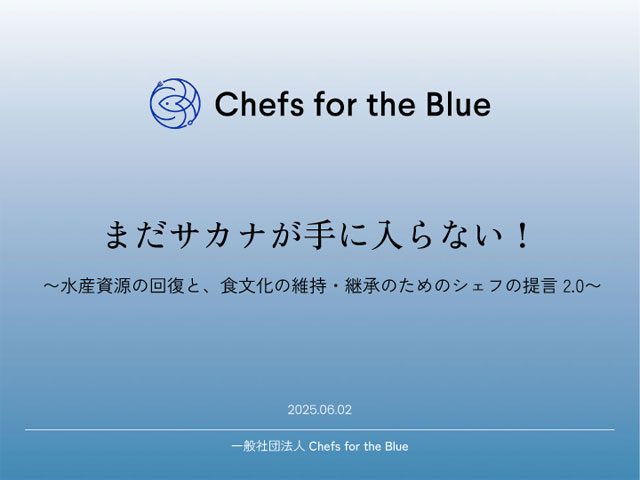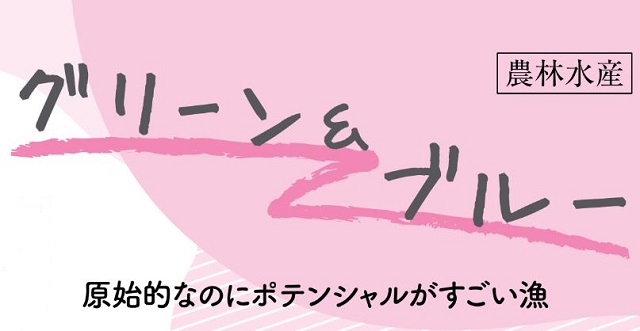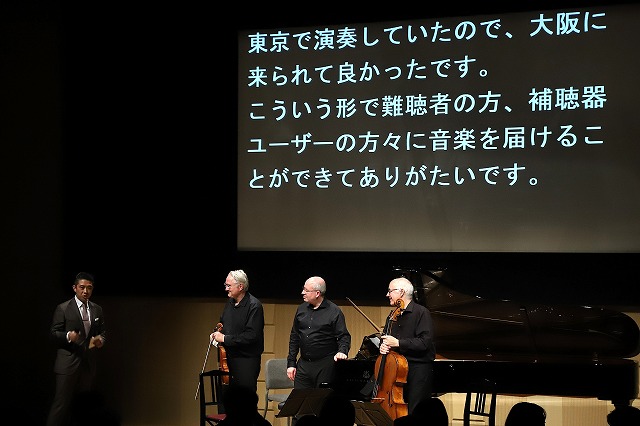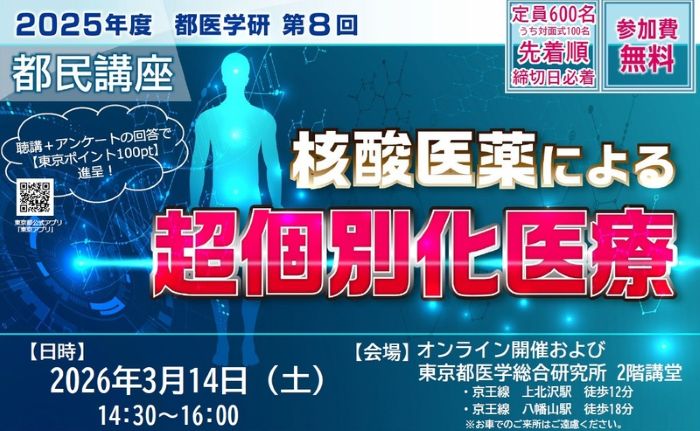「水産資源の枯渇は問題提起の段階はとっくに過ぎていて…(中略)癌(がん)宣告をされてどのステージかという問題です」(イタリア料理店オーナーシェフ)
「うちのような地魚を売りにしている店は、いつまでできるのかとても心配」(居酒屋店主)
「このままでは10年後、本物の鮨(すし)屋は本当に一握りになるでしょう」(鮨店主人)
シェフスフォーザブルーは今年5月、全国の飲食店オーナーと食材調達担当者を対象に、水産物調達の現状を知るためのアンケートを実施した。15日間という短期間にもかかわらず、集まった有効記名回答は1301人。冒頭のコメントは、そのアンケートの自由記述欄に記入してくださった数々のご意見からの抜粋だ。
10年前と比べ、市場などに流通する魚介類の物量変化を問う質問には、95.2%の方が「とても悪くなった」「悪くなった」と回答。同様に価格変化を問う質問には、99.5%の方が「とても高くなった」「高くなった」と答えた。魚介類の仕入れの今後について危機感はあるかという質問には、98.1%が「危機感がとても大きい」「少しある」と答えている。
さらに、肉や野菜などに比べて魚介類の仕入れがどうかを問う質問に、「問題はとても大きい」「大きい」と答えた人が73%と、全食材中で特に魚介類調達が難しい現状が浮かび上がった。
回答者が属する飲食店は、鮨屋や日本料理店、フランス料理店などの高価格店から、蕎麦(そば)屋や居酒屋、カフェなど中・低価格帯の店舗まで多様だったが、集計した1301人の声は一様に悲痛で、シェフスフォーザブルーの料理人たちが8年間訴え続けてきた危機感と一致した。
飲食業に従事する人口は、全国で400万人を超える。そして鮨屋をはじめ、日本の多くの飲食店にとって魚介類は最重要の食材だ。資源管理のルールが今のまま変わらなければ、魚はさらに減り続けることが予想され、今後多くの飲食店が立ち行かなくなるだろう。雇用やインバウンド(訪日客)消費への影響も必至だ。
この集計結果は今年6月2日、私たちが小泉農林水産大臣と森水産庁長官に提出した提言書にも組み込んだ。日本の国民が魚料理を食べられなくなる未来が来ないよう、私たちの魚食文化が消えないよう、魚料理の作り手、食べ手の声を水産行政に届け、適切な施策を求め続けたい。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.27からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)