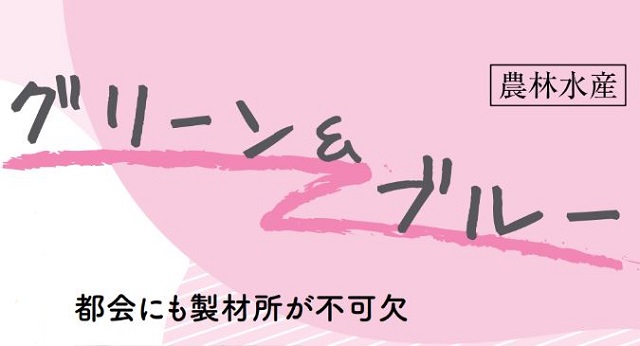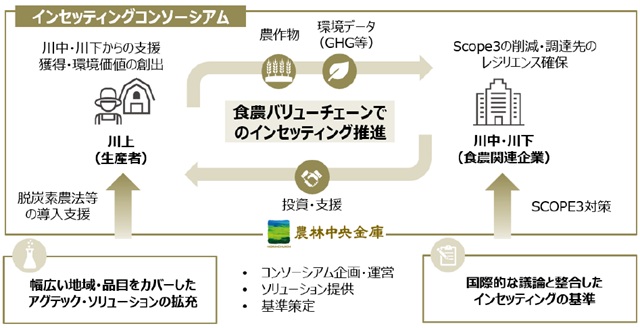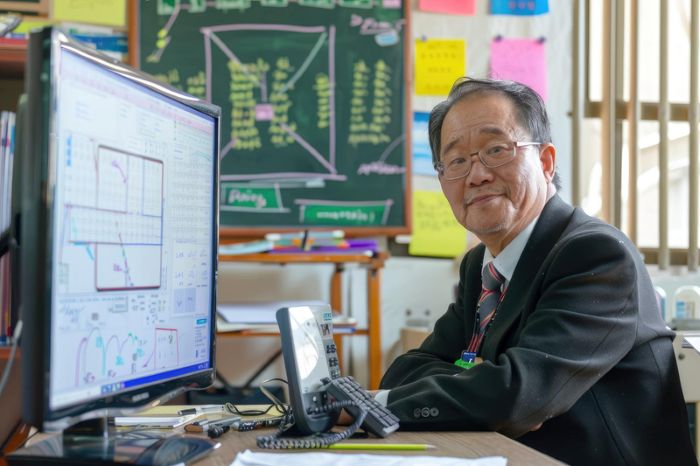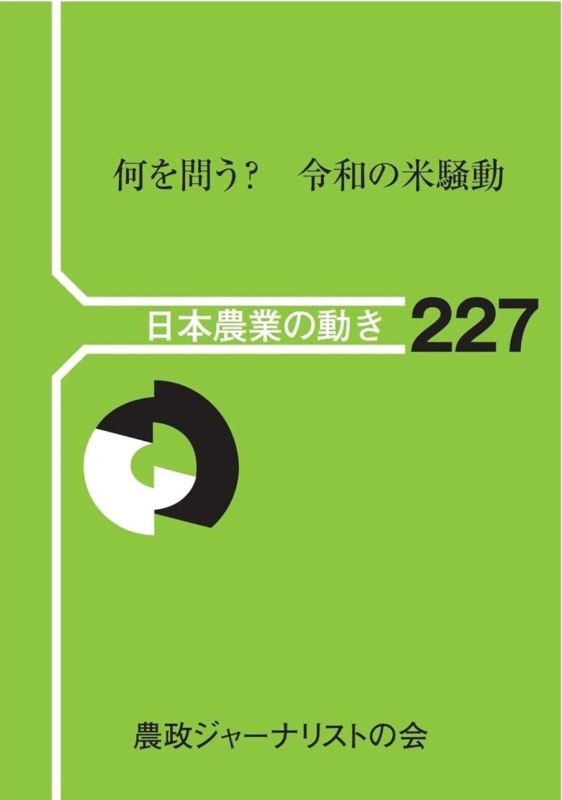製材所といえば林業産地に居を構え、山で伐採された丸太を挽(ひ)いて角材や板材をつくる工場だとイメージする人が多いだろう。
だが、木が使われるところには必ず製材のニーズがあり、それは山間地に限らない。都会でも木が使われる場面は多く、人がたくさん住んでいて経済活動が盛んなだけに使われ方も多彩だ。東京・新木場の(有)小一屋は、そうした都会の木材利用を支える、23区内では珍しくなった賃挽き専門の製材所である。
小一屋の経営スタイルは、客が持ち込む材料を指定された寸法に製材するというものだ。丸太を仕入れて製材したものを販売するのではなく、製材という労務を提供し、その対価(「挽き賃」と呼ぶ)を売り上げとする。これが「賃挽き」である。
東京には国内はおろか世界中から多種多様な木材が集まってくる。中には最終的に使われるサイズにあらかじめ仕立てられた製品もあるが、丸太のままだったり大きめの角材に挽いただけであったりと、製品になる前の段階のものも多い。
それらの材料をサイズやデザインを決めて製品に仕立てるには製材というプロセスが欠かせず、小一屋には日々、さまざまな注文が舞い込んでくる。意外なところでは、公園や学校などで伐採された樹木をベンチや家具などに利用するために製材してほしいといった依頼もある。
仕事の多様さは都会ならではだが、実はほかに頼めるところがないという事情もある。社長の羽手原勲(はでわら・いさお)さん(54)は「何しろ23区内で賃挽き製材は壊滅状態ですから。賃挽き専門はウチ以外にほとんどないんじゃないかな」と苦笑いする。
23区内で製材所が減ったのは、オーダーメードの無垢(むく)材が使われる場面が少なくなったからだ。窓や建具の枠材、天井と壁あるいは床と壁が接する部分に張る見切り材などは、もともと木材の重要な用途だった。しかし、最近は表面に木柄をプリントしたり木目模様のシートを貼ったりした建材が安価で扱いやすいからと多用されるようになった。こうなると製材の出番はない。
だが、貼り物でも練り物(木粉を接着剤で固めた建材など)でもない無垢の木の魅力は一味違う。建材類は施工したてはきれいでも時間の経過とともに色褪(あ)せていく。一方、無垢材は年月を経るほどに表情が深まり、風合いが増す。
製材所があるから無垢材を利用できる。その意味をかみしめたい。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.18らの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)