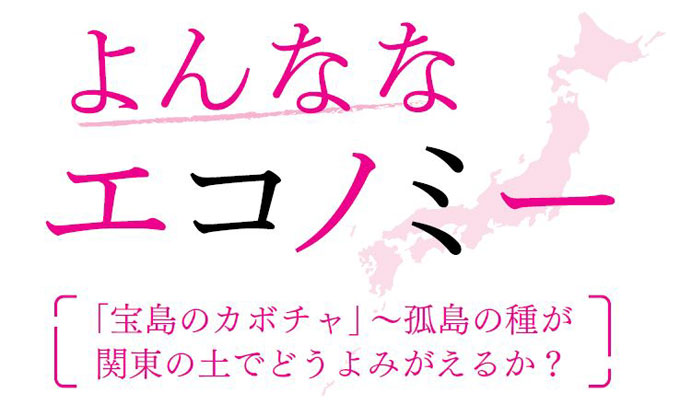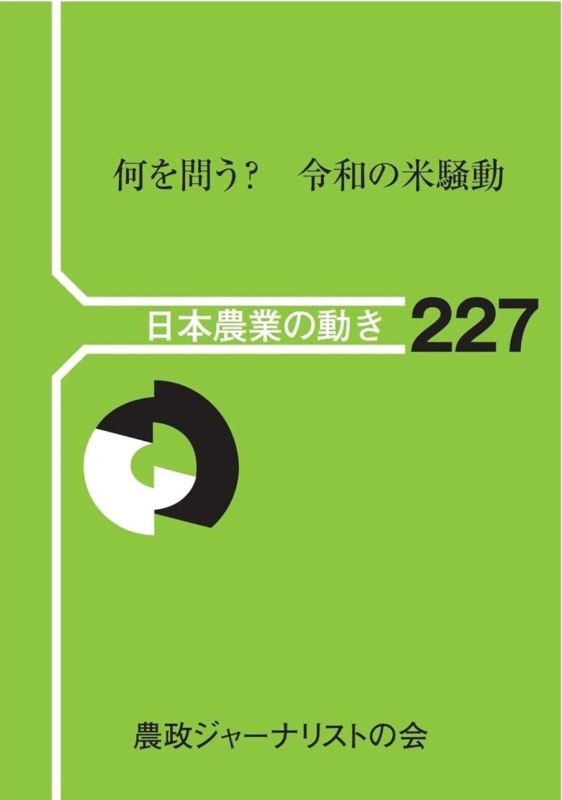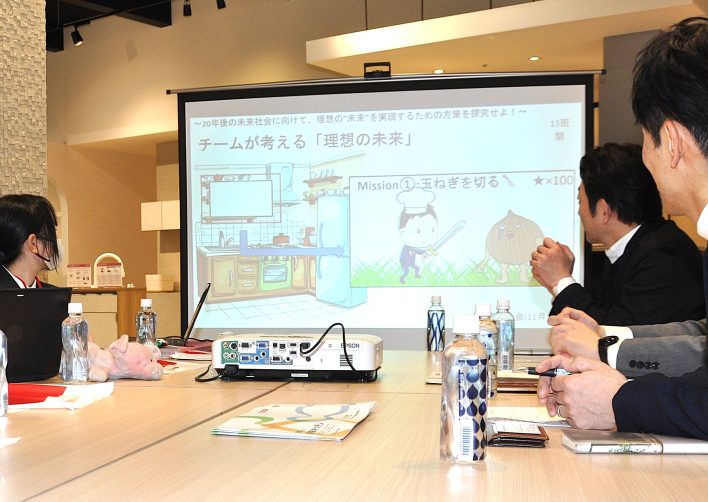群馬県太田市の亀井秀夫さん(72)は年が明けた6日、カボチャの種を、関東地方の約20軒に郵送した。鹿児島県の南に連なるトカラ列島の宝島の知人から11年前に引き継いだものだ。
「いただいた3粒の種は、いきなり300個余りのカボチャに育ちました。生命の勢いをいただきましたが、そろそろ畑仕事がきつくなった」ため、今年を最後にカボチャ栽培は終わりにすることにした。
これを聞いた地元新聞の友人が、「宝島カボチャの種を提供します」と記事にしたところ、地元の群馬県をはじめ、栃木県や埼玉県、福島県などから問い合わせが相次いだ。ほとんどが「縁起が良い名のカボチャを、家庭菜園で育ててみたい」との申し出だったが、本格農家からの要請もあった。
宮下利雄さん(73)は、太田市尾島の利根川河川敷の農地で、名産のヤマトイモなどを生産してきた。江戸時代からの13代目。「宝島は絶海の孤島。サンゴ礁が隆起した火山灰で、生き抜いてきた種に興味があります。亀井さんの畑に転がっていたカボチャに、菊のご紋のような模様を見つけました」
4日に、20粒の種を持参した亀井さんを、春から育てる予定の畑に案内した。利根川沿いの肥沃(ひよく)で水はけのよい土地で育てたヤマトイモは、トロロにすり下ろすと、お箸でつまめるくらいの強い粘り気がある。全国にファンがいる。「宝島の種が関東ローム層の土で育つと、どんな味になるのかな」。
4月中旬から5月のGWのころにかけて種をまき、5月中に「本葉4〜5枚」を定植する。収穫は9月中旬から11月の霜が降りる前までだ。
「宝島カボチャ」をまずは関東に定着させようと、2人は栽培方法を練り始めた。
亀井さんと宝島の出会いは、姉に呼ばれて東京へ移り住んだ妻のヨシノさん(74)だった。
1965年当時、東京・文京区の小石川の製本会社を中心に「宝島村」が形成されつつあった。敗戦直後に北緯30度線で分断されて米軍の占領下になったトカラ列島は、6年後の52年に本土復帰。その後、宝島の有志が上京して製本会社を設立。同郷の人たちを採用して、50年代には小石川周辺の同島出身者は300人余りに拡大した。
同社の経理担当をしていた杉田ハルコさん(86)は、「戦時中は肥料で大きなカボチャにして食料代わりにしたと聞いたけど、もともと痩せた土地だったから。島で栽培してるとの話は聞かなくなったわね」。
今は「関東トカラ会」として、トカラ列島出身の仲間数百人が交流しているが、「故郷のカボチャを関東の土でよみがえらせよう」と検討が進んでいる。「せっかくの伝統あるカボチャだから、宝島の小学校に種を戻してみてもいいかな」。そんな提案も亀井さんの耳に届き始めた。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.3からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)