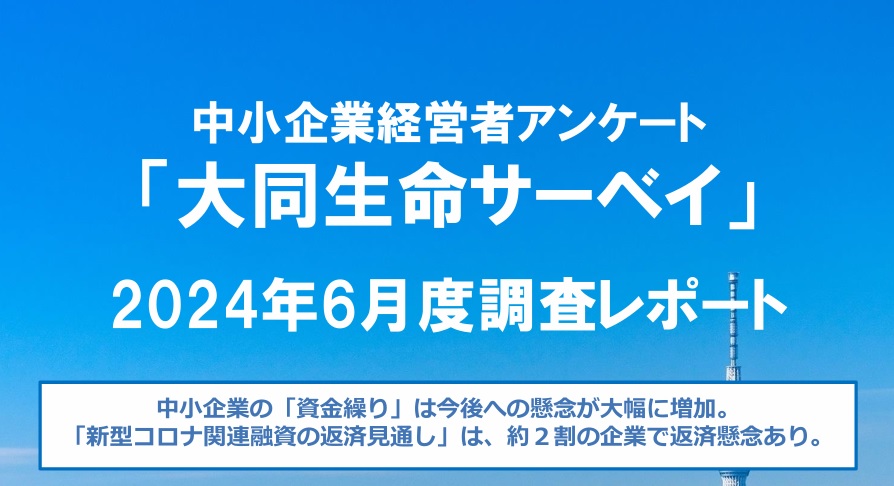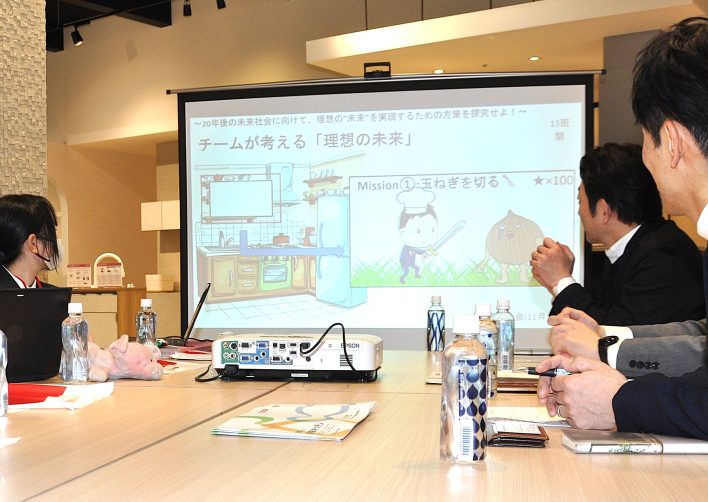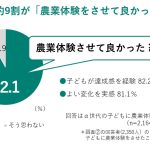もうとっくに“限界点”を超えているウクライナ戦争やパレスチナ自治区ガザでの深刻な人道危機。停戦や紛争終結に向けた道筋を示せない各国首脳や国連に対する国際世論の批判は強まっている。個人一人一人にとっても、紛争を止めるために「自分に何ができるか」を問われているような状況だ。この状況から目を背けず、自分なりの答えを作品に込めた水墨画家がいる。
1921年の創立から水墨画振興に取り組む日本南画院(京都市)の堀江春美理事長だ。東京都港区の国立新美術館を皮切りに3月20日から始まった「第64回日本南画院展」に“祈り”と題する水墨画を出展した。「私にできるのは祈ること。描くことが私の祈り」と静かに語る。
“祈り”は、円屋根の尖塔(せんとう)に十字架が立つ高い聖堂が、別の建物のU字型の開口部越しに見える、奥行きのある構図。聖堂の下は“煙のようなもの”に覆われて見えない。それは見慣れた光景になってしまった空爆直後に立ち上る噴煙のようにも見えるし、夜を払う太陽が昇り消えていく朝もやのようにも思える。
開口部の内側は暗く、水墨画特有の深い黒が開口部を縁取る。その黒さは狙撃手が潜む闇を想起させ、その深さは戦禍で家族ら大切な人を失った遺族の悲しみの大きさに比例するかのようだ。
この深く黒い縁取りを突き破るような白は、聖堂頂点の十字架に近づけば近づくほどその明るさを増す。紛争終結に向けた希望の輝きのような明るさが印象的だ。この白と黒の対比は、「墨と水のグラデーション(濃淡度合い)で描く水墨画」(堀江理事長)の真骨頂であり、ウクライナとガザの現状に対する堀江理事長の悲しみの深さと平和を求める祈りの強さが感じとれる。
このように“祈り”は、昼と夜を共に想起させるルネ・マグリット「光の帝国」のような陰影に富んだ両義性にあふれており、鑑賞する人の想像力を強く刺激する。白黒の世界である水墨画に豊かな色彩を感じる鑑賞者は少なくない。水墨画には白い花を赤い花と想像させるような色の余白がある。“祈り”からは、開口部の先に広がる日の光の暖色とともに、紛争終結を真摯(しんし)に念じる人々の静かだか力強い祈りの声も感じとれる。
40代の時、最愛の夫を亡くした堀江理事長は、大切の人を失う心の痛みを知っている。堀江理事長は「筆を手に取らず一日中、墨をすって終わる日もある。墨をすりながら自分の内面を見つめる。ウクライナ戦争が始まり、ガザの深刻な状況を知って以降、“祈り”を描くと決めた。私の内面から突き上がってくるもの、心の目で見えてきたものを描いた」と語る。
水墨画は、中国の山水画が禅宗と共に鎌倉時代の日本に伝わり、画僧の雪舟などの活躍で室町時代に山水以外にも自由な対象を描くようになった。水墨画の一源流である南画(南宗画)は唐(中国)の詩人・画家の王維に始まり、日本には江戸時代にもたらされたという。日本では精神性を重んじ、池大雅や与謝蕪村、渡辺崋山、谷文晁などにより日本独自の南画の基礎が築かれた。

日本南画院は全国で水墨画教室も開き、水墨画、南画の普及に努めている。堀江理事長は「若い人にも水墨画に触れてほしい。興味を持ってもらえるよう、日本南画院のホームページも作った。興味のある人は全国にある水墨画教室に問い合わせてほしい」と呼びかけている。
国立新美術館での「第64回日本南画院展」は水墨画の力作183点を展示。大勢の人が訪れ、墨の濃淡の巧さで多様な世界を表現する水墨画を楽しんだ。国立新美術館では4月1日まで開催。同展は、国内を巡回し、6月20~25日に兵庫県宝塚市の宝塚市立文化芸術センターで、7月16~21日に京都市の京都市美術館(京都市京セラ美術館)でそれぞれ開かれる。
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)