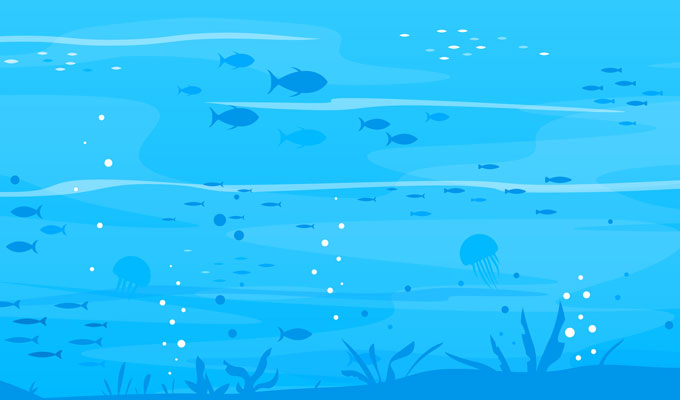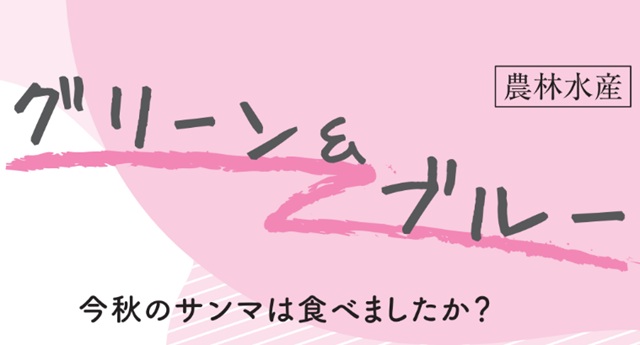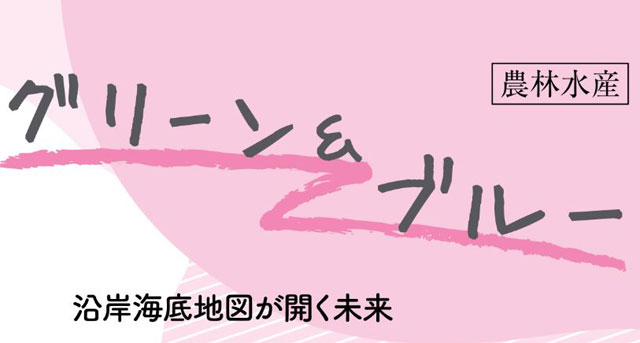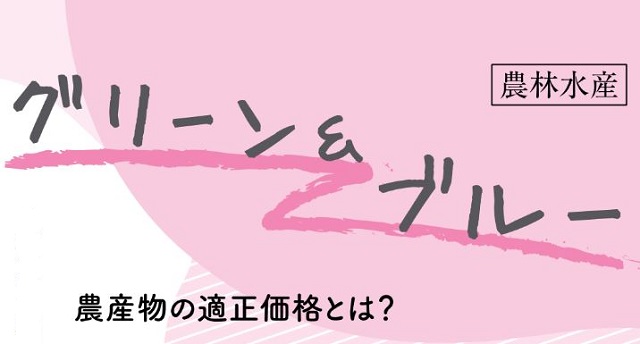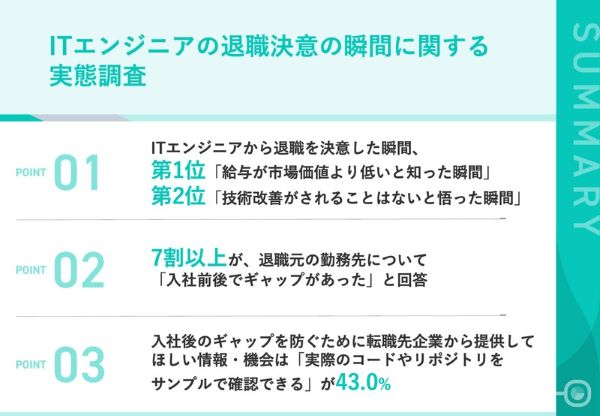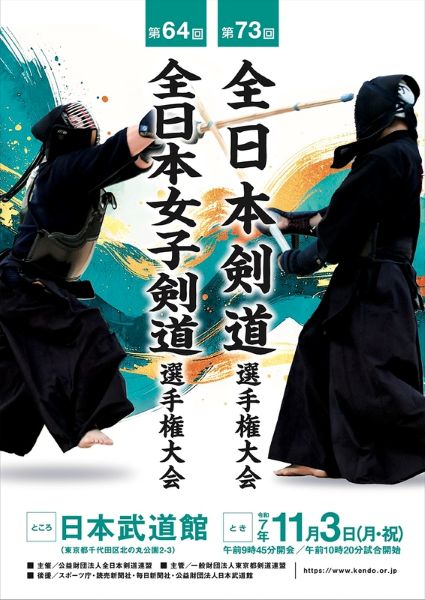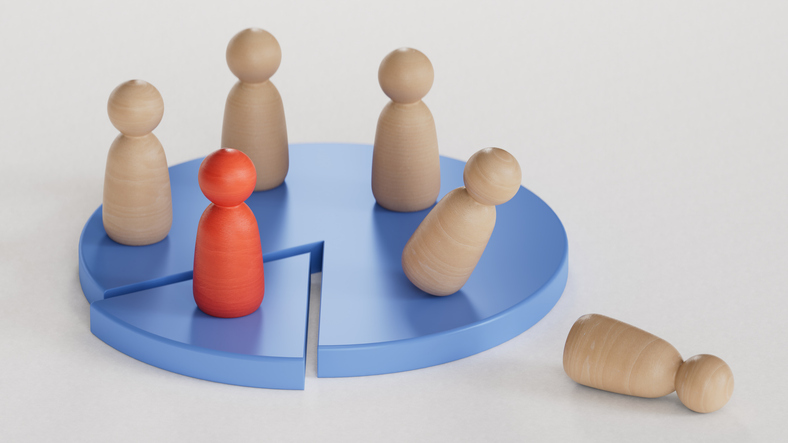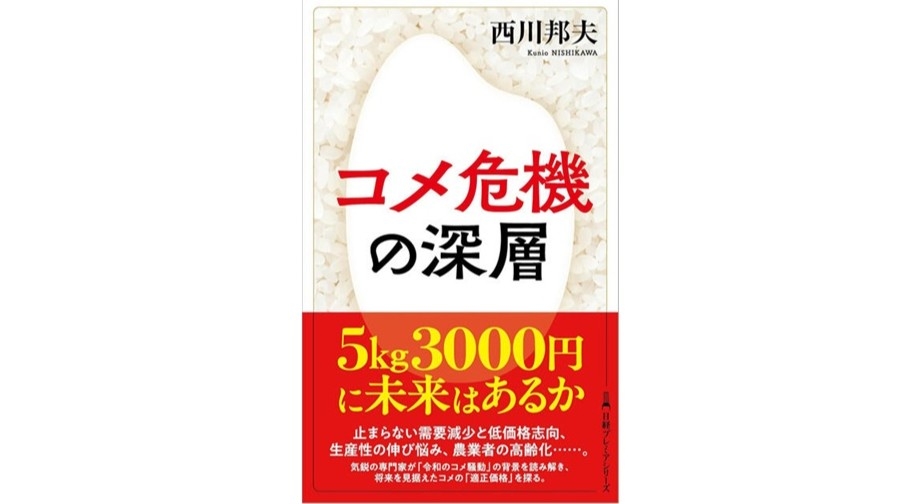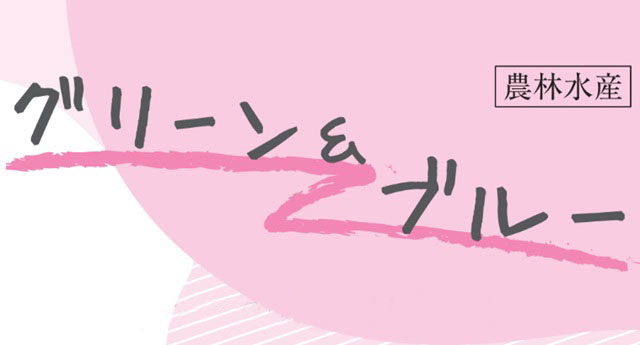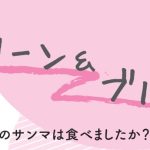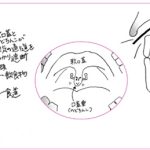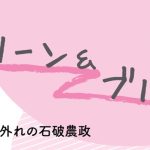「水産女子」という取り組みをご存じですか?(写真はイメージ)
これは水産庁が”水産業界を女性が活躍しやすい環境に整え、多様な人材の力を生かせる状態にすることで、業界全体の魅力向上へつなげよう”と2018年11月にスタートしたプロジェクト。正式名称を「海の宝! 水産女子の元気プロジェクト」といいます。
実は、筆者は本プロジェクトの初期メンバー。16人から始まり、今年10月には105人にまで拡大。メンバーの職種も、漁師さん、魚屋さん、水産加工業者さんをはじめ、料理家さんや水産テック企業の社員さんなど多岐にわたります。活動する場所も全国約30の都道府県に広がり、全員で集まることは難しくなった一方で多様性が増しています。
水産女子の活動は主に三つ。①つながる ②伝える ③創るー があります。
「つながる」では、年に1回程度のリアルな総会をはじめ、オンラインやSNSを使って勉強会や情報交換が行われています。
「伝える」では、おのおのがSNSで仕事や海辺の暮らしなどを発信するほか、水産女子としてメディアに出演したり、各種イベントでブースを借りてそれぞれの商品をPRしたりしています。今年8月には有志メンバーによる公式インスタグラムもはじまりました。
「創る」では、メーカーと共同して水産現場で女性が使いたくなるウエアや用具の開発に取り組んだり、料理レシピのコミュニティーサイトと「水産女子のおすすめレシピ」特設ページをつくったりと、企業を巻き込んだコラボレーションを目指しています。
いずれの活動も重要ですが、このコラムを書くにあたって話を伺った水産庁の担当者さんは、「特にコラボレーションに力を入れていきたい」と語ってくれました。水産業は女性活躍の推進に限らず、多くの深刻な課題を抱えています。その打開策は水産業界の中だけで生み出すことは難しく、多様な業界の方々に知恵や技術をお借りすることが必須。これは「創る」だけでなく、「つながる」「伝える」など、すべてにいえると思います。
そうした際に、重要になってくるのが女性の力。「女性がいるグループは、そうでないグループよりも多様性を受け入れやすく、”持続可能性”への意識が高い」といった研究結果が出ているように、未来に向けた共創には女性の力が欠かせません。
水産業をこの先の未来へつなげるため、そしておいしくて安全な食卓を守り続けるため、このコラムを読んでくださる皆さまの力を貸してください。「こんなコラボレーションができるかも」と少しでもわくわくした方は、ぜひ水産庁の「海の宝! 水産女子の元気プロジェクト」事務局までご連絡を。私たち水産女子と楽しく、おいしい未来をつくっていきましょう!
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.46からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)