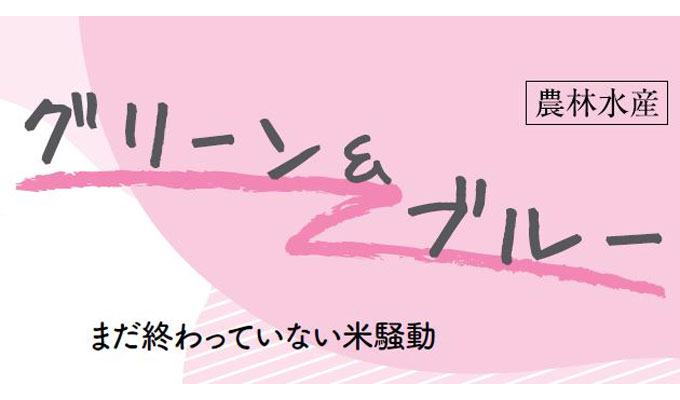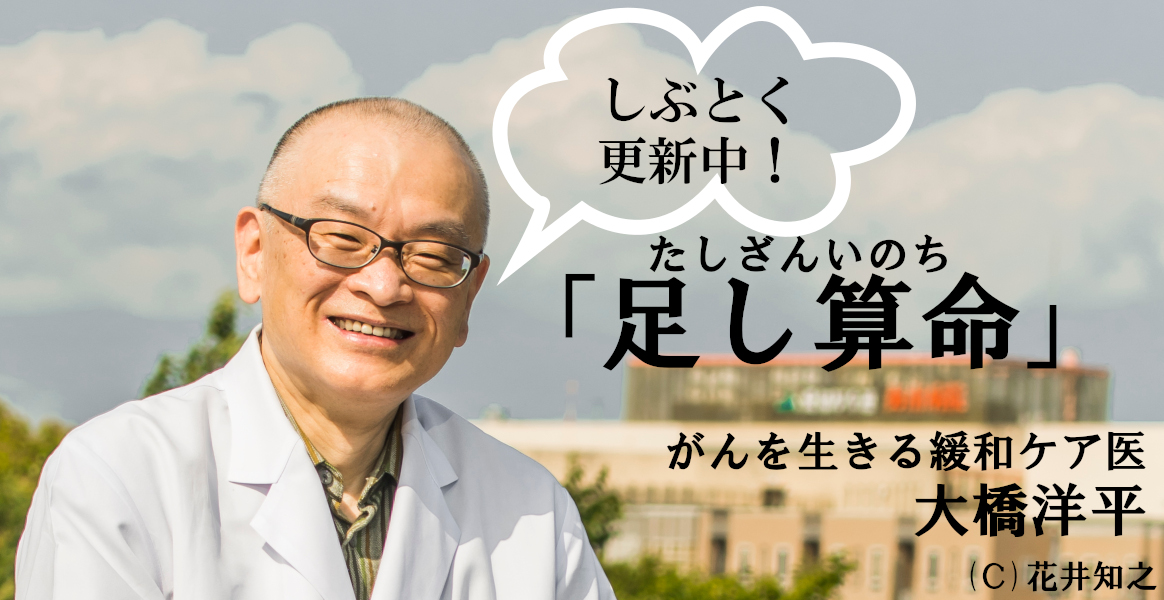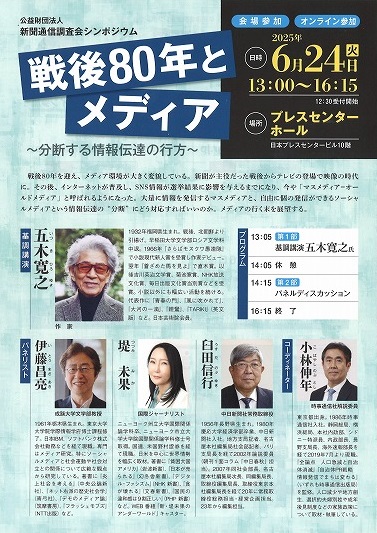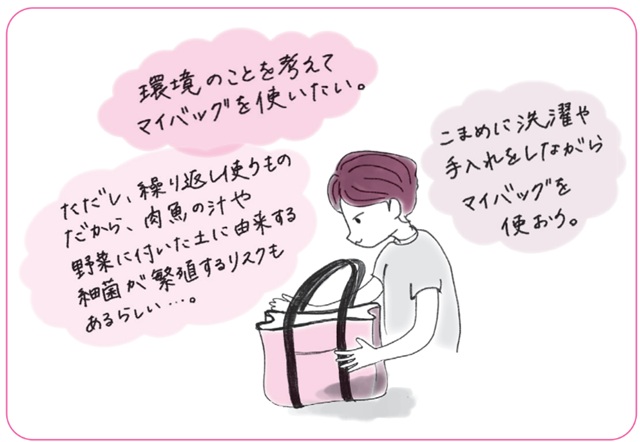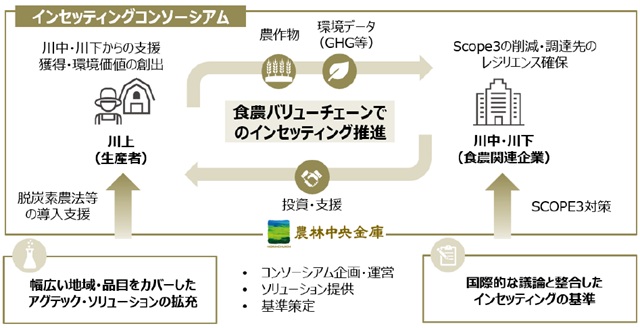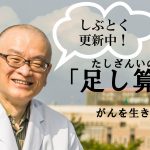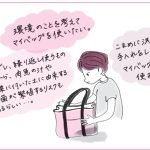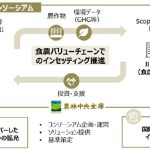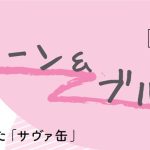林業と言えば、かつては「3K」(きつい・汚い・危険)業種の代表格として扱われ、中山間地の過疎高齢化も影響して慢性的な人材不足にあえいでいた。新卒や中途採用で林業に就く人もいるにはいたが、他の仕事がなく仕方がないからという消極的な理由での参入が多くを占めていた。
ところが、1990年代半ば以降、都会からのいわゆるIターン者を含め、やりがいを求めて林業に就業する人たちが増えてきた。これにはバブル経済が崩壊して経済至上の価値観が疑問視されるようになったことや、環境保全への意識が高まったことなどが背景にある。
国も2003年度からは「緑の雇用」事業を開始し、各種研修を実施するなど林業従事者の育成に本腰を入れるようになった。同事業を利用して新規に就業した人は22年度までの20年間で約2万2千人に達している。国勢調査によると、20年時点の林業従事者数は6万1千人とされているので、同事業のインパクトがいかに大きかったかが分かる。
もちろん、就業した人のすべてが定着したわけではない。だが、最初の就職先を辞めても別の職場に移ったり、自ら起業したりして林業に従事し続ける人も少なからずいる。男の職場というイメージが強い中、男性に交じって現場の作業に従事する女性も増えた。
20年ほど前、経営難に陥ったある林業の組織で、内勤者は待遇が維持されているのに、経費節減のために常勤を解かれ、臨時雇用に格下げされた現場作業員たちが反発の声を上げたのを取材したことがある。
結果を言えば、彼らの声は無視され、中心になって動いていた人はその組織を辞めてしまった。その後ずっと音信が途絶えていたのだが、最近ある林業関係の会合でその人と偶然再会した。聞けば、退職後に自分で林業会社を立ち上げ、今は10人以上の作業員を雇っているという。経営は楽ではないが、やりがいのある職場だと思ってもらえるように頑張っているのだと話してくれた。
労災の多発や低賃金など、依然として林業を巡る課題は多いが、こうした人たちが最前線にいることはとても心強い。より良い仕事をしようと思う人が増えることこそが産業を底上げするのだと確信している。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.39からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)