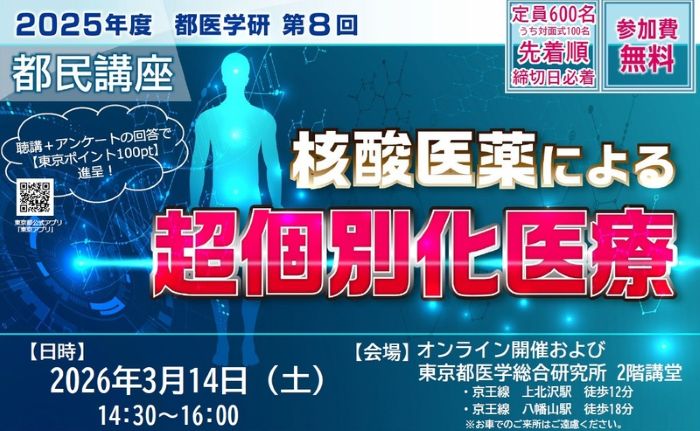石破茂首相は訪米し2月7日(現地時間)にトランプ大統領と初の会談に臨んだ。驚いたのは、会談の中身ではなく、帰国後に開口一番「(首脳会談は)1回で終わりじゃない、この後何度も何度もやるでしょう」(9日のNHK日曜討論)と言い切ったことだ。少数与党の石破内閣は苦しい国会運営を迫られており、まさしく「一寸先は闇」の綱渡り状況が続いている。首脳会談を無難に乗り切ったことで政権運営に自信を深めたのだろう。
石破内閣は、政権を延命するためには国会での「熟議」しかないことを十分に理解している。議事の運営は様変わりだ。たとえば自民党の小野寺五典政務調査会長は、1月31日の衆院予算委員会で米価の高騰や水田政策について質問し、野党席を何度も振り返りながら「直接農家を支援する仕組み、私だけでなく野党の皆さんからも指摘があった」と述べ、野党と協調する姿勢を示した。
これに応じて、江藤拓農相は「これまでの殻を破った水田政策の見直しが必要だ」と水田の水張り要件の撤廃を公表し、議場からは拍手がわいた。小野寺政調会長は「野党の皆様の様々な声の力もいただきまして、水張りについては要件としないという答弁をいただきました」と述べ、野党に花を持たせて質疑を終えた。これまで、予算委はもちろん農林水産委員会でも野党に対する配慮はまったくなかった。
本来、民主主義は少数の意見を傾聴して議論を尽くすことが前提だ。ろくに議論もしないで多数で押し切っていたのが異常だった。少数与党の下でようやく、まともな国会運営を期待できる変化が生まれた。
特に、農業政策は右も左もなく、与野党が協調しやすい分野だ。政治状況に振り回されない息の長い政策が重要だ。中期指針である基本計画の策定が大詰めを迎えており、挙国一致、超党派の農業政策を示してほしい。
ただ、安易な「与野党の協調」は、場当たり的なポピュリズム(大衆迎合)に陥る危険と隣り合わせだ。政策の整合性や持続性を失う恐れがある。水張り要件を撤廃して水田を畑地化する政策は、米の増産を前提にした輸出促進と矛盾しないのか。
江藤農相は、飼料用米の増産支援から事実上撤退する方針も示した。これまで政府・与党は、集落の維持、畜産業との連携、食料安全保障の確保、水田が持つ多面的機能を高く評価して、飼料米専用品種の育種や農機の開発に膨大な財政を投入してきた。飼料米の増産や耕畜連携に励んできた農家ははしごを外される
高騰する米価対策として、政府備蓄米の放出も政治主導で決まったが、政策転換の説明は不十分だ。「新米が出回れば価格は落ち着く」「米の価格は基本的に市場原理で決めるべき」という政府の説明は何だったのか。政策を転換するならば、検証と反省、場合によっては責任の追及が伴わなくてはならない。そうでなければ、「熟議」を装う政治家のパフォーマンスに陥り、政策は方向性を失ってしまう。(共同通信アグリラボ編集長 石井勇人)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)