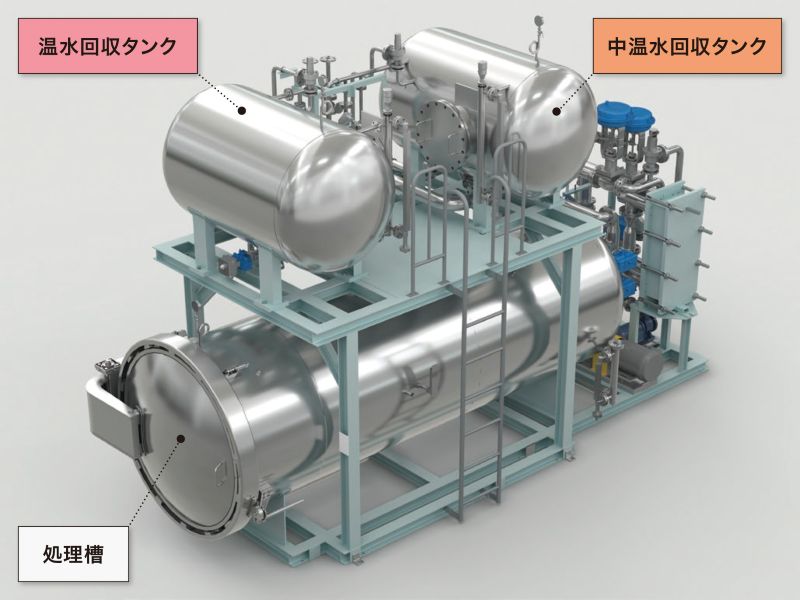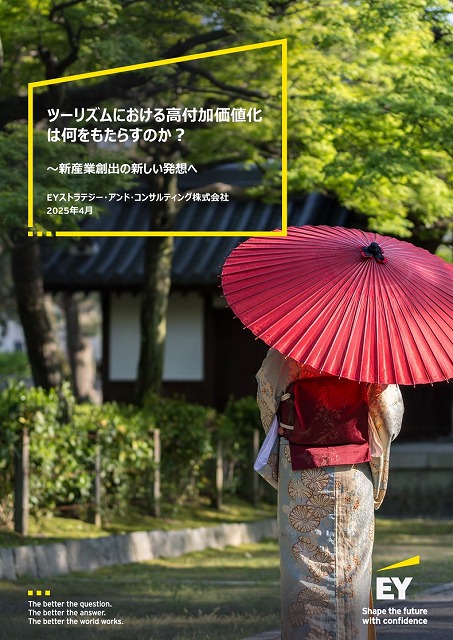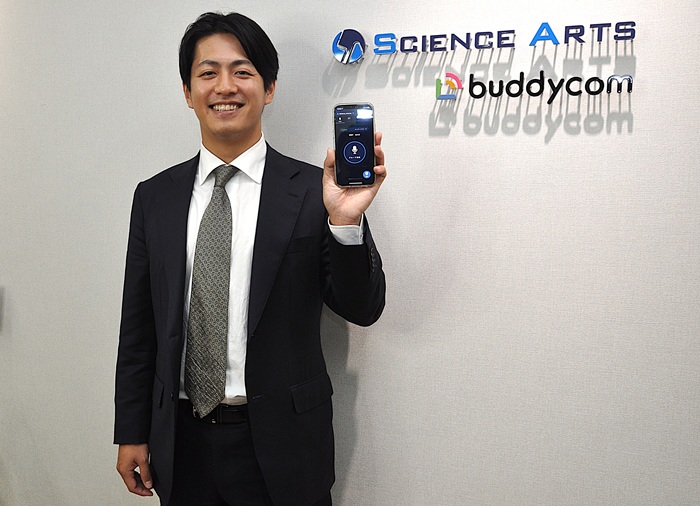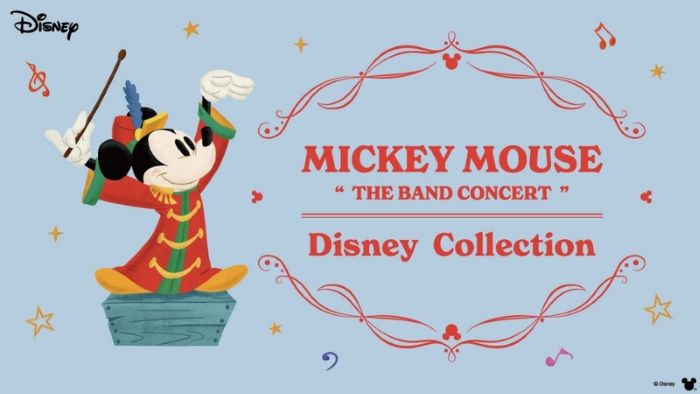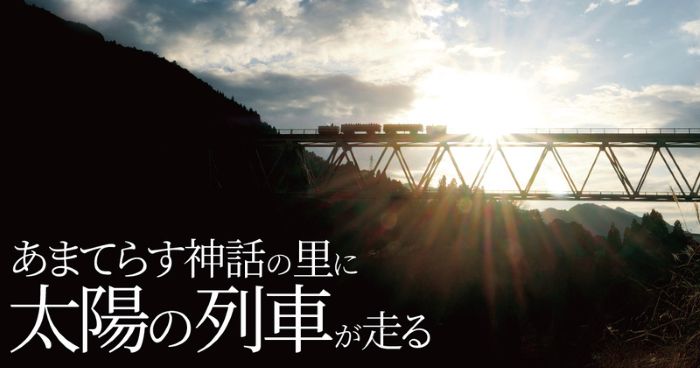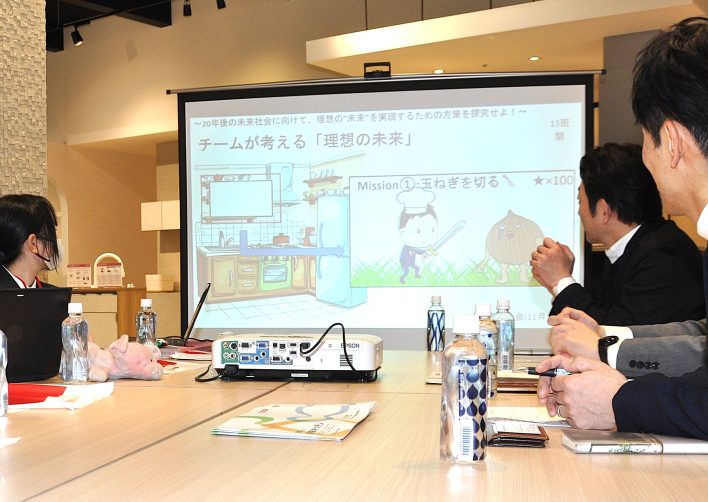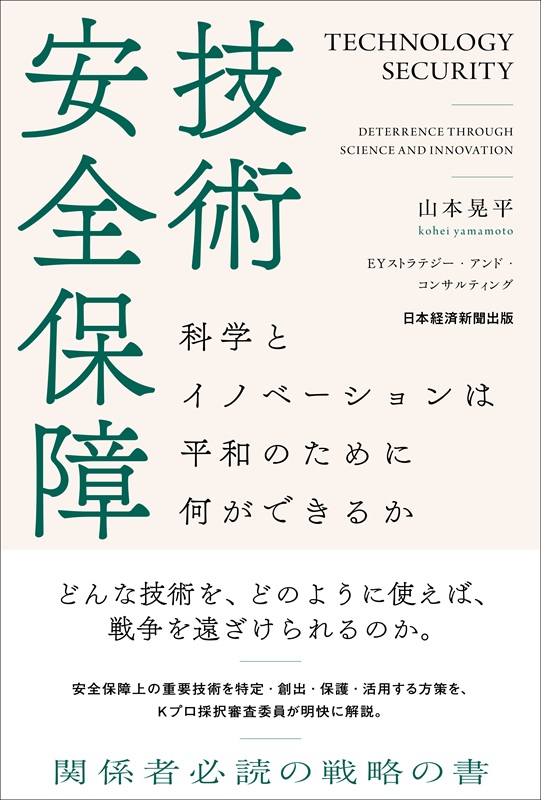
数年前に内閣府に担当大臣ポストも設けられた、いわゆる「経済安全保障」における“技術”の役割を正面に据えて「技術で戦争を遠ざける方策」を探った書籍『技術安全保障』(日経BP)が、このほど刊行された。
先端半導体などの輸出規制を巡る米中対立など、近年の技術をめぐる大国間の駆け引きの背景にある“技術安全保障”の考え方を論理と実践の側面から一般向けに解説。「技術によって戦争を遠ざける方法を議論するための出発点を提供すること」を目的に、関係者が最低限知っておくべき“技術と安全保障の関係性”を1冊にまとめたという。
「経済安全保障」に、学術的、国際的に完全に合意された画一的な定義はないが、この経済安全保障が以前より注目されている理由として本書は、過去の米ソ冷戦と異なり、現在対立する国々は互いに「経済的に密接に結び付いている」点を挙げる。このような経済的依存関係にある国同士の対立を戦争に至らせないためには「経済安全保障の技術戦略が必要」と強調する。
経済安全保障の鍵を握る「重要技術」について本書は「他国の経済や軍事における重要な製品・サービスのサプライチェーン(供給網)上で、自国のみが有する製品・サービス、部品、素材、製造技術、製造装置といったもの」と説明。
こうした重要技術を持っていることで「他国が日本にとって望ましくない行動をとったときに、輸出規制を発動する(またはその可能性を示唆する)ことで、行動を改めてほしいというメッセージを送ったり、実際に行動を取る前に抑止したりといった効果が期待できる」とする。
またこの「重要技術」は「技術によって何を成せるかに注目した概念」であり“技術そのもの”ではないと強調。「経済安全保障上必要なのは、まったく新しい技術や素材を生み出すインベンション(発明)ではなく、それを活用したイノベーション(新結合)である」と説明する。
その上で「ある技術を(経済安全保障上の)重要技術である、あるいは重要技術になり得ると判定するためには、科学技術、経営学、経済学、国際政治学の知見が組み合わさることが必須となる」として、重要技術を判定、活用できる、これらの専門知見を融合した体制構築の必要性を指摘している。

著者は大手コンサルEYストラテジー・アンド・コンサルティング(東京都千代田区)の山本晃平・ストラテジックインパクトシニアマネージャー。経済安全保障上の技術戦略の視点から、企業の技術力を生かしたイノベーション創出を支援するEYの企業向けサービスを担当している。
本書は16歳から1年弱、自衛隊に在籍して以降抱いてきた各種の疑問「そもそもなんで戦争があるのか」「どうすれば平和を維持できるか」「科学技術は世界平和に貢献しているか」への「大人になった自分からの中間回答」でもあるという。山本さんは「科学技術に携わるさまざまな方々に、自身が平和へ貢献することができるということを知っていただきたい」とコメントしている。
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)