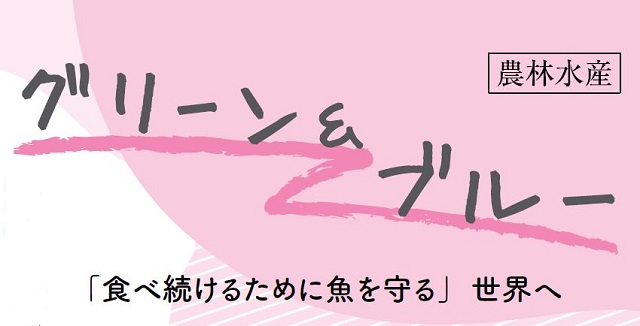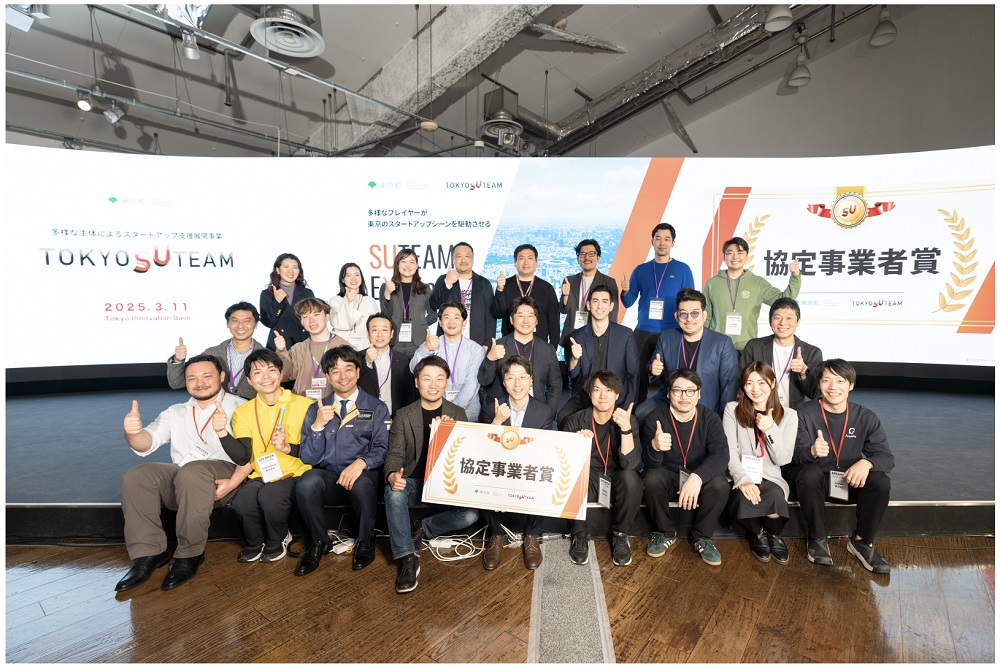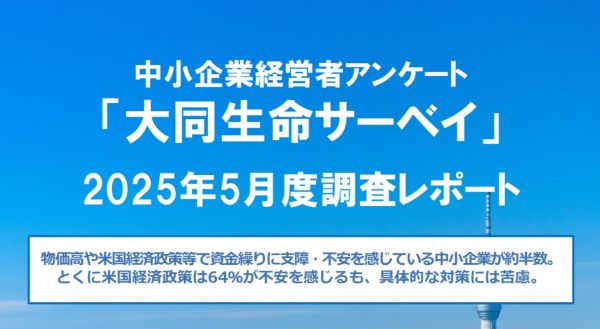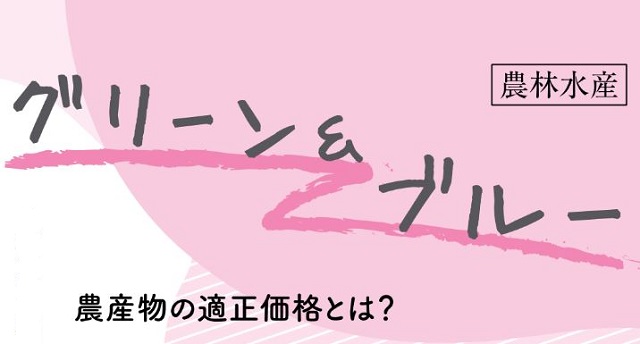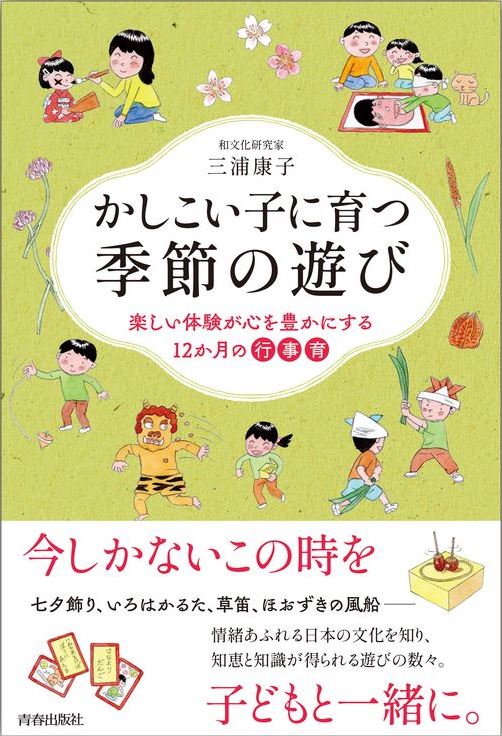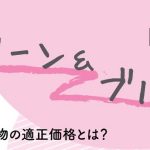高速鉄道に乗って「光」と「時空」の旅を続ける。
実は、日本統治時代より前の台湾は不毛の地だった。島の中央を縦貫する中央山脈から川が一気に海に流れこむ地形で、水が十分に利用できなかったからだ。地図を見ると、台湾の河川は「〇〇渓」という名前が多い。「渓」という漢字は急流という意味だ。それを豊かな水田地帯に変えたのは、台湾総督府の土木技師らによる治水、水利事業だ。最も有名なのは、台南の山あいにある烏山頭ダムや嘉南平原に総延長1万6千キロの排水路を造った「嘉南大圳」。責任者だった石川県出身の技師、八田與一の命日(5月8日)にはダム付近で慰霊祭が行われ、政府要人も参列する。昨年は、先日選挙で勝って5月に総統になる頼清徳副総統が花を手向けた。

みずみずしい水田が広がり、時に山の緑が迫る車窓の風景は、日本と台湾だけのものだろう。水田と新幹線と富士山の風景は、日本人であれば、そのエリアに住んでいなくても郷愁を呼び起こされる。台湾人も同じことだ。日台関係が良好な理由として、統治時代の事績や、国際政治で同じ陣営に属していることがよく挙げられる。しかし、より本質的には、郷愁を誘う風景を共有していること、平たく言えば、新幹線と高鉄の車窓の風景がそっくりなことが肝なのではないか――。高鉄に揺られながら、そんなことを考えた。
高鉄の南の終着駅「左営」は高雄市内の地区名だ。普通、漢字圏の地名を日本で呼称する際は音読みか現地語発音でするが、高雄は「コウユウ」ではなく「たかお」と訓で読む。もともとこの辺りは先住民が「ターカウ」と呼んでいたのを、漢人が入ってきて「打狗(現代中国語の発音でダーゴウ)」と字を当てたのだという。ところが、日本統治時代になって「狗(犬)」を「打つ」とは卑俗だということで「高雄」になった。現在は現地語に従い世界的に「カオション」だ。結果的にもとの名前で呼んでいるのは日本人だけという不思議なゆかりのある町だ。

高雄はおしゃれな港町だ。ことに愛河が注ぐ愛河湾というベイエリアは、名前に負けないロマンチックさだ。横浜の山下公園や神戸のメリケンパークのように整備された遊歩道に南シナ海からの風が吹き抜ける。2021年にオープンした「高雄流行音楽中心」は、シドニーのオペラハウスのように壮大なモニュメントになっていて夜にはライトアップされる。対岸にはほぼ連日夜店が出ており、恋人たちはもちろん家族連れでにぎわう「光の世界」となっている。

路面電車のライトレールでベイエリア内を少し移動すると、かつての倉庫街がカフェやブティックになった若者に人気のスポットもある。アジア最長という旋回橋も見られる。さらにライトレールに乗って市内の「内惟芸術中心駅」まで行くと、木が生い茂る中を電車が走る様子から「トトロのトンネル」と呼ばれる区間があり、日本アニメ好きの台湾人や外国人に人気だ。

高雄や台南は北回帰線より南にあって気候帯は熱帯に属するだけに、冷たいスイーツのおいしさが際立っている。「豆花(トウファー)」は大豆やゼラチンでつくられ、つるんとした食感で、小豆やフルーツと一緒にシロップをかけて食べる。「氷点」の看板を出すかき氷専門店も多い。水ではなく牛乳を凍らせた氷を使い、マンゴーやイチゴなどのフルーツをふんだんにかける。ついさっき漁港でもある高雄の海鮮料理で満腹になったはずの胃袋に何のためらいもなく入っていった。

台湾南部への旅を終え高鉄で台北に戻った翌日、今度は在来線を運行する台湾鉄道(台鉄)で太平洋側の東岸にある宜蘭を訪れた。台湾の鉄道は清朝末期に一部がつくられたそうだが、本格的に敷設が進んだのは日本統治時代になってからだ。台湾総督府ができて13年目の1908年には北端の基隆と高雄を結ぶ線が完成。しかし、東岸は急峻(きゅうしゅん)な地形もあって開発が遅れ、台湾島を1周する形で鉄道がつながったのは1991年と比較的最近の話だ。
台鉄、高鉄、地下鉄すべてのターミナルとなっていて広大な待合スペースのある台北駅で花蓮と台東の中間辺りにある瑞穂まで行く特急に乗った。位置関係で言えば、宜蘭は台北とは富士山より高い雪山(3886メートル)を中心にした雪山山脈を挟んだ位置にあり、列車は山あいを抜けていく。台湾で最も雨が多い地域といい、筆者が特急で通った日も降っていたが、今回の宜蘭訪問はこの雨がポイントだ。山脈を水源とする豊富な天然水で、「熱帯や亜熱帯の台湾では不可能」とされていたウイスキー造りを成功させたカバランウイスキー蒸留所の見学が目的の一つだからだ。


宜蘭駅の駅舎は1945年にできた古いものだが、今は駅とその周辺が地元出身の絵本作家、ジミー(幾米、本名・廖福彬)の作品世界を表現したファンタジー空間になっている。壁がジャングルのようにペイントされた駅舎の屋根からは大きなキリンが姿を現している。通りを挟んだ広場は、大きな緑色の天蓋(てんがい)があり空中を蒸気機関車が走っている。特に観光地化されておらず、地元の人がちらほらと歩いているだけという様子が、かえって作家への親しみを感じさせた。駅横の公園を見ると、男性と女性が旅行かばんを引いて反対方向に歩いていく像があった。ガイドに聞くと台湾人ならだれでも知っている物語の一場面だという。看板に作品のテーマが記されていた。「人生は偶然に満ちている。2本の平行線もいつか交わる日がくるかもしれない」。深い。筆者などこれまで平々凡々たる人生を送ってきた部類だが、こう言われると心に若干のうずきを感じ、しばし自分史の時空をさまよった。

カバランウイスキー蒸留所は市内から車で20分ほどだ。カバランというのは、先住民語で宜蘭一帯を指す言葉だという。敷地は36ヘクタールと広大で、蒸留所には見学施設が併設されている。ユニークなのは、見学後にウイスキーを自分で調合してオリジナルボトルをつくる「DIYブレンディング体験」があることだ。外国人の観光客も多く、今年の訪問者数は2月末の時点で3万人に達していた。

台湾は2002年の世界貿易機関(WTO)加盟をきっかけに専売制が廃止され民間の酒造が可能になり、海外展開もしている大手飲料メーカーがウイスキー造りに乗り出した。一般にウイスキーの醸造には本場のスコットランドのような寒冷な気候が適していて、挑戦を無謀だという声も多かった。しかし、研究と試行錯誤の末、高温多湿のハンディを逆手にとり、熟成を早める製法を編み出したという。担当者は「スコットランド産で12年かける熟成を6年で行う」と胸を張った。世界的なコンクールの受賞歴もあるといい、味の方も折り紙つきだ。

さて、DIY体験。目の前に、異なった樽(たる)で熟成された4種類のウイスキーと、小さなグラスと試験管が用意される。一つ一つ、香りをかいで試験管からグラスに注いで調合する。少しずつ割合を変えるだけで香りや味わいが変わるのが分かる。最後に気に入った配合割合を係員に告げると、ボトルを1本つくり、ネーム入りのラベルを貼ってくれる。日本に帰ったら台湾の旅を思い出しながら一杯やろうと、早速、心がうきうきしてきた。(<下>に続く)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)