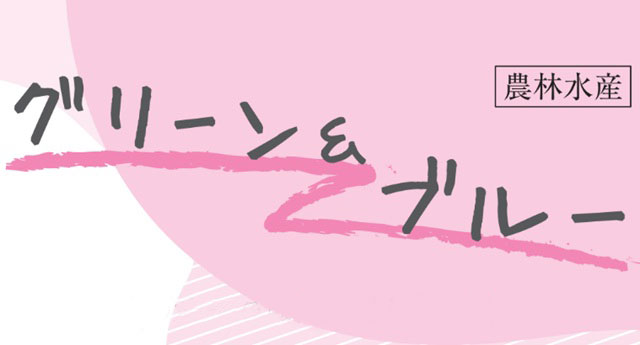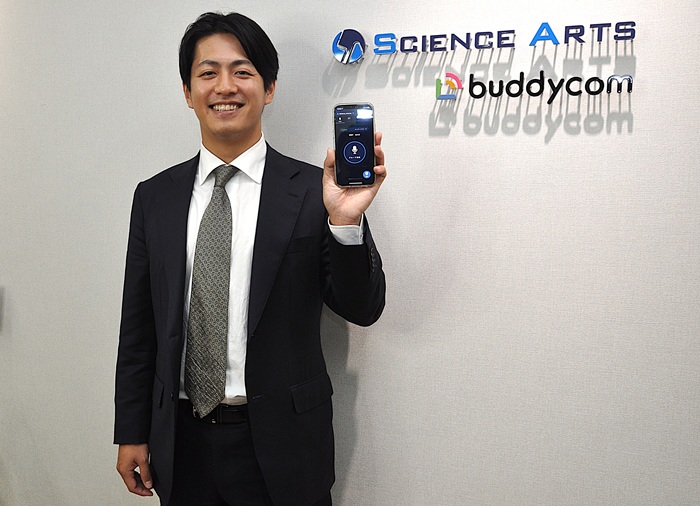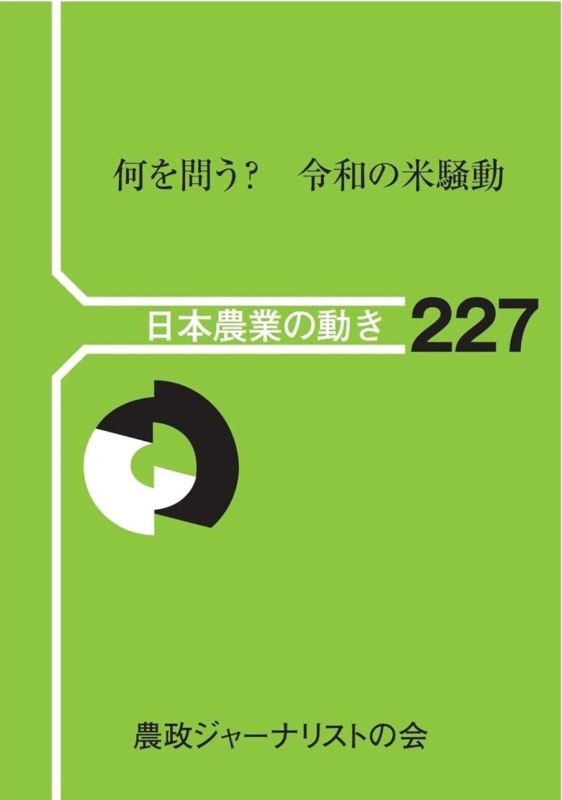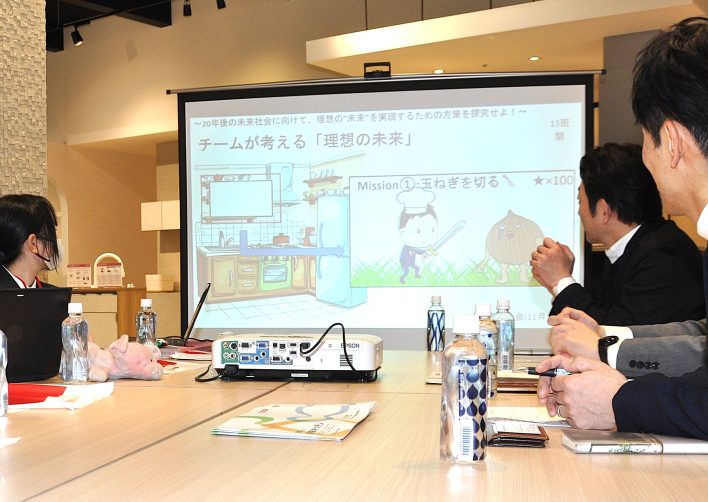国会がようやく開幕。そしてわが国憲政史上初の女性首相が誕生したが、この国会ではこの間、国民や米に関わるさまざまな業界を悩ませ続ける米行政の問題を、将来に向け徹底した審議と究明を期待したい。
新内閣は当初から新農相が誰になるか、で米対応への本気度がわかる、とされたが、農水省元キャリア官僚で、「理屈で政策を考えるタイプ」(自民党内)の鈴木憲和議員(43)を起用、強い本気度を示した。農業県山形選出で「米マニア」を自認。党の米の需要拡大プロジェクトチームの座長を務め、農林部会長代理の後は岸田、石破の両内閣で農水副大臣とひたすら農林族幹部への道を歩む期待の人材だ。
見識と経験と情熱を備えた新農相だけに明確な出口の見えない「令和の米騒動」解決には強い思い入れがあるのは当然だろう。急激な物価高や実質賃金の低下の中、米需要を延べ60万トンも見誤り、生産農家の米生産を抑制したあげく、一時、政府備蓄米放出をかたくなに拒み、結果として多くの生活困窮世帯の家計を直撃するまれに見る失態を演じた米行政の信頼回復に、期待がかかる。
失態の背景には「米消費は減るもの」との思い込みや、業界や国民への傲慢(ごうまん)な態度がある。
そんな姿勢が見えたのは、8月初めに米行政の失態を謝罪した場面。農水事務次官ら幹部が自民党で農林議員らに異例のみっともない謝罪をしたが、国民にはといえば小泉前農相が定例会見で、たまたま記者の質問に答えたかのように「騒動の責任の一端はわれわれに…」とかなりわざとらしく釈明した。
同省の責任は決して「一端」ではなく、大臣単独で謝罪会見を開くべきだった。鈴木農相にはこうした省の体質を変える一方、あくまで国民を優先した対応を期待したい。
さらに国会審議で与野党議員にも注文したい。米集荷競争の過熱と市場まかせの流通との関係をどう見るか。なぜ10年後の農地の耕作者未定が相次ぐほど稲作が若者や農家後継者に忌避されるのか。成立後20年余経過する改正食糧法など法制度の見直しは必要ではないのか、など議論をできるだけ深掘りすべきだ。
「価格はマーケットで決まるもの」「米価格にはコミット(関与)しない」との信念を持つ鈴木農相だが、国会審議を真摯(しんし)に受け止め、2027年度からの崖っぷちに立つ新たな米政策にぜひ生かしてほしい。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.42からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)