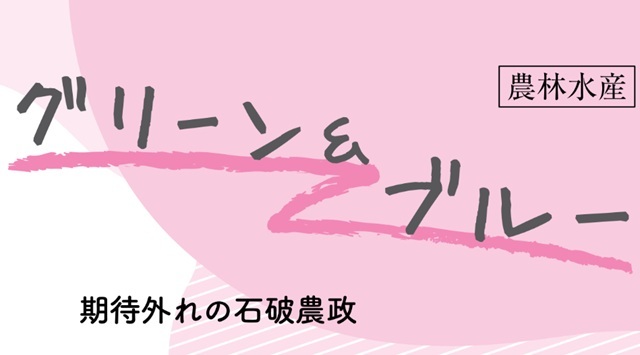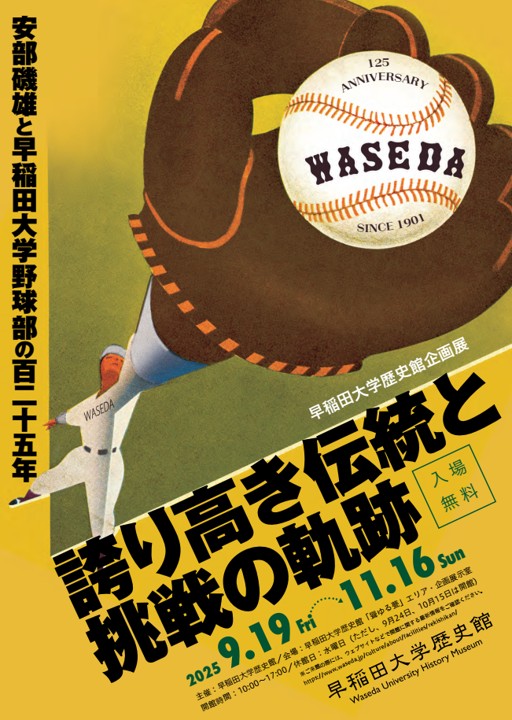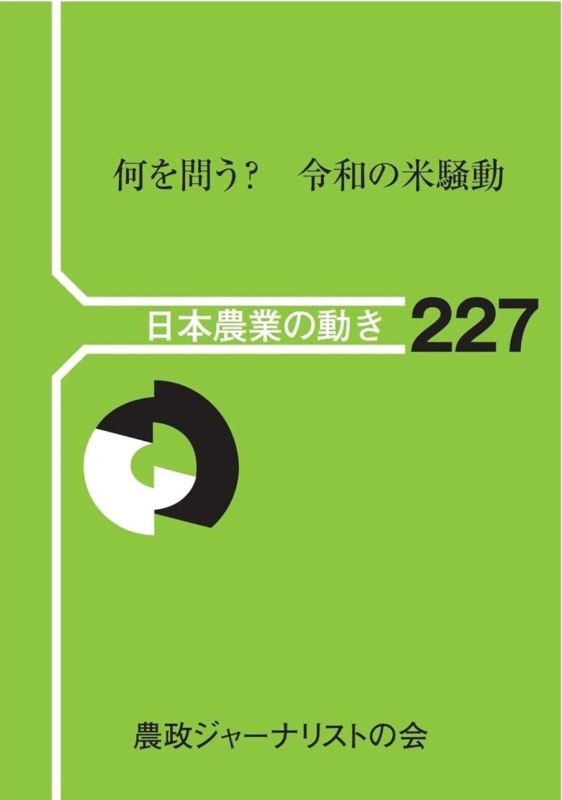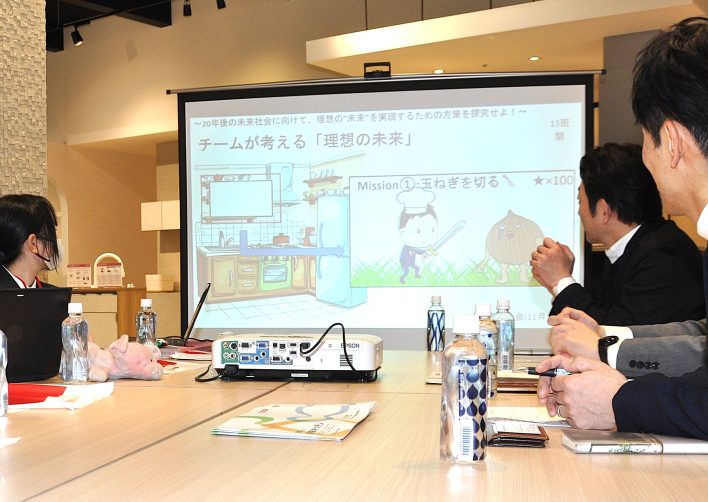政権発足から1年弱というところで石破茂首相は力尽きた。農林水産大臣を経験した首相なだけに、農業振興や農村活性化に従来路線から変わる、個性的な新味を農政に打ち出すのでは、と生産現場では期待する声も多かったが、結局は期待外れだった。
自民党総裁選では食料安全保障や食料自給率の向上に加え、米の生産調整継続への疑問、直接所得補償の導入など多少は思い切った発言もしていただけに、「石破農政」とは何を目指し、どういう構想や手法なのか、その全体像を示してほしかった。
特に農政は首相のライフワークである地方創生や防災と密接に絡む政策だ。農業・農村を活性化することが若者を地元にとどめ、地方の賑(にぎ)わいを維持し、自然景観や国土の保全にもつながる関連性がある。都市生活者や消費者にとってどれほどありがたいことかを強調すべきだった。
それによって農業政策はより生き生きとし、地方創生をより強靭(きょうじん)なものにし、地域社会をリスクの少ない体質にするとの意気込みがほしかった。
もとより仲間は少なく、党内基盤は弱い。弱いがために政権発足早々、衆院解散・総選挙を打ち出し、基盤強化を求めたのだろうが、東京都議選、参院選と負け続けた。
さらに運が悪かったのが米騒動の最中に政権に就いたことだ。前年の倍にも高騰した米価は消費者の猛烈な反発を受けたが、当初原因がよくわからなかった。農水省は業界団体や有識者の指摘にも頑として首を縦に振らず十分な検証をしなかった。
しかし、6月の閣僚会議で首相自ら指示して需給の検証をさせたところ、2023年の米生産が需要に対して大凶作に匹敵する最大56万トンも不足、24年も同じく最大32万トンが不足していたことが判明。
農水省が需要の見通しを誤り、生産農家に抑制的な作付けをさせていたのだ。史上稀(まれ)に見る農政の大失策であり、背景には農水省の「需要は基本的に減少傾向にある」という硬直的姿勢があった。農水省は石破首相には親和性のある官庁だったが、物価高に悩む有権者は反発を強め、結果として政権の寿命を縮めさせたかもしれない。
一方、石破首相の退陣騒ぎを横目に令和の米騒動は、終結の見通しが立っていない。稲作地帯には「大手の卸が農家の庭先に頻繁に来ている」(東北地方のJA営農課長)。「JAの概算金に2千円くらい上乗せ」(同)するケースがあるという。新政権発足を待たず早期に国会を開き、与野党あげての米論議が待たれる。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.36からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)