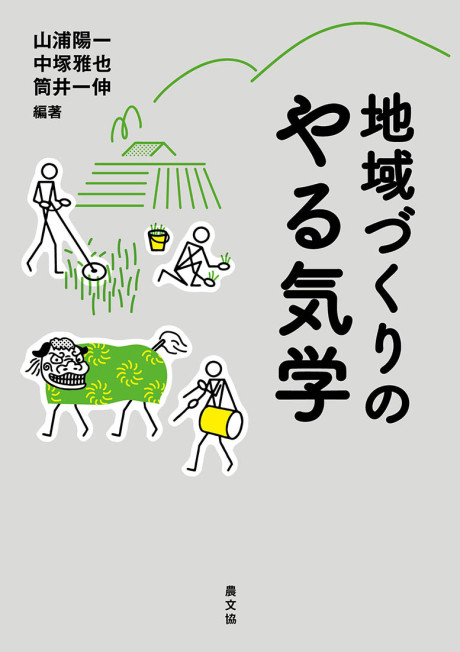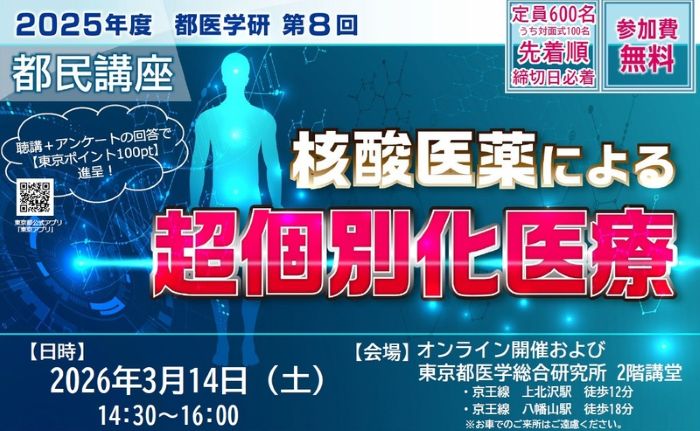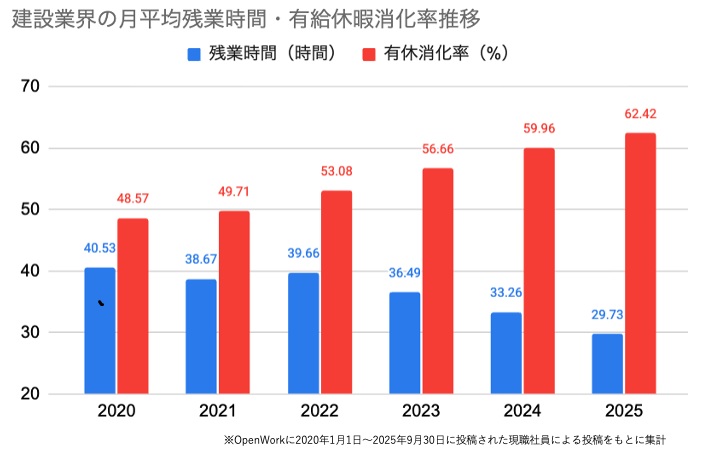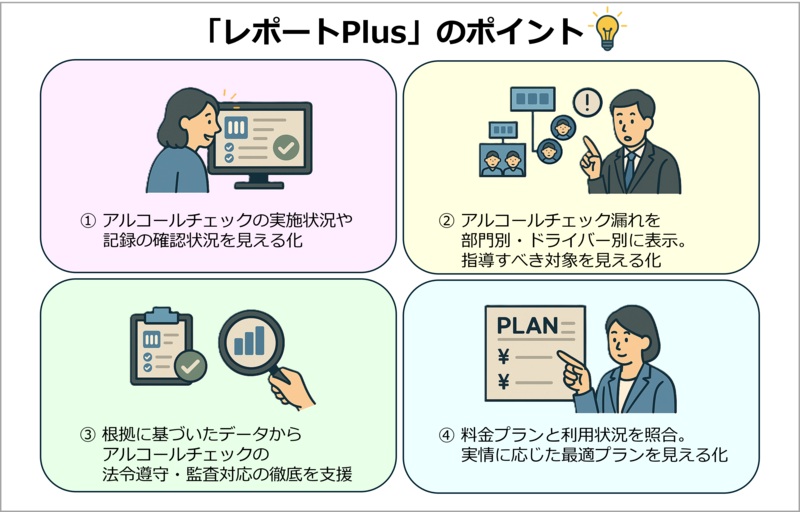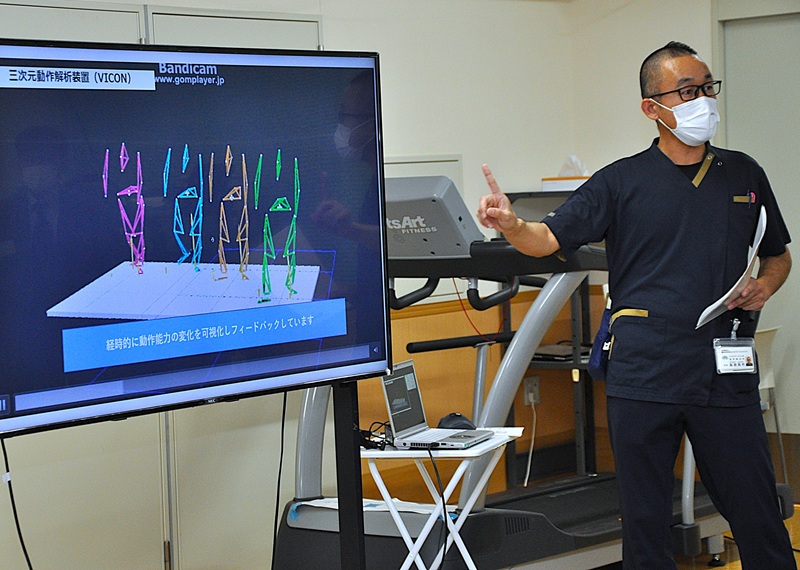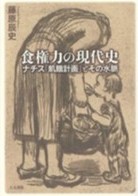地域の活動の大切さは十分に認識していても、その役職を自ら手を挙げて引き受けるのはハードルが高い。本書の最大の特徴は、地域の活動を支える指導者の育成ではなく、あまりやる気がなく、参加する動機も、経験や知識も乏しい「普通の人」が地域づくりにどう向き合うかを論じている点だ。
「地域のため」という献身的な動機だけでは、活動を持続できず、少数の優れた指導者や意識の高い行政職員によって成功している事例を「横展開」してみても、「やっぱり人材だよね」で終わってしまい、参考にならない。
本書の第1部「事例編」では、地域福祉、ため池管理、草刈り隊、地域おこし協力隊、農泊などさまざまな現場の実態を報告している。「全然(活動に)参加せんくせに、誰がものいうてんや」など、「あるある」とうなずく具体例が満載だ。事例ごとに「コラム」の形で解説があり、土地改良区など農村の活動とは縁遠い読者でも理解できるように工夫されている。農村の事例が多いが、もちろん「地域づくり」は都市部の課題でもあり、自治会はもちろん、ボランティア活動、読書会などのサークルなども地域を支えるコミュニティーだ。
第2部「考察編」では、「普通の人」が地域づくりに参加し、活動の支え手になる要点を探究する。広く・浅く関わる人材を増やすためには、やる気と実際の活動のギャップをどう埋めるかが焦点だ。本書は、意外にもそのキーワードを「慣れる・つるむ・さぼる」だと指摘する。
参加の動機や意識はコミュニティーとの関わりの中で変化していく。できれば「いきいき」と活動できる方向に進化するのが望ましいが、「しぶしぶ」参加している人にとっては、適度にさぼってバランスをとることも重要だ。難しいことは役職者に任せ、自分に関係が薄い活動は欠席し、最後は「諦める」もありだという。
私事で恐縮だが、評者は任意団体「農政ジャーナリストの会」の会長を半ば義務感で引き受けたことがある。執行部の会合は欠席者が多く、役職の担い手の確保は難しく、高齢化も著しい。どうしたら若い人が参加してくれるか、だれか仕事を引き受けてくれないか、後継者を育てなくては、ということばかり考えてきたが、本書はその誤りに気付かせてくれた。「なんだ、さぼっても良いのか」。大きな脱力感が、読後の偽らざる感想だ。
山浦陽一・大分大学経済学部准教授、中塚雅也・神戸大学大学院農学研究科教授、筒井一伸・鳥取大学地域学部教授の3人の編著者のほか7人の研究者が各章を分担・執筆している。一般社団法人 農山漁村文化協会(農文協)から2025年3月5日に出版された。1980円(税込み)。
(共同通信アグリラボ編集長 石井勇人)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)