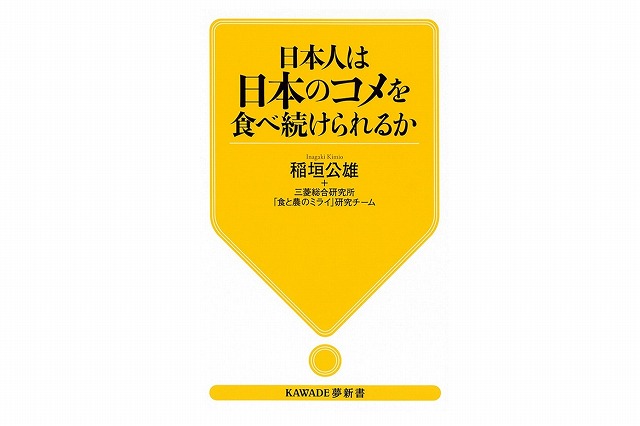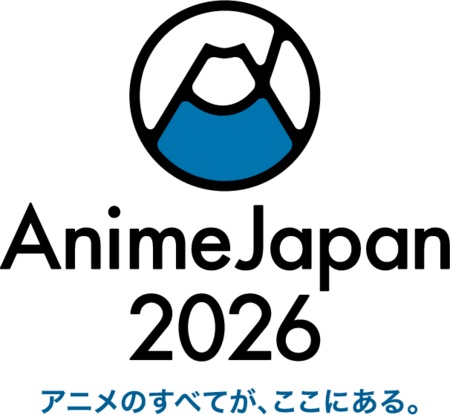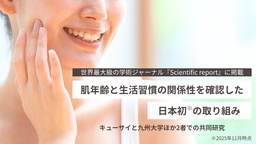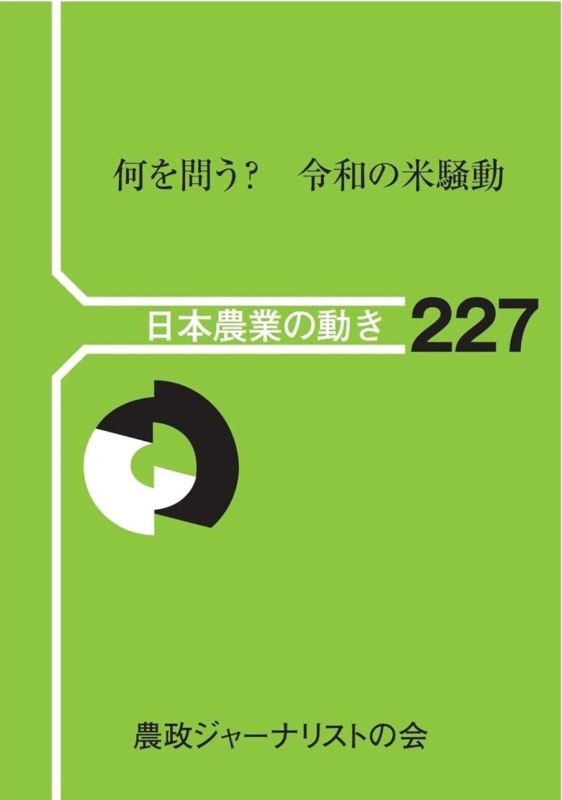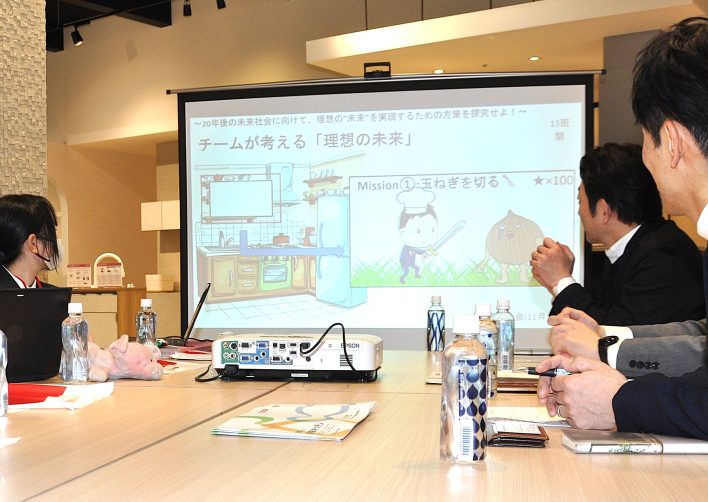桜の満開と重なった週末3月30日の午後、若者や家族連れでにぎわう東京・青山から表参道、原宿にかけて30台のトラクターが行進し「農を守れ」「米農家の時給は10円」「農民を殺すな」などと訴えた。この「令和の百姓一揆」の5日後、「タリフマン(関税男)」を自称するトランプ米大統領は、日本からの輸入品に対して24%の関税を課すなど「相互関税」を発表した。自由貿易体制を全面否定するような高率に驚いたが、日本の米を特定して「700%」の関税を批判したことにはもっと驚いた。
発言の真意は不明だが、ホワイトハウスのレビット報道官は3月11日に同様の発言をしており、トランプ政権内に強く刷り込まれているのは間違いない。日本にとって米が「聖域」だと見抜いた上での発言だろう。「700」という数字に、20年前の通商交渉関係者はある種の懐かしさを覚えるかもしれない。
農水省は、2005年の世界貿易機関(WTO)交渉時に米の関税(従量税)を「778%に相当」と説明したことがあるからだ。当時の内外価格差が大きかったこともあるが、WTO交渉では関税の一律削減が焦点になっており、それに備えて「糊代(のりしろ)」を大きくとっておこうという思惑があった。この数字が逆手にとられるとは、隔世の感を禁じ得ない。
政府備蓄米の放出後も米価は高値で推移しており、消費者の不満がトランプ政権の「外圧」と結びつけば、米政策は大きな転換を迫られる。既に日本側の自動車業界など米国への輸出を経営の柱としている産業界には、対米交渉で「農産物と規制緩和ぐらいしか差し出すものはない」という動きがある。
相互関税を受けて目下の世論は、自由貿易体制の擁護論一色だが、自由貿易は優勝劣敗、構造調整を迫られる側にとっては災禍でしかない。「令和の百姓一揆」に参加した生産者や消費者の多くは、環太平洋連携協定(TPP)に反対した人たちであり、米の自給体制の維持を求めている。彼らは、グローバリズムに翻弄され、疲弊し、地域の崩壊に直面し、自分たちの生活とコミュニティー(地域)の維持を訴えている。
1次産業(米)と2次産業(鉄鋼・自動車)の違いはあっても、求めていることはトランプ政権の主張とそっくりだ。貿易の自由化に伴う構造調整は、本来は所得再分配などを通じて各国政府が取り組む国内の課題だ。米国の歴代政権はそれを怠り、忘れられて置き去りにされてきた人々の怒りがトランプ政権を支えている。トランプ政権の政策は理屈に合わず、矛盾だらけで、前向きに評価できる点はひとかけらもないけれども、少なくとも「一揆」の参加者は、構造調整の犠牲者の怒りを共有するだろう。
一方、自動車産業など自由貿易の勝者や傍観者は、日米双方に存在する犠牲者の痛みを十分に理解する努力をしてきただろうか。長年の低米価のメリットを享受し、農家の疲弊を看過しておいて、米が不足し米価が高騰すると「輸入が日米双方の利益」と考えるとしたら、あまりにも鈍感だ。
「百姓一揆」の実⾏委員会の菅野芳秀代表(75)は「ムラから農民が消え、ムラそのものが消えようとしている。都会の消費者はそのことを知らないでいる(中略)やわらかく、おおらかな、のびのびした運動を続けていこう」と呼びかけた。
自由貿易体制の推進論者や擁護論者に求められる姿勢は、構造調整を迫られる人々に対する思いやり、共感、加害者意識だ。日本のこれまでの政策にそれが十分だったとはとても思えない。「関税男」や「百姓一揆」の怒りを鎮めようとするならば、その原点は加害者意識が十分だったかどうかの反省にある。
高率関税を免れるために、農業を差し出すという発想は論外だ。目先のディール(取引)が成立しても根本的な解決にはならない。対米交渉にあっては、置き去りにされた人たちに直接の恩恵が及ぶような直接投資や調達(米国からの輸入)の構想を示す必要がある。国内にあっては、中小規模の農家も対象に含めた戸別所得補償型の直接支払いや集落機能の維持を促す政策を、できるだけ早く実現することだ。
(共同通信アグリラボ編集長 石井勇人)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)