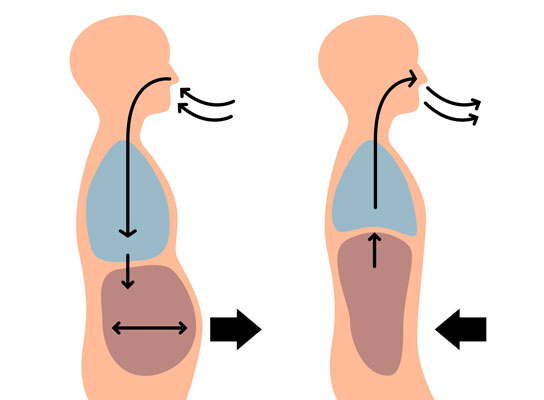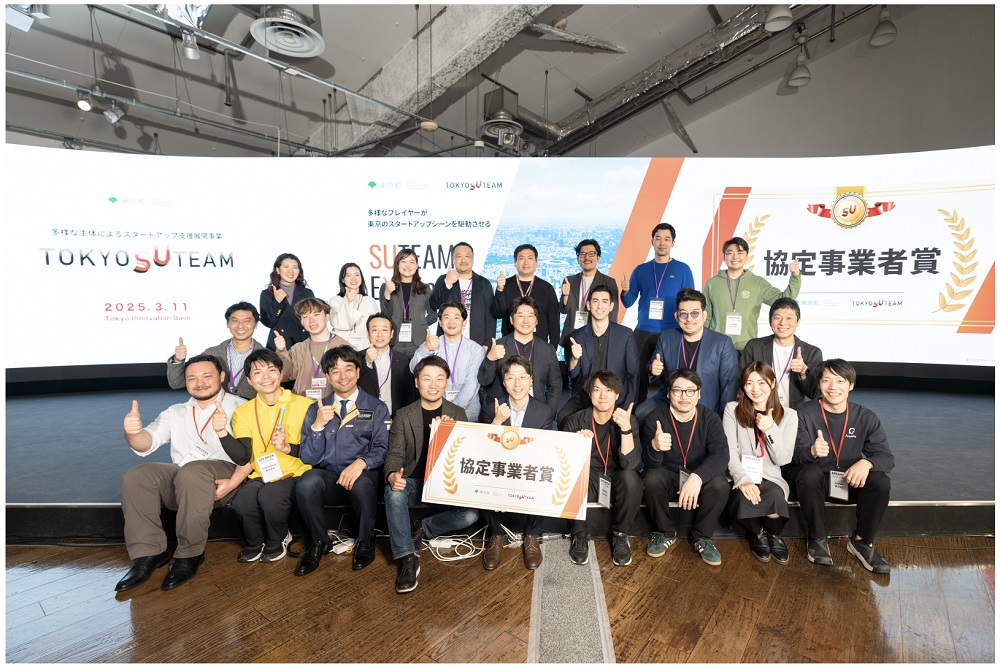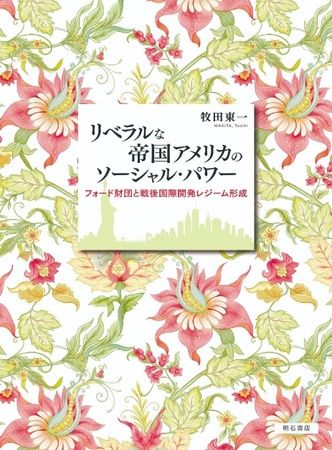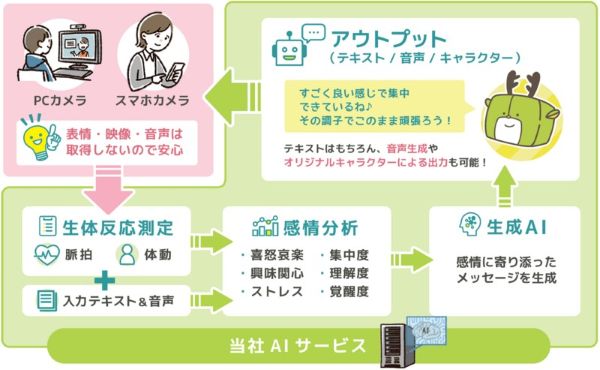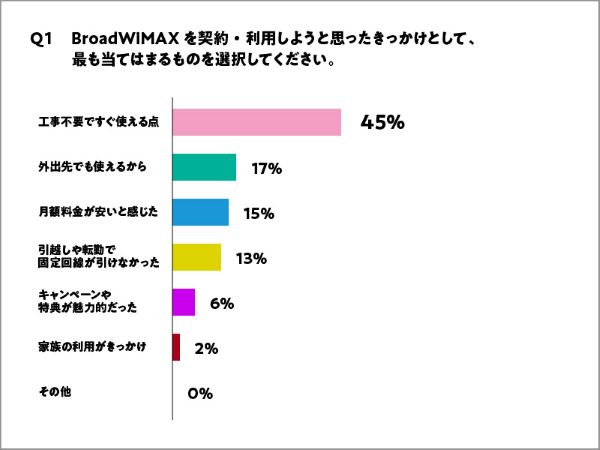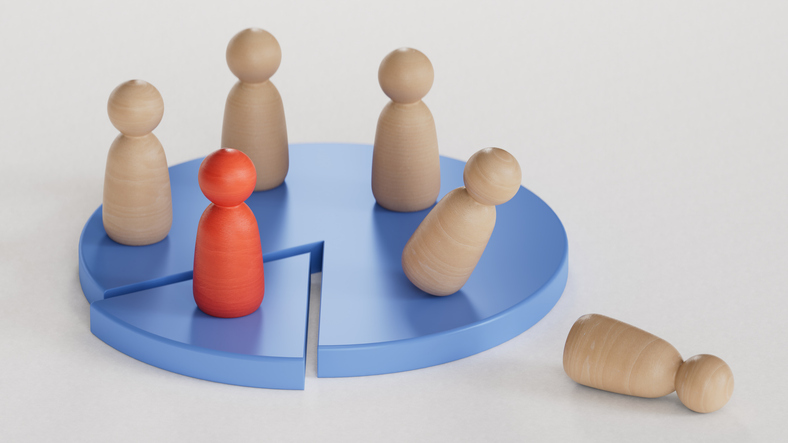東京農業大学は、ザリガニを新たな資源として活用するため、ケニア共和国の大学や企業と共同して養殖・食品加工・普及に向けた研究を加速する。江口文陽学長は「(研究成果が)食材としての活用につながっていくことに大きな意味がある」と社会実装の重要性を強調している。

嫌われ者が国際貢献
日本で生息するザリガニのほとんどは、米国から持ち込まれたアメリカザリガニで、生態系を脅かすとして今年6月から条件付特定外来生物に指定されるなど、人気はいまひとつだ。特に稲作農家にとっては、畔(あぜ)に穴を開け、稲の茎を食いちぎるなど嫌われ者で、泥の中に生息する印象から食材として認知されていない。

一方、海外では欧米や中国などでもアメリカザリガニを中心に、ザリガニは重要な食材で、養殖され市場も拡大している。共同研究では、ザリガニを持続可能な食料資源として位置付け、雇用の創出など地域経済だけでなく、気候変動対策など国際的な貢献を目指す。

12月8日に東京農大世田谷キャンパスで開かれた研究発表会で、共同研究の代表を務める武田晃治教授(写真)は、尻尾の筋肉部分は、高タンパクでオレイン酸に富み、GABAなど機能性成分も多く含むと説明し、「長期的な持続可能な食材にするためには閉鎖型の養殖技術やゲノム編集技術を使った筋肉部分の増量が課題になる」と指摘した。
捨てる部分がない
共同研究のケニア側のパートナーであるジョモ・ケニヤッタ農工大学(JKUAT)のギシェハ・マシュー・ギタウ博士は「ザリガニの養殖は畜産業と比べて環境負荷がずっと小さく、持続可能な農業を促進し、気候変動対策に貢献できる。中小規模の農家の収入になり、貧困を減らし、栄養を改善し、食料安全保障に寄与する」とメリットを説明し、「ザリガニを資源として活用することで持続可能な農業を目指し世界に貢献したい」と述べた。

ザリガニを食材として商業ベースに乗せるため、研究にはケニアの養殖企業の「キスメオ有機」が参画している。同社のヌドゥン・ロビンさん(写真)は「コロナ禍前はナマズを養殖していたが、ザリガニはコストが低廉で、中小農家を支援できる。産卵数が多く指数関数的に増殖し、成長も早い。インドネシアのようなイスラム圏の市場も有望、需要が大きく伸びている。殻も含めて丸ごと食べられるが、殻は肥料や食品添加物などにも利用でき、捨てる部分がない」と述べ、養殖の事業化に強い意欲を示した。
難点は殻むき
共同研究は、最終的な消費段階での認知を重視しており、アメリカザリガニの食用例として、柳原料理教室を主宰する江戸懐石近茶(きんさ)流宗家の柳原尚之さん(写真)が、炊き込みご飯、かき揚げ、胡麻和えの3種類の料理を試作、研究発表会の会場で試食用に提供した。

柳原さんによると、ザリガニはエビとほぼ同様に調理できるが、1匹から小指の先ほどの身しかとれず、手作業でむく作業が難点。「農大の学生に手伝ってもらった」という。

当日は、ケニア風の塩茹など様々なザリガニの調理例も発表、試食用に提供された。いずれも、臭みはなく、エビと比べると歯ごたえがある。

来賓として出席した在京ケニア大使館のズガ・セリン2等書記官は「日本と国交を結んで60年の節目で、食料安全保障や食のサプライチェーンが大きく変わろうとしている。両国の研究者が連携することは時宜を得ている」と挨拶した。(文・写真:石井勇人共同通信アグリラボ編集長)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)