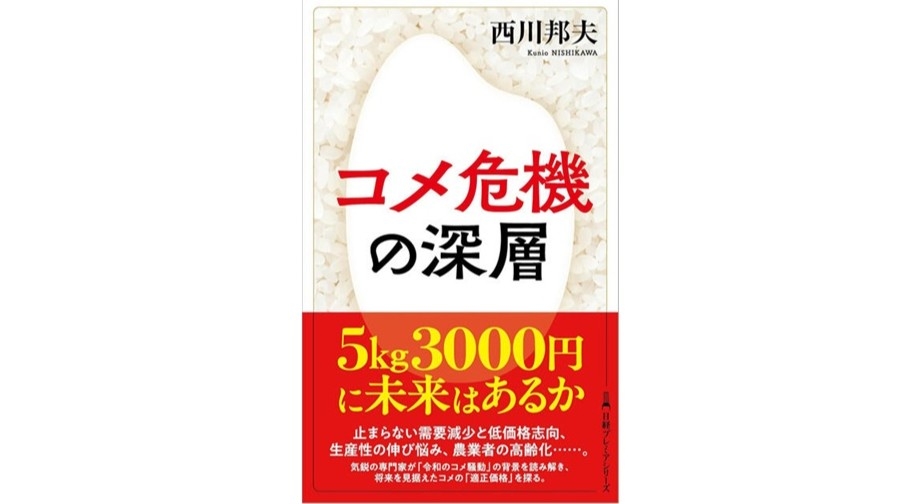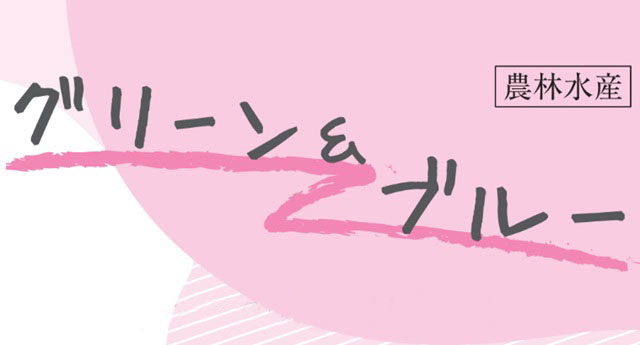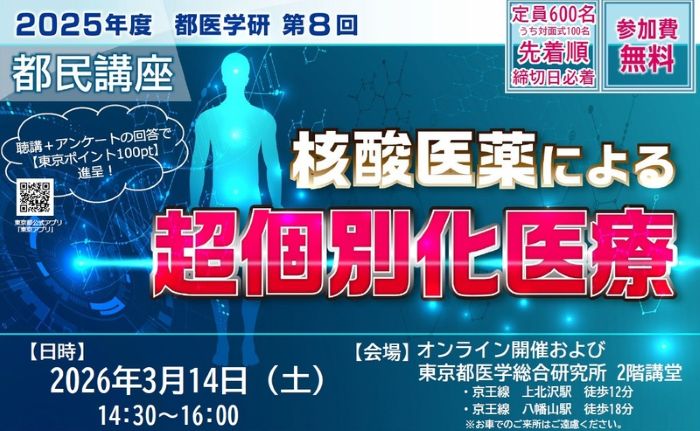米価が高止まりしている。2025年産は大幅な増産が見込まれているのに、店頭価格は5㌔㌘4000円前後で値上がり前の2倍近い。需給は緩和しているのに、なぜ値下がりしないのか。主食用米の需給バランスに着目し、米価の高騰をいち早く予想した茨城大学の西川邦夫教授が、「令和のコメ騒動」の背景と米の生産・流通の構造的な課題を、わかりやすく解説する。
著者は、米価高騰の初期段階から、「(高騰は)需給変動と価格弾力性で説明できる古典的な事象」と指摘し、需給ギャップ(米不足)が解消されないかぎり高値が続くと予想した。経済の原理・原則に基づいた説明は単純明快で説得力がある。しかし、現在は政府備蓄米の放出や稲の作付面積の拡大で、米の過剰が予想されている。米相場の価格を見通すのは難しい。本書は「米の消費にはまだ分からないことが多い」と、需要側の分析の不足を認めている。
特に、価格の変化と購買量の関係を示す「価格弾性値」の議論は不十分だ。一般論として米のような必需品の弾性値は「低い」とされているが、実際にどのくらい低いのか。米の消費パターンが多様化し、価格弾性値は世代や所得階層によっても異なり、パンや麺類との代替性も強まっていると思われるが、今のところあまり論じられておらず、今後の研究を期待したい。
米の価格に限らず、著者の説明は一貫して原理・原則を踏まえている。特に、現在の生産調整について「正式な国の政策である」という指摘は、メディア関係者にとって極めて重要だ。食糧法は「生産調整の円滑な推進」(2条)、「生産調整方針の作成者に対する政府の認可」(5条)、「政府による助言と指導」(6条)を規定しており、生産調整は「実質的な」というただし書きを付けるべきではなく、名実ともに国の政策だ。
共同通信を含む多くのメディアが「事実上の減反政策(生産調整)」と表記し、当の政府が「減反を廃止した」(安倍晋三元首相)と説明し、あたかも少なくとも形式上は生産調整が廃止されているような印象を与え、読者を誤認させてきた。表記の再考の必要性を痛感した。
また、「適正価格」という表現にも注意が必要だ。本書は生産者、消費者、国際市場の観点から3種類の価格を説明しているが、そもそも「適正価格」という表現に明確な定義はなく、昨年改正された食料・農業・農村基本法にも存在しない。改正に先立って示された審議会の基本法検証部会の「最終とりまとめ」の中で「適正な価格」と書かれていたのが、法案の段階で「合理的な価格」に差し替えられた。
その経緯は明らかではないが、価格の「水準」を論じる以前に、「適正価格とは何か」が問われなければならない。本書は、日経BP/日本経済新聞出版から発行された。定価1210 円(税込み)。
(共同通信アグリラボ編集長 石井勇人)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)