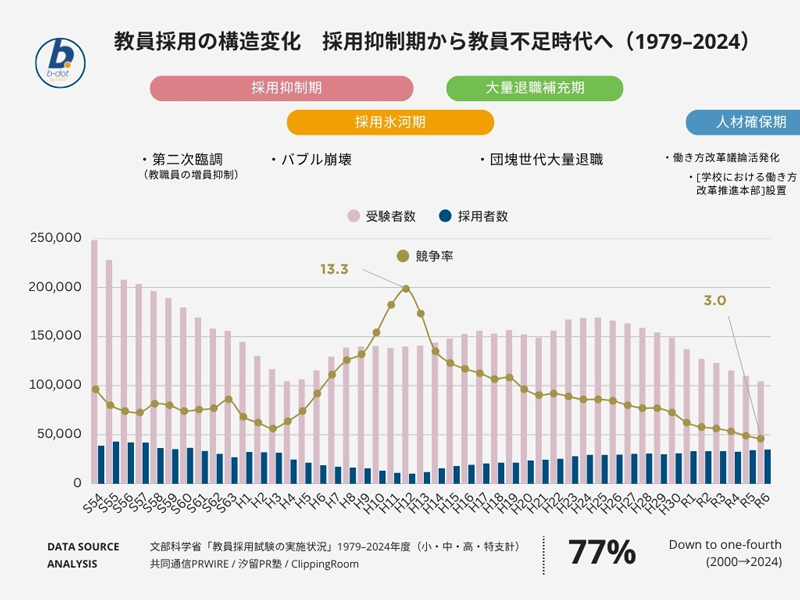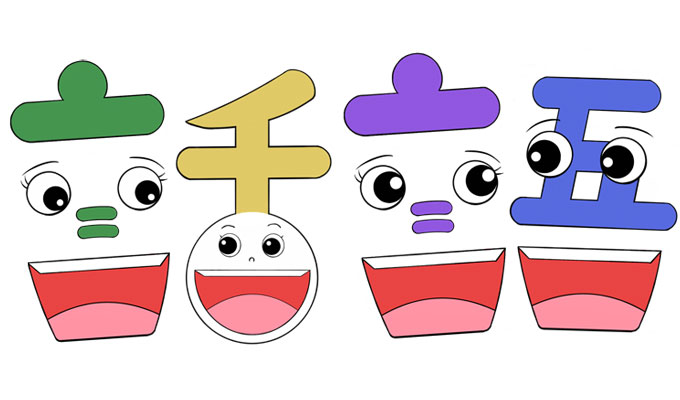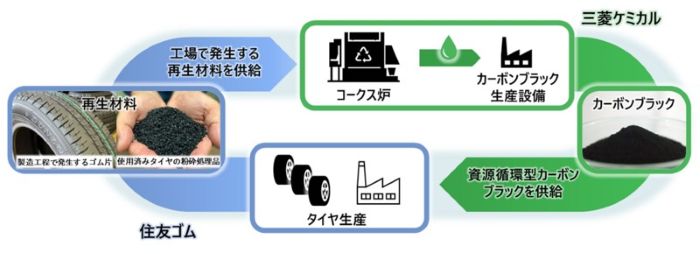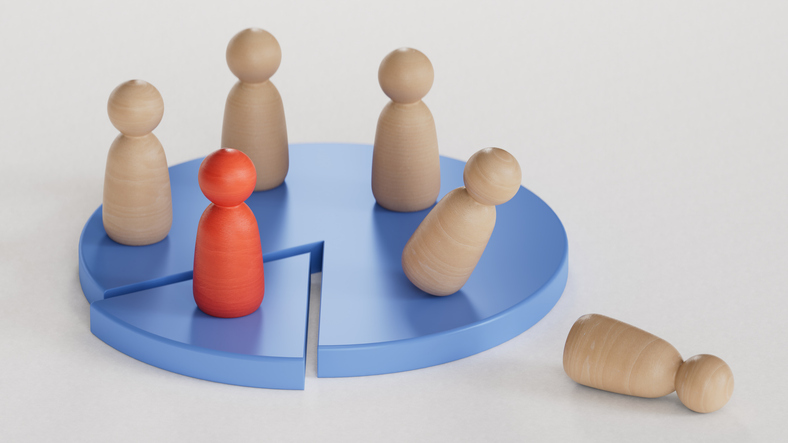近江国、滋賀県は行くたびに魅せられる。県の面積の約6分の1を占める琵琶湖の周囲には、豊臣秀吉が最初の居城を築いた長浜、国宝の城がある彦根、近江商人発祥の地の近江八幡、歴史的な寺社が数多い大津…と、訪ねる価値のある市と町がめじろ押しだ。オーバーツーリズムとは無縁で、落ち着いて散策できる。
食も素晴らしい。稲作が盛んで、かつて日本穀物検定協会の食味ランキングでは滋賀県産の「日本晴」という品種のコメを基準にしていたほどだ。近江牛はブランド和牛の中でもとびきり歴史が古く、江戸時代に「ご養生肉」としてみそ漬けが彦根藩主の井伊家から将軍への献上品や諸侯への贈答品に使われていた。
特徴的なのは、琵琶湖の魚介を使った郷土料理だ。かつて日本各地に根付いていた淡水魚の食文化は、河川の汚染と人々の嗜好(しこう)の変化で衰退した。琵琶湖でも外来魚のブラックバス、ブルーギルの増加や水質悪化などの影響で資源量は減少しているが、今も日常的に利用される。コアユを天ぷらにしたり、ホンモロコを素焼きにしたり、スジエビを大豆と炊いたりと、おいしいレシピがたくさんある。西岸の高島市では、ナマズですき焼きを作るそうだ。
先日、念願だった琵琶湖博物館を見学し、好きだった淡水魚がますます大好きになった。JR草津駅からバスで25分の烏丸(からすま)半島にある、湖をテーマにした日本でも珍しい総合博物館だ。期待した以上に展示が充実し、半日では足りないくらいだった。自然と文化の両方を扱い、食に関係する展示は多岐にわたる。
琵琶湖の生い立ちは400万年前に遡(さかのぼ)る。普通の湖は流れ込む土砂で埋まって数千年で消滅するが、その何十倍も長生きしている世界でも数少ない古代湖の一つだ。琵琶湖にしかいない固有種の魚は17種、貝は30種もあり、豊かな生物多様性が独自の食を育んだ。伝統食の代表ふなずしは、子持ちのニゴロブナと飯を一緒に漬け込み、半年以上も乳酸発酵させる。酸味と複雑な風味を持ち、食べ慣れるとクセになるという。
楽しいのは、淡水生物の展示としては国内最大級の水族展示室。琵琶湖や滋賀県の河川にすむ在来の魚のほぼ全種類を含む100種以上の魚と、世界の古代湖で独自に進化してきた生き物が観察できる。小型の淡水魚は美しい種が多く、見惚れてしまう。
湖の魚、地元野菜、近江米、近江牛を使った料理を出すレストランも出色。固有種ビワマスと外来種ブラックバスを組み合わせた「湖の幸の天丼」も魅力的だったが、ライスで琵琶湖の形を再現した「びわ湖カレー」を試した。広くて深い琵琶湖だからライスの量がたっぷりで、コメ高騰の折ありがたくいただいた。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.29からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)