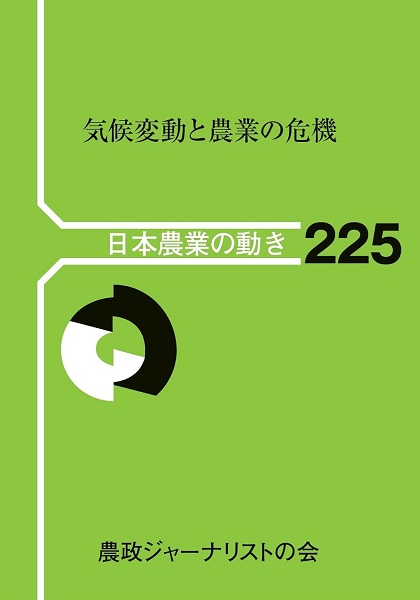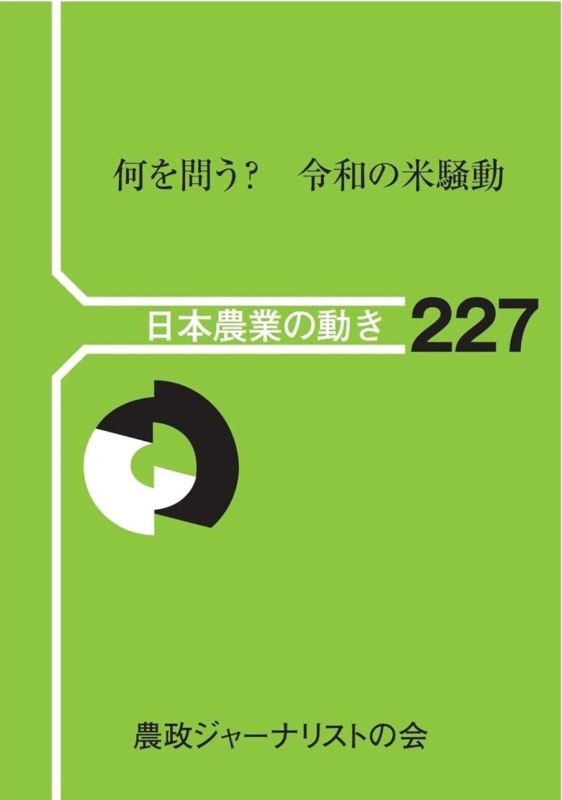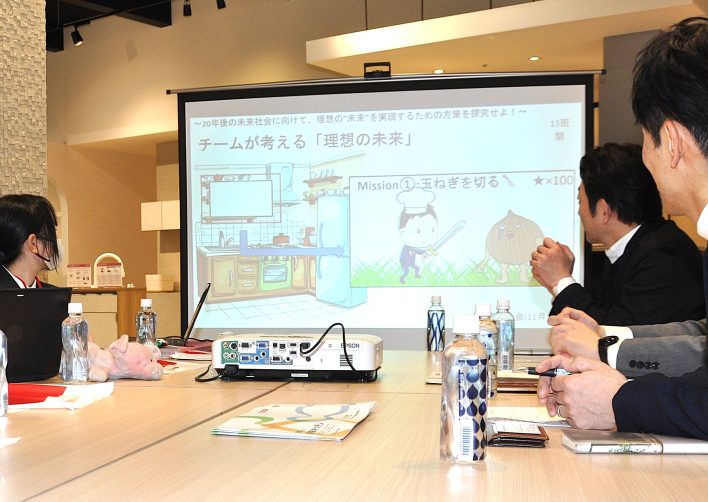トランプ米大統領は1月に政権復帰を果たすと直ちに、気候変動対策の国際枠組みであるパリ協定から離脱する大統領令に署名、インフレ対策として「掘りまくれ」と石油の増産に拍車を掛けている。農業政策への影響も無視できない。農務省のウェブサイトから気候変動対策に関連したページがごっそりと削除された。
ただ、米国に追随する国はなく、米国の正式離脱も来年1月だ。トランプ政権の「孤立主義」がいつまで続くのかは見通せないが、気候変動対策を進めなければ人類の持続的な発展はあり得ないという国際潮流は不変だ。
本書は、「農政ジャーナリストの会」が昨年秋に開催した4回の連続研究会の採録だ。気象予報士でもある田家康・農林中金総合研究所客員研究員は、「気候変動」ではなく「気候変化」が実態だと指摘し、1次産業に及ぼす具体的な影響を説明している。例えば、水田・稲作の場合は、高温障害よりも水不足の影響が深刻だと警告する。山岳に貯蔵されて春以降に水源となる雪が減少し、田植えの時期に水を供給できなくなるからだ。
木之内均・東海大学熊本キャンパス長は、これまで冷害対策が主流だった品種改良や技術体系が熱帯研究に転換していくとみる。新潟大学農学部の山崎将紀教授と伊藤亮司助教は、新潟県の稲作に関する耐高温品種の開発や栽培管理技術などの実践を報告した。海洋生態系や水産資源については、国際捕鯨委員会日本代表代理などを務めた小松正之・生態系総合研究所代表が「著しい影響と言うよりも、死ぬ寸前」と危機的な状況を伝えている。
一般社団法人 農山漁村文化協会(農文協)から2025年2月17日に出版された。1320円(税込み)。
(共同通信アグリラボ編集長 石井勇人)
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)