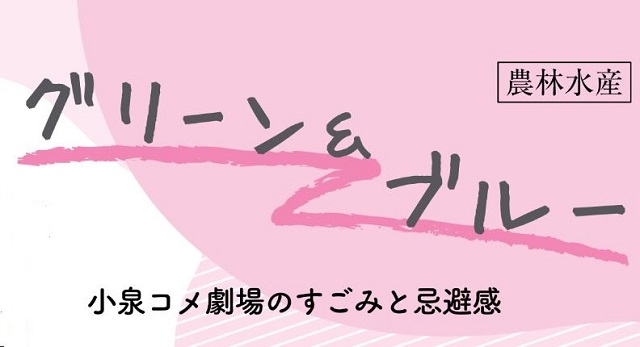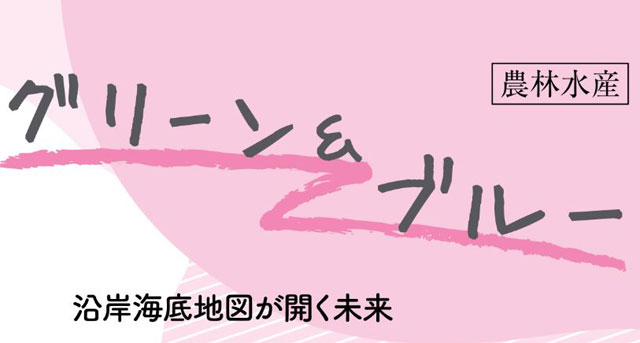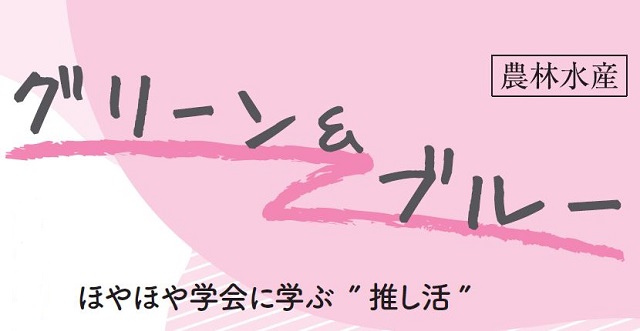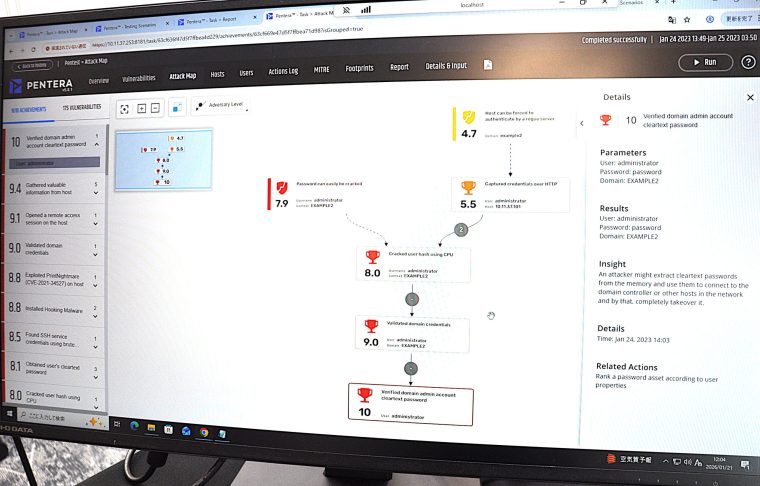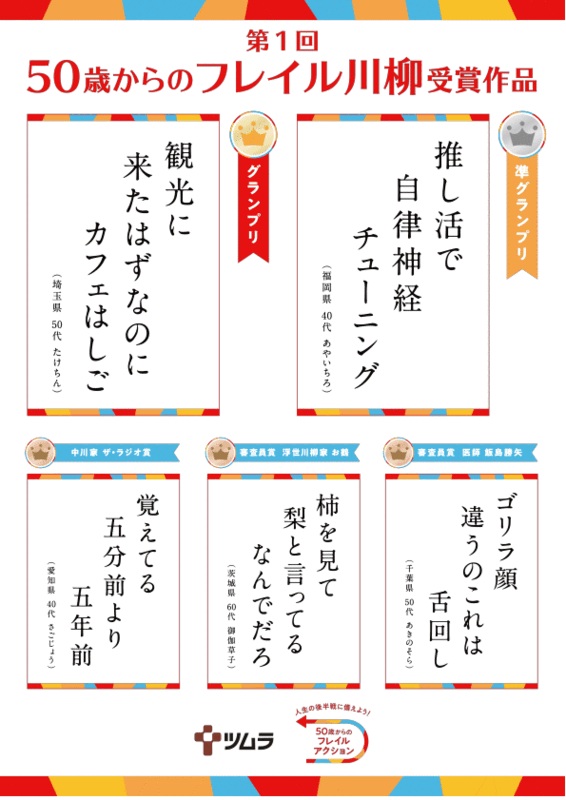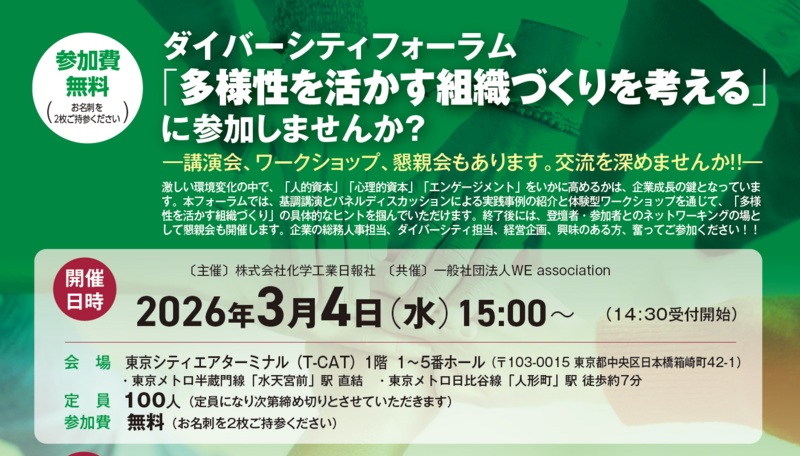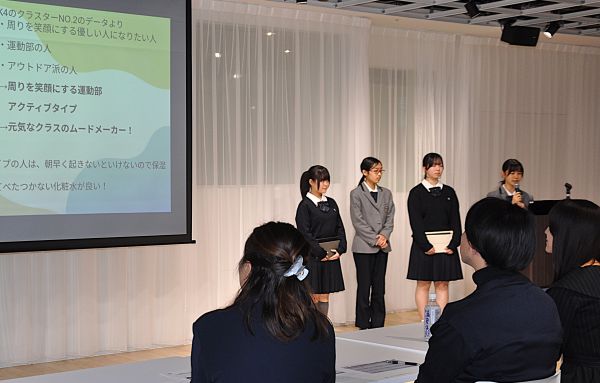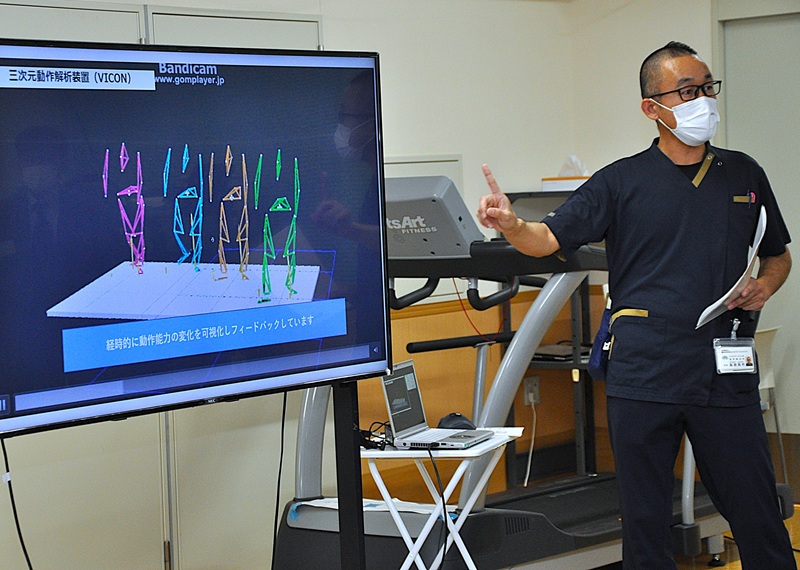2月初めに宮城県南部の山間地に赴いた際、たまたま入ったレストランで隣り合わせた人から、近くの道の駅で「ばっけ」が売りに出ていると聞いた。
「ばっけ」とは東北の方言でフキノトウのことである。熱湯をくぐらせたフキノトウを味噌(みそ)で和えた「ばっけ味噌」は、ほろ苦い味わいが箸休めによく、酒にも合う。
フキノトウは春の訪れを感じさせてくれる。山菜のシーズンが今年も始まったかと心が浮き立つ。
まだ東京に住んでいた30年ほど前、東北のある山村を取材で訪れた際、山を伐開して日当たりを良くし、ワラビ園を造成したと地元の人から聞いて「わざわざ木を伐(き)ってまですることなのか?」といぶかしく思った。
だが、その後、林業の取材を続けるうちに、山里の人たちにとって山菜が特別な存在であることがだんだんとわかってきた。かつての自給自足に近い暮らしの中では、数少ない現金収入の途のひとつであり、また、干したり塩漬けにしたりして食べ物が乏しくなる冬場に備える保存食にもした。
シーズンになると家族総出で山に行き、山菜を大量に採るのが習わしで、そのために新潟県のある山間地では、かつて「ゼンマイ採り休み」といって小学校を1週間ほど休みにしていたことがあったと聞く。
現在も森林組合や婦人会などが共同で運営している山菜加工施設は各地にある。それらの施設で瓶詰などに仕立てられた商品は、都会のスーパーなどに出荷され、あるいは地元の道の駅などでも販売されて、現金収入をもたらしてくれる。
そして山菜は長く厳しい冬が終わり、山や田畑できびきびと立ち働く季節の訪れを象徴する存在でもある。出盛りの機会を逸すまいと山菜採りに出かける山里の人たちは、どこかうれしげであり、気持ちを浮き立たせていることが傍から見てもわかる。
私の住む山村でも春先に共有林の一角がワラビ採りのために開放される日があり、集落の人たちは大きなビニール袋や背負い籠をいっぱいにしてなお、そこにもあそこにもと形の良いものをみつけては採り続けて倦(う)むことがない。
昨年、塩漬けの名人を取材してその手法を詳しく聞き取る機会があった。今年は私もワラビやフキを大量に採って塩漬けにし、冬場の食卓に彩りを添えたいと思っている。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.8からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)