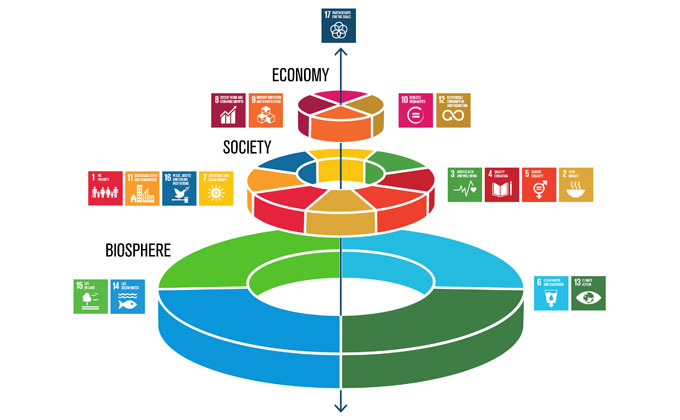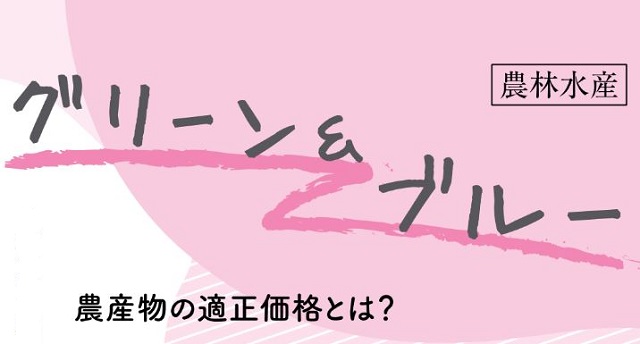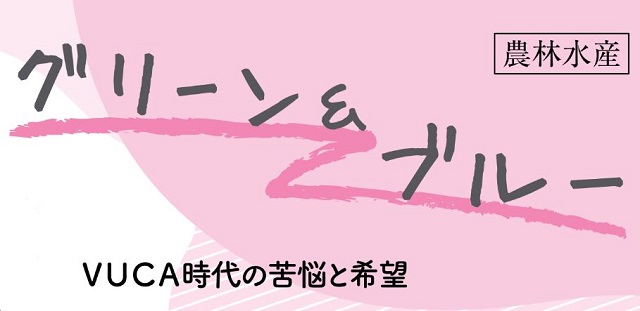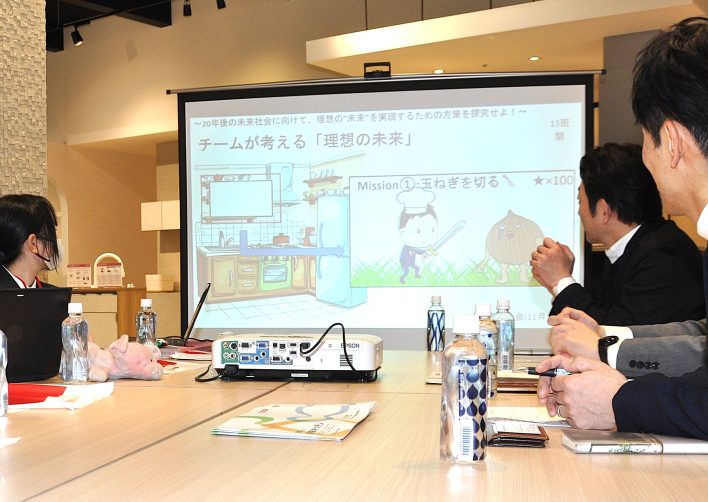久しぶりにヨーロッパを訪れたこの春、スペイン・グラナダの街角で懐かしい〝顔〟に出合った。スペイン北部に広がるカンタブリア海のアンチョビだ。
アンチョビとは、カタクチイワシの塩漬けのこと。頭と内臓を除いて開いた新鮮なカタクチイワシを塩漬けにし、発酵・熟成の後にオリーブオイルを注いで保存した缶詰や瓶詰といった伝統的な加工品は、イタリア産やスペイン産が良品として知られている。
なかでもスペイン北部、カンタブリア海のカタクチイワシを使ったアンチョビは、料理界でもファンが多い高級品だ。水温の低い海でゆっくりと大きく育ったカタクチイワシの特徴は、その身にたっぷりと抱え込んだ濃いうまみ。食べ応えのある大きめのフィレを丸ごと、トマトのピューレやオリーブとともにパンに載せたシンプルなピンチョスはもちろん、パスタやサラダに忍ばせれば最上級の美味を楽しめる。
7年前、私がこのカンタブリア海のすばらしい水産資源回復ストーリーを知ったのは、ひょんなことがきっかけだった。
「この海のアンチョビがまた味わえるようになったんだ。みんなでイワシを守った成果だよ」
レストラン取材で会った現地シェフの何げない一言。それがどうしても気になって、地元の水産研究所を訪れたのだった。
過剰漁獲が続いていたカンタブリア海で、カタクチイワシ資源が激減したのは2005年のこと。研究所が出した警告を受けて、州政府はなんと、翌年からの無期限完全禁漁と漁業者補償を即断したそうだ。漁業者は方針を支持し、アンチョビの加工事業者も他国産のカタクチイワシを製品化することで急場をしのいだ。すると州民は品質が同じでないことを知りながら、事業者を守るためそのアンチョビを買い支えたのだという。こうして人々が一丸となった5年間の後、かの地のカタクチイワシ資源は奇跡的な復活を遂げ、加工事業者も存続し名産のアンチョビも食卓に戻ったのだ。
カンタブリアの海が教えてくれた通り、生物である魚は守れば増える資源だ。しかし足元を見ると、私たちの海では科学的根拠に基づいた資源管理が遅れ、カタクチイワシをはじめ現在も減少を続けている魚種が数多い。この先もずっと、いりこ出汁(だし)の味噌(みそ)汁やシラスが食卓に並ぶ未来はあるだろうか。グラナダの青い空の下、7年ぶりの極上アンチョビを味わいながら、遠い日本の海を思った。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.17からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)