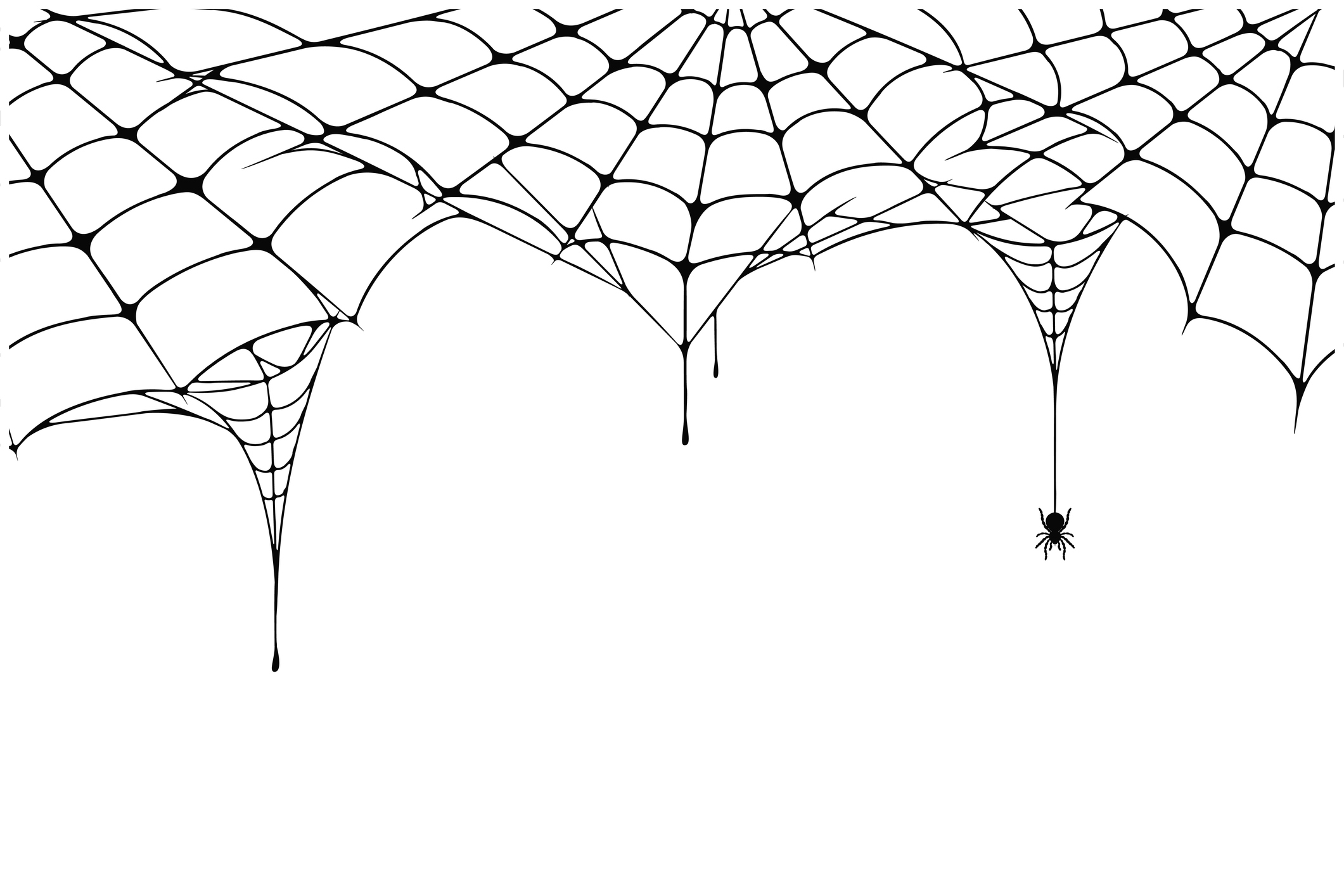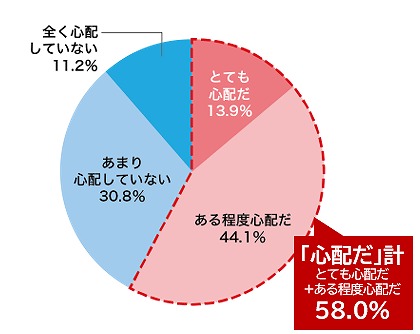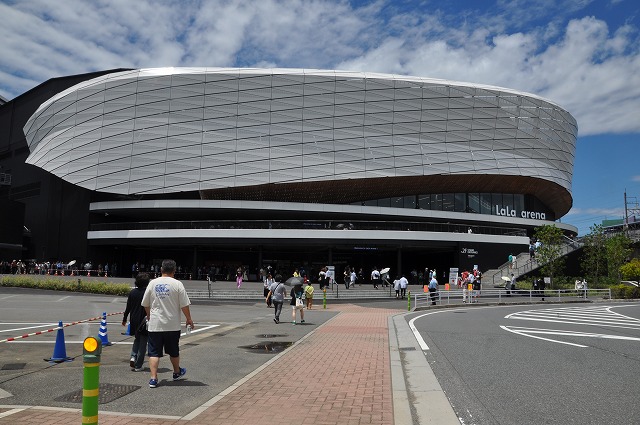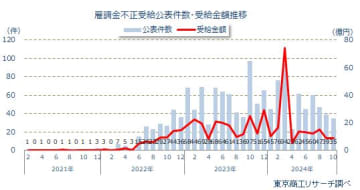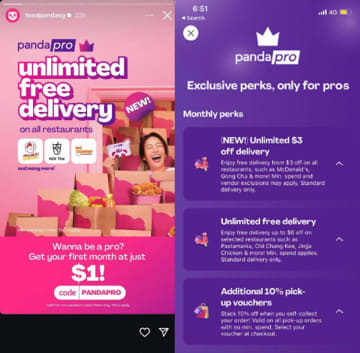芥川龍之介が「蜘蛛の糸」を著したのは、もう100年以上も前のことであるが、今も子どもたちに読み継がれている。自分だけ地獄から抜け出そうとする無慈悲な心によって、カンダタが再び元の地獄に落ちてしまうという短い物語の中には、子どものみならず、大人への大きな教訓も含まれる。
永田町を「血の池地獄」にたとえることは決して適切ではない。しかし、最近の“永田町劇場”の舞台裏を見聞きしていると、蜘蛛の糸にしがみついて必死に登ろうとするだけでなく、「下りろ、下りろ」と言わんばかりに他者を振り落としにかかる光景が想像される。もっとも、腕力による競い合いの方が、実際の永田町政治よりもはるかに分かりやすい。
岸田文雄政権の支持率が低迷して久しく、回復の兆しは見られない。韓国政府の歩み寄りによって日韓関係の正常化が図られつつあっても、さらに、たとえ岸田首相が電撃的なウクライナ訪問を果たしたとしても、支持率が不支持率を上回るようになるとは考えにくい。「反転攻勢の起爆剤になるような材料が見当たらない」(官邸関係者)のである。
しかし、岸田首相にとっての救いは、政権獲得を目指すべき野党各党も、ポスト岸田を狙う自民党内の面々も、「一本の糸」を巡って水面下でつぶし合っていることである。自民党三役経験者の一人は、「総理は腐っても鯛。束になっても敵わないかもしれないのに、野党も総裁候補たちも束にさえなっていないどころか、足の引っ張り合いを繰り返している」と嘆く。
2021年10月に岸田政権が発足してしばらくは、茂木敏充幹事長や林芳正外相、高市早苗経済安保担当相、河野太郎デジタル担当相などがポスト岸田の有力候補として報じられた。だが、出所は不明ながら、さまざまなネガティブ情報が飛び交ったり、虫眼鏡を当てることによる印象操作が行われたりして、結果的に4人への期待度はかなりしぼんできている。
火のない所に煙は立たぬと言うが、今や小さな火種でもあればうちわであおられ、容易に足元をすくわれかねなくなっている。火種がなくても煙が立つこともあるため、もはや何が真実であるかの見極めが難しい場合もある。最近の林外相のG20欠席問題も、放送法の解釈変更を巡る行政文書問題も、事の本質の他に、何らかの政治的な背景もあるのではないかと勘繰る者さえいる。
清和政策研究会は自民党の最大派閥であるが、安倍晋三元首相が凶弾に倒れてから8カ月が過ぎてもなお、後継者は決まっていない。それどころか、やはり「一本の糸」を巡り、水面下では激しい情報戦と所属議員の囲い込みによる“骨肉の争い”が繰り広げられている。そして誰かがカンダタのように「この糸はおれのものだ」と言い張った瞬間、安倍派は分裂し、糸が切れてしまう可能性が高い。
こうした争いを“切磋琢磨”と呼べば美しく聞こえるが、「政策論争を抜きにした足の引っ張り合い」(閣僚経験者)にほかならない。その結果、たとえ低支持率でも、早くも永田町では「ポスト岸田は岸田」とささやく者が増えつつある。野党もこの体たらくであるため、年内にも行われると見られている衆院選で自民党が負けることは考えられず、岸田首相は来年秋の総裁選で難なく再選されるとの予想である。
だが、果たしてこれで民主主義が機能していると言えるのかと問われれば、答えは否であろう。野党も総裁候補も協力や連携を拒むどころか、潰し合う結果、政権党の選択肢も、総理総裁の選択肢も、実質的に存在しなくなっているのである。コーヒーに飽きて紅茶を飲もうとしても、そもそも紅茶が用意されていないのと同じでことであり、これは国民にとっても、消費者にとっても、この上ない不幸なことである。
せめて二者択一の政治状況が提供されれば、政治に緊張感がもたらされるし、国民の政治的関心は高まるはずである。しかし、現実に見えるのは釈尊の悲しい顔よりも、国民の不満げな顔ばかりである。
【筆者略歴】
本田雅俊(ほんだ・まさとし) 政治行政アナリスト・金城大学客員教授。1967年富山県生まれ。内閣官房副長官秘書などを経て、慶大院修了(法学博士)。武蔵野女子大助教授、米ジョージタウン大客員准教授、政策研究大学院大准教授などを経て現職。主な著書に「総理の辞め方」「元総理の晩節」「現代日本の政治と行政」など。
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)