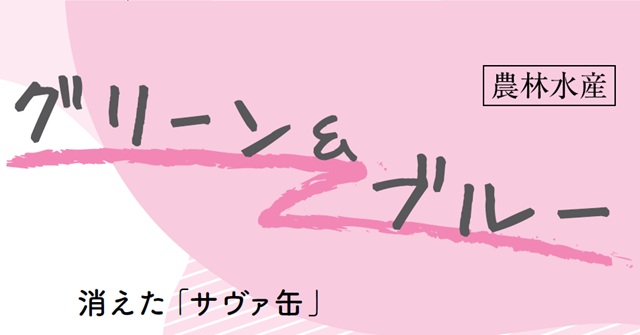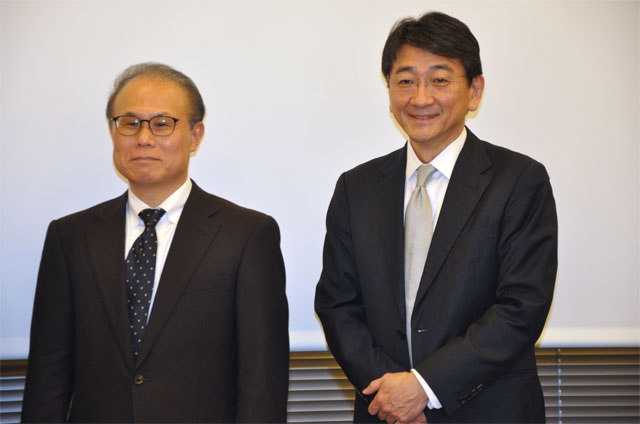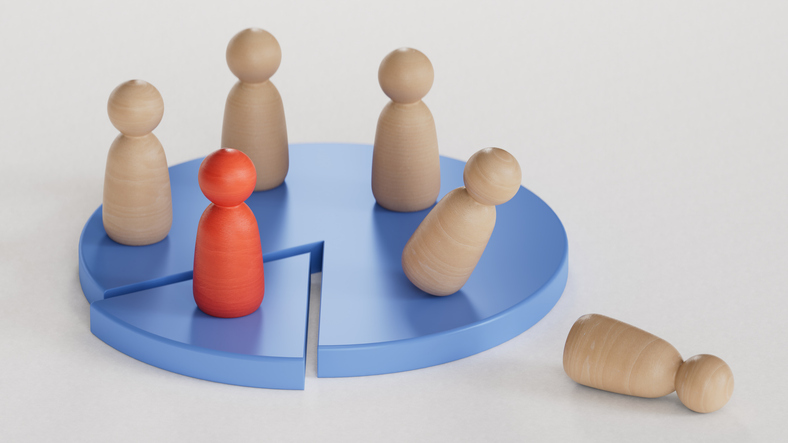岩手県の国産サバ缶ブランド「サヴァ缶」が今年、販売終了したことをご存じだろうか。「サヴァ缶」は、東日本大震災からの復興を目的として2013年に開発され、黄色やグリーンなど店頭で目を引くカラフルなパッケージと、レモンバジルやアクアパッツァなど5種類の洋風フレーバーで人気を博した缶詰ブランドだ。
岩手日報社の記事(6月20日付)によると、「累計販売数1200万個以上の人気だが、サバの不漁や原材料のコスト増、製造工場の休止が重なった」ためだという。全国的なサバ缶ブームの火付け役となった「サヴァ缶」が消えたことは、業界で大きなショックをもって迎えられた。
では、サバはどれくらい不漁なのだろうか。農林水産省の統計によると、24年度のサバ類漁獲量(マサバ・ゴマサバの総計)は26万トン。サバの漁獲量は資源量の長期的な変動により大きく上下し、1970年代の太平洋側だけで100万トンを超えていた時代と比べて激減していることは事実だが、一方でマイワシの67万トン、ホタテガイの32万トンに次いで日本3位の漁獲量を誇る魚種だ。つまり決して「獲れていないわけではない」。
ではその26万トンの漁獲が、どのような用途に使われているのかを見てみよう。主要32漁港の2024年サバ類の用途別出荷量割合を調べてみると、用途として最も多いのが、クロマグロを中心とした水産養殖や漁業用の飼料で、なんと6割近い59パーセントを占める。次点が缶詰向けで15パーセント、干物など、その他食品加工向けが14パーセント、生鮮食用向けはわずか11パーセントという内訳だった。
用途がなぜここまでアンバランスになっているのかといえば、漁獲が幼魚に集中しているからだ。サバ類の年齢別漁獲尾数推移を見てみると、寿命6〜7年のサバ類の漁獲は圧倒的に0歳、1歳の小サバが中心で、サバの塩焼きにできるサイズの生鮮流通はもちろん、加工品を作れるサイズの流通も少ない。
成魚に成長する前に漁獲する量が多ければ、産める卵の量が減るため資源量は減少する。資源が減り、漁獲が減れば、市場原理の中で価格は上がるのが通常だ。鮮魚であれ加工品であれ、私たちが魚を食べ続けるために何が必要か、環境変化を踏まえ、皆で考えるべきステージにあるように思う。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.32からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)