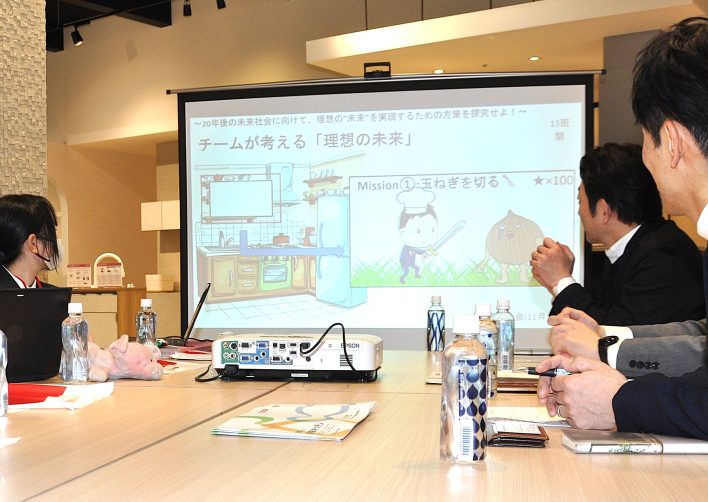オオサカムセンデンキ▼究極の塩おにぎりの開発

「父と母がこの会社を作って66年。記念に何か面白いことをやろうと思って、ノリで始まったんです」
そう話すのはオオサカムセンデンキ(大阪市)の島田明浩常務だ。1970年大阪万博の思い出を大切にしている両親のために、「清水の舞台から飛び降りる」つもりで、大阪ヘルスケアパビリオンへの協賛を決意した。
参加したのは、「ミライの食と文化」ゾーンの食物販。展示扱いのため家賃や光熱費はかからなかったが、協賛金を回収するには果てしなく遠い道のりに思えた。
全てを入社3年目以内の社員に任せての商品開発。写真映えを狙ったチュロスをキッチンカーで試験販売してみたが、売り上げが伸びず断念。島田常務が「ご飯が好き」だったことから、「おにぎり専門店」にかじを切った。
ヘルスケアパビリオンであることから健康志向を重視し、ビタミンやミネラルを豊富に含むとされる兵庫県産ヒノヒカリを使用。1年間の試行錯誤を重ね、温泉水で炊くまろやかなご飯にたどり着いた。さらに、知り合いの飲食店からの紹介で、高知の塩職人・田野屋塩二郎さんの天日塩を知った。注文は数カ月から数年待ちだったが、頭を下げに現地に向かった。
「ちょっと高かったので最初は値切ろうと思っていたんです。でも、塩二郎さんが塩作りをしている姿を見たら、とても値切れないなと。塩おにぎりは“万博価格”とも言われましたが、まさに命懸けで塩を作っていたんですよ」

炊飯には「かん水(塩になる前の水)」を絶妙な割合で混ぜ、おにぎりに合うオーダーメードの粗塩を別包にした600円の究極の塩おにぎりが完成した。
「自分の思いを持って語れる商品じゃないと意味がない」。社員一人一人が“自分の物語”を持てるよう、海賊サンドやお重など、メニューを社員全員で考えた。具材の産地にもこだわった。レタスや卵焼きは大阪産を利用。牛肉は、両親の故郷・淡路島の「淡路ビーフ」を採用した。
▼社員全員で万博へ、累計35万食販売

「中小企業、特に携帯ショップって本当に人が集まらなくて。万博に関わることで、万博に参加した企業ということで働き続けてもらうことも目的でした」
新入社員6人は万博勤務を前提に採用。社員総出で出勤し、素手でご飯を握り、バックヤードでラベルを貼った。
「ここのおにぎりを毎回買っている」「どこにお店があるの? お店作ってください」「次の予約が取れなくて、今日が最後だからお礼が言いたくて来た」。来場者から思いもかけない言葉が次々と寄せられた。
塩おにぎりはSNSで拡散され、気が付けば連日完売。おにぎりを持った小泉大臣(前農水大臣)と吉村知事のツーショットが投稿され、人気に拍車がかかった。その結果、塩おにぎりだけで5万食、全メニュー累計で35万食を販売。パビリオン内トップの売り上げを記録していた。
「想定の倍、10トンの米がなくなりました。予想以上に売れたことで契約していた量の3倍の塩が必要になり、週末を乗り越える塩がないとか、しょっちゅうでした」

▼万博に“参加する”ことで得たもの

「万博への参加はお金には変えられないもの。万博という祭りに参加することに社員みんなが乗ってくれた。一つの目標に向かって会社が一つになっていましたね」
万博参加後、同社の離職率はほぼゼロになり、採用面接の応募者も集まるようになった。同社には利益の約3割を社員に分配するルールがあり、「今回の万博の売り上げも、従業員全員で分け合うつもり」だという。
万博の次に見据えるのは植物工場。コロナ禍中に沖縄で取得した土地で、野菜の水耕栽培の実証実験を始めた。周辺のホテルや飲食店と契約し、できた野菜を全数買い取る仕組みを考えている。
「農業は“きつい・汚い・収入が少ない”というイメージを変えたい。植物工場は室内でできるし、安定した収入を得られるなら“やりたい”という若い人が増えるはず。そうすれば、農業の担い手不足が解消される」
将来的にはコンテナで米を育て、砂漠でも生産できる“未来の食”を目指している。
「僕らは“塩おにぎりロス”。チャンスがあれば、またどこかで販売したいと思っています。祭りみたいに、スタッフが笑って楽しくやれるのが一番」

万博参加で得た“お金では買えない価値”を次の世代にどうつなぐか。オオサカムセンデンキの新たな挑戦が始まる。
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)