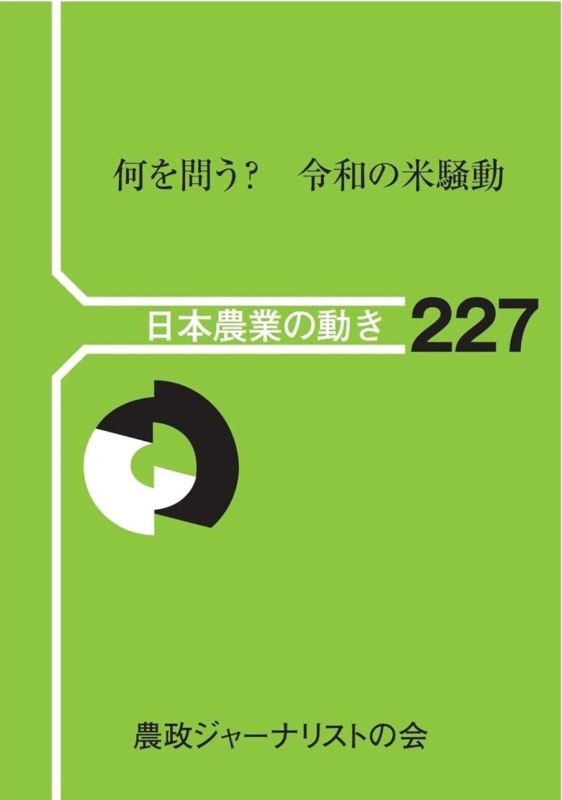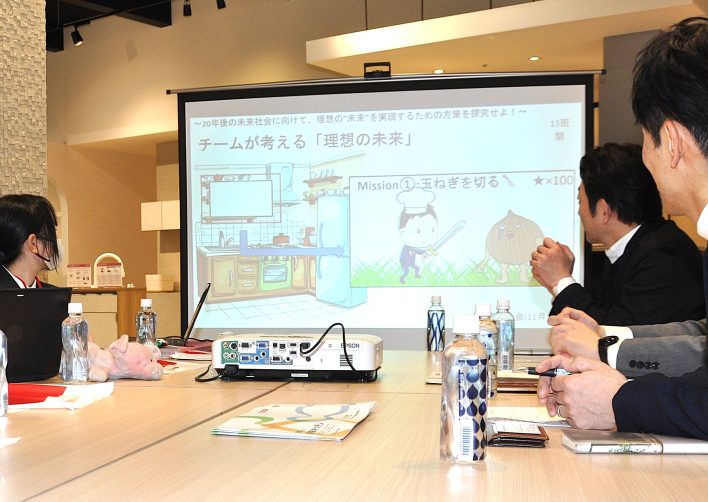水産庁は10月31日、小型漁船によるスルメイカ釣り漁に対し、配分された漁獲枠をすでに超過しているとして来年3月までの採捕停止命令を出した。スルメイカの採捕停止命令は、国内で漁獲可能量(TAC)制度が始まった1990年代以降初であり、メディアも大きく取り上げている。
これまでの経緯をごく簡単に振り返ってみよう。まず大前提としてスルメイカは激減しており、資源は深刻な状況にある。1963年には59万トンもの漁獲量があったが2000年には30万トン、24年は1・8万トン。
24年末に水産研究・教育機構が計算した資源量推定値も、「限界管理基準値」と呼ばれる限界ラインを大きく下回っており、卵を産むべき親が足りていない。
そのため、今年4月からの年間漁獲枠検討時、科学者の当初推奨値は1万トン、つまり前年の漁獲実績を下回っていたが、水産庁は「漁業の経営その他の事情を鑑みて適切ではないと農林水産大臣が特に認める場合」として設定ルールを変更。結果的に1・9万トンが採択された経緯がある。
さらに期中である9月には漁獲枠の拡大が行われ、6千トンあまりが追加された。夏に太平洋側の漁獲量が想定以上に積み上がり、「操業停止という事態も想定されることから、関係業界からは迅速な追加配分を求める声が高まっていた」(9月17日付『水産経済新聞』)ためだ。
つまり現状、スルメイカに関しては科学者の推奨値を超える漁獲枠が設定されており、ただでさえ危機的な本資源の未来を考えれば、これ以上の増枠は行うべきではない。そして漁獲枠に達した際の操業停止は当然のルールであり、今回の採捕停止命令は順当な措置だと言える。
スルメイカは漁業者にとっての大切な商材である一方で、国民にとっては守るべき重要な食材だ。さらには日本にとっては貴重な資源であり、海の生態系を構成する上で必要不可欠な生物でもある。
今回のような漁獲枠の期中改定が二度と行われないために、多くの漁業者にとって未経験である漁獲枠の計画的消化に向けて、今後水産庁には情報共有と適切な制度設計をお願いしたい。そしてより精度の高い見通しのもとで漁獲枠を設定するために、きめ細やかな研究を目指した環境と予算の整備を早急に進めるべきだろう。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.43からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)