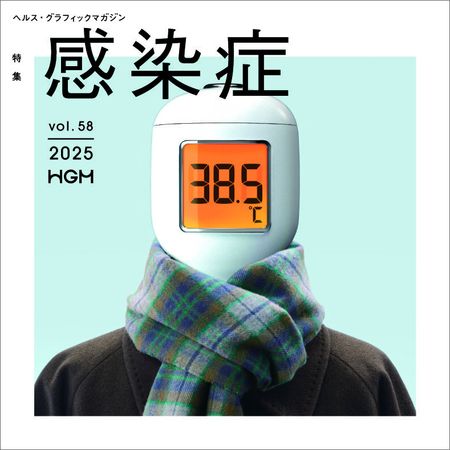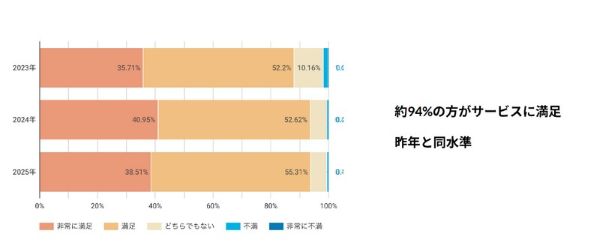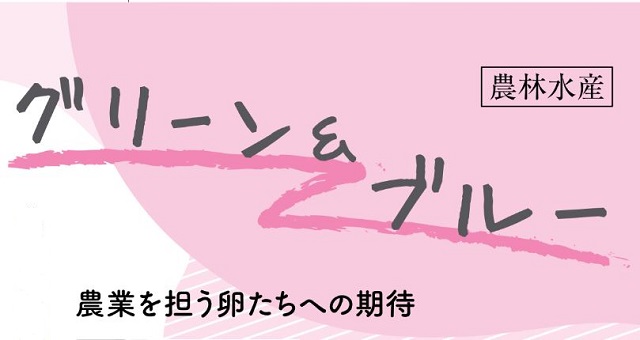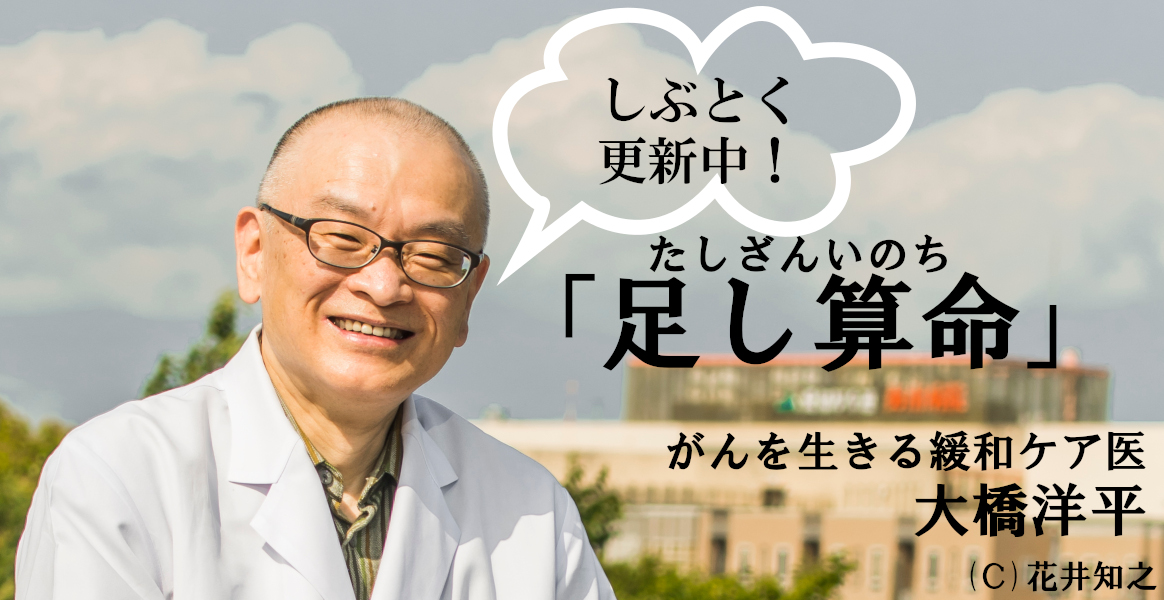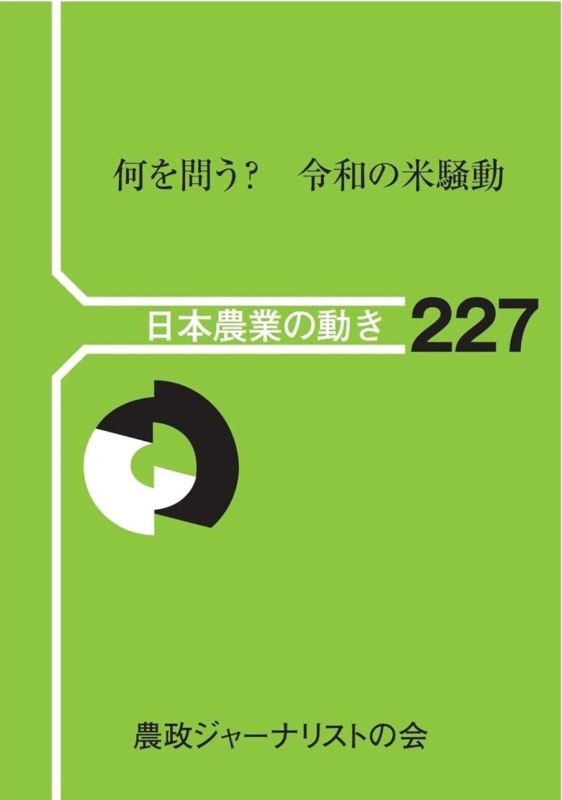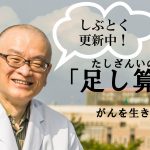福島県の旧都路(みやこじ)村(田村市都路町)は、南北に連なる阿武隈山地の真ん中あたりにある。
3月の中ごろ。あいにくのみぞれ交じりの雪の中、県内外の約60人が集まって、毎年恒例の植樹会が開かれた。6メートルほどのメタセコイア3本に約2メートルのイロハモミジ、イタヤカエデ、コブシなど計13本。苗木を植える人たちの中には、次世代の子どもたちの姿もあった。
5年目の今年は、都路街道(国道288号)沿いに広がる耕作放棄地が中心で、道ゆくドライバーに「山の再生」をアピールすることも狙いだった。
植樹会を主催した「あぶくま山の暮らし研究所」理事長の青木一典さん(63)は「農地や山を元の姿に戻して、自然にお返しする。原発事故の直後に植えたモミジの幹は、両手でつかめるほどに成長しました」。
青木さんの自宅は東京電力福島第1原発から約25キロ。農家の4代目として黒毛和牛経営を継いだが、事故後に断念。森林組合で働きながら独自に植林を続けてきた。青木さんの背中を見て集まった地元住民や県内外の林業関係者、森林研究者らが5年前に立ち上げたのが同研究所だ。
「150年先も、阿武隈の山とともに」と、ホームページは謳(うた)う。原発事故で山に降りかかった「放射性セシウム137」の半減期は30年。これが数パーセントに減り、ほぼ日常の暮らしが戻るのは150年先という計算だ。もうひとつ。「明治維新以来150年、開発を優先した地域づくりの考え方を改める」との思いも込められた。
阿武隈山地は広葉樹が多く、もともと炭焼きを生業としてきた歴史がある。日本の燃料が石油に代わる1960年代に、コナラなどを原木としたシイタケ生産に様変わりした。事故前の阿武隈山地は、質の良いシイタケを生産する日本有数の原木生産地として知られた。
それが原発事故で途絶えた。
福島県の7割を占める森林は除染をしていない。というより、除染をすると、地表から5センチの山の表土に含まれている土壌保全機能などが失われてしまうからだ、という。
ただ、待つだけではない。
今回の植樹会の集合場所になった中央森林組合都路事業所は、県の森林再生事業を活用して、コナラの伐採、植林を進めている。今ある原木が使えないなら、新しく育てて20年後にシイタケ用原木として生産できないか、という試みだ。
事業所に勤める青木さんは言う。「出荷できるか分からないけれど、とにかくトライ。森林は50年、100年で巡ります」
都路街道は、その名の通り、海岸沿いの双葉町から江戸へ木炭を運ぶルートだった。事故後、双葉町の「中間貯蔵施設」は県内の除染土を丸ごと引き受けた。が、20年後の「県外最終処分」を国は法律で定めながら行き先は決まっていない。
除染土処理問題への全国的な無関心に危機感を強めた双葉町長は2月、改めてアピールした。「原発のエネルギーを首都圏で利用した過去を、ご存じない方があまりに多い」
放射能汚染への関心が薄れるのに乗じるように原発再稼働が加速する中、150年先の再生を目指し、故郷の山に向き合う人々は黙々と木を植え続ける。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.13からの転載】
![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)